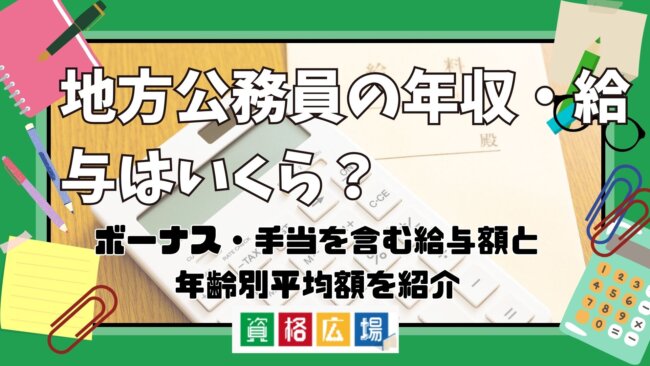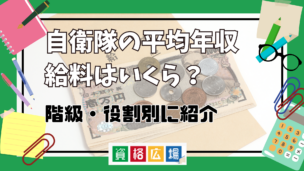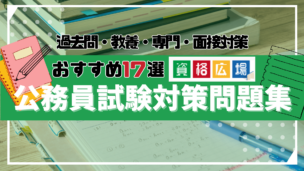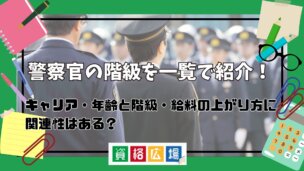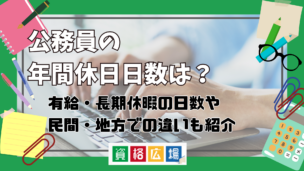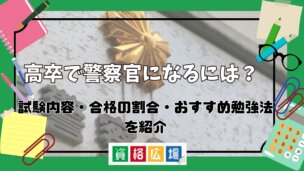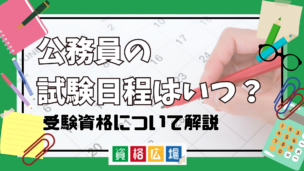地方公務員とは、地方自治体で働いている公務員のことです。
具体的には、都道府県や市町村や消防、教員、警察などが挙げられます。
公務員は安定した収入であることから目指す人も少なくありません。
しかし実際、「公務員ってどれくらいの給料をもらえるの?」「公務員の給料って高いって本当?」と気になる方もいるのではないでしょうか?
そこで今回は、公務員の給料事情について詳しくご紹介します。
公務員を検討している方はぜひ参考にしてみてください。
この記事で分かること
- 地方公務員の年収
- 地方公務員の給与やボーナスの仕組み
- 地方公務員の手当について
国家公務員と地方公務員の違いとは?年収・試験難易度・仕事内容の違いをわかりやすく解説
公務員の年収・給与は平均いくらぐらい?職種・年齢別の給与から年収推移・手当やボーナスまで紹介
市役所職員(地方公務員)の年収・手取り給与はいくら?民間から転職のケースや高卒・大卒の違いなどを紹介
公務員の給料について
早速ですが、今回の記事のメインテーマである公務員の給料についてまとめてご紹介します!
公務員の区分による違いにも着目しておりますので、ぜひご覧ください!
国家公務員の年収はおおよそ550万円程度
まずご紹介するのは、省庁に勤務する形で国政にダイレクトに関わる業務を行っている国家公務員の給料についてご紹介します。
人事院が公開している資料によると、仮に一般職に進んだとした場合の国家公務員の給料は下記のようになっているようです。
| 平均給料(月額) | 334,218円 |
|---|---|
| 平均給料(年収) | 約5,500,000円 |
※年収の算出方法 平均給料×12+平均給料×4.5ヶ月(ボーナス)
公式に発表されている資料を参考にしたところ、国家公務員(一般職)の平均給料や年収はこのようになっておりました。
国家公務員についてもっと深掘りしたい方は、ぜひこちらの記事もご覧ください!
→国家公務員総合職(旧I種)資格取得の難易度は?試験情報・報酬相場を徹底分析
地方公務員の年収はおおよそ500万円程度
続いてご紹介するのは、都道府県や市区町村に密着した業務を行う地方公務員の給料について調査しました。
今回は都道府県の庁舎に勤務した場合と仮定し、給料のシュミレーションを行っております。
| 平均給料(月額) | 315,093円 |
|---|---|
| 平均給料(年収) | 約5,200,000円 |
※年収の算出方法 平均給料×12+平均給料×4.5ヶ月(ボーナス)
こうして比較すると、地方公務員の給料は多少なりとも国家公務員と違いが生まれているのが現状のようです。
地方公務員のお仕事についてもっと知りたい!という方は、ぜひこちらの記事をご覧ください!
公務員の給料体系は国家公務員・地方公務員によって異なる
国家公務員と地方公務員の給料体系は異なり、国家公務員は「俸給表」に基づいて給料とボーナスが支給されますが、地方公務員は各自治体で定められた「給料表」によって給料が決まります。
どちらも一般企業と同様に年齢や勤続年数に応じて給料が上昇する仕組みとなっています。
俸給は基本給を指し、職務の難易度などに応じて決定され、職種によって給料は異なるケースがあります。
たとえば国家公務員でも国税庁の職員といった専門知識が必要な職種であれば、高めの設定となっています。
給料は年齢や勤続年数に応じて徐々に上昇しますが、若い時期は比較的低くなりがちです。
また、俸給は能力によらず一律ですが、ボーナスは勤務実績に応じて決まります。
なお公務員の給料は、国全体の平均値をオーバーまたは不足しないよう設定されています。
給料が高すぎると国民からの不満が生じる可能性があり、逆に低すぎると公務員の採用に困難が生じる可能性があります。
上記のように公務員の給料は一律ではなく、能力や職務の難易度に応じて変動します。
ほかにも、年齢や勤続年数に応じて徐々に上昇するため、安定した収入が期待できる一方、入社当時や若い時は比較的低い収入になりやすくなります。
地方公務員とは?
日本では、地方自治体にまつわる業務を行う地方公務員と、国にまつわる業務を行う国家公務員があり、合わせて333万人もの人が公務員として働いています。
すなわち、全国民の40分の1に相当する人数が公務員として働いている計算になりますが、その中でも地方公務員は人数が多く、全体の約8割が地方公務員となっています。
地方公務員とは、都道府県や市町村、消防や警察といった地方自治体で働く公務員を指します。
地方公務員の年収は?
令和3年度の総務省の調査によると、地方公務員の年収は約643万円、平均基本給月額は343,207円となっています。
さらに基本給には月額支給される手当(扶養手当・地域手当・通院手当・特殊勤務手当・時間外手当・そのほかなど)が加算され、合計すると約40万円程度になるとされています。
公務員は、勤続年数が基本給に直結する、年功序列の給与制度なので20代、30代の若手公務員はこの平均よりは、収入が低くなっております。
参照:総務省
地方公務員の初任給はどれくらい?
総務省の調査によると、地方公務員の初任給(一般行政職)は大卒で平均187,623円、短大卒で167,464円、高卒で154,067円といわれています。
ちなみに国家公務員は人事院の調査によると一般職の場合、大卒程度で222,240円、高卒程度で180,720円となっています。
さらにここに諸手当などが加わるので実際は、上記よりもやや上がる見込みとなります。
また地方公務員の1年目の平均年収は大卒だと3,095,780円、短大卒は2,763,156円、高卒は2,542,106円程度と考えられています。
地方公務員のボーナスは?
地方公務員のボーナスの平均支給額は約161,6万円といわれています。
地方公務員のボーナス支給額や支給日は各地方自治体の人事規則を元に定められており、所属する地域によっても異なります。
総務省の都道府県別の給与実態調査によると、最もボーナス額が多いのは東京都で平均179,5万円、最下位は鳥取県で薬139,8万円となっています。
ちなみにボーナス支給日は地域によって多少の違いがあるものの、国家公務員のボーナス支給日(6月30日・12月10日)と同日もしくは前後に支給されるのが一般的です。
公務員のボーナスはおもに在籍期間と勤務成績が反映される仕組みとなっています。
参照:総務省
公務員のボーナス支給日はいつ?民間企業との違いや平均額を紹介
年齢別で見る地方公務員の平均年収
地方公務員の給料は、年齢や勤続年数を重ねていくと徐々に増えていくのが一般です。
また、公務員の年収は大卒か高卒かによっても異なり、大卒の方が高卒よりも10万円程度高くなっていることが多いです。
ここでは、総務省が発表する地方公務員給与の実態を参考に、年齢別の地方公務員の平均年収についてご紹介します。
20代の平均年収
20代の平均年収は大卒で約303万、高卒で約288万円と言われています。
20代の公務員は年功序列制なので、長く勤務すれば勤務するほど給料もあがり、充実した福利厚生も享受することができます。
30代の平均年収
30代の平均年収は大卒で約434万、高卒で約423万円と言われています。
20代と比べて仕事上の責任が増してきたり、役職が上がたりして給料も安定してくるのが30代です。
生活にも余裕ができ、結婚や出産などプライベートでも大きなイベントを迎える方が多いのがこの年代となります。
40代の平均年収
40代の平均年収は大卒で約595万円、高卒で約583万円と言われています。
先述の通り公務員は年功序列制なので、40代になれば家族がいても生活には困らない額の給与が支給されるようになります。
この年代で一戸建の購入を検討する方も少なくないようです。
50代の平均年収
50代の平均年収は大卒で約626万円、高卒で約602万円と言われています。
役職も上がり、大きな責任が伴う立場になる方もいるでしょう。
国全体の平均値をオーバーしないよう、1,000万円には届かないように設定されているものの、大企業で働く50代の平均年収(650万円)よりは多くなっています。
地方公務員の年収額はこの50代をピークになるといわれています。
参考:総務省
大卒公務員の収入
大卒の地方公務員と国家公務員の収入に関するデータは下記のようになっています。
| 国家公務員 | 地方公務員 (全地方) | |
|---|---|---|
| 平均月額給与 | 334,711円 | 325,991円 |
| 平均年収 (ボーナスを含む) | 約677万円 | 約633万円 |
国家公務員の平均年収は約677万円、地方公務員の平均年収は約633万円となっています。
12ヶ月分の月収に加えて、夏・冬のボーナスや手当を加えた数が年収です。
大卒の国家公務員・地方公務員の年収に大きな差はないことが分かります。
参考:人事院「令和4年国家公務員給与等実態調査 」
参考:総務省「令和4年地方公務員給与の実態」
大卒の公務員と民間企業で年収比較
| 公務員 | 民間企業 | |
|---|---|---|
| 平均月額給与 | 約650万円 | 約520万円 |
公務員の年収は、上記の「国家公務員と地方公務員の平均年収」から平均額を計算すると約650万円です。
民間企業の年収平均金額は正社員で523万円となっているため、公務員の年収は低いとは言えないでしょう。
しかしあくまで平均年収ですから、全ての公務員が年収600万円を超えているわけではありません。
特に公務員の場合、勤務年数が短い場合は大卒でも月収が低い傾向があります。
参考:国税庁「令和4年分 民間給与実態統計調査」
地方公務員の職種別の平均収入とは
地方公務員は大きく分けて一般職と特別職から構成されています。
一般職は主に、都道府県庁、市役所・役場、学校部門、警察部門、消防部門などに勤務し、特別職は、選挙で選任される自治体の首長や議会議員として従事します。
一般職の地方公務員の職種は、大きく分けて「行政職」「資格・免許職」「技術職」「公安職」の4つあります。
ここでは、それぞれの地方公務員の職種別で平均収入を見ていきたいと思います。
行政職
一般行政職の公務員は、いわゆるお役所仕事といわれるような事務的な仕事がメインとなってきます。
地域密着型なのが特徴的で、治安や消防、水道や交通などのライフライン、教育・文化事業など、業務領域は多岐にわたっています。
一般行政職の平均給与
平均月給 401,372円(平均年齢41.8歳)
平均年収 約620万円(平均年齢41.8歳)
一般行政職の公務員の年収は、平均給与額は約620万円となっています。
(※総務省の調査による「令和4年 地方公務員給与実態調査結果等の概要」より、これは平均給与月額315,093円に諸手当月額86,279円を加えた額で算出しています。)
また、令和4年賃金構造基本統計調査を元に算出した結果によると、中小企業の平均月収は29.3万円であり、平均年収は約410万円となっており、年収で比べると中小企業<公務員(一般行政職)といえます。
計算式:(中企業の平均月収+小企業の平均月収)÷2=中小企業の平均月収
中小企業の平均月収×12+賞与(平均月収×2と想定)=中小企業の平均年収
また、全上場企業の平均年収は約630万円であるので、企業にもよりますが統計上は大企業≒公務員(一般行政職)といえます。
資格・免許職
資格・免許職とは自治体が発行した資格を必要とする職業です。
例えば、「保健師」「看護師」「臨床検査技師」「栄養士」「幼稚園教諭」「保育士」などが挙げられます。
職業別にピックアップしてみると、同じ職種についても民間より公務員のほうが給料が良いというケースがあります。
地方公務員として働く看護師の平均年収は、584万円(平均年齢40歳)となっていますが、民間で働く看護師の平均年収は530万円程度と言われています。
また、給料が安いというイメージを持たれている幼稚園教諭においても、公立幼稚園教諭の月給においては、私立の幼稚園教諭よりも10万円高くなっています。
資格・免許職の給与が公務員>民間となるのは、公務員は「勤続年数が長いほど給与が高くなる」からといえます。
民間・私立の場合は出産や育休などで退職してしまうことがありますが、公務員の場合は、休暇制度が整備されているため仕事が続けやすく、必然的に勤続年数が長くなっているからです。
技術職
技術職で採用される公務員は技術系公務員と言い、その他に理系公務員とも呼ばれます。
技術職の種類は土木職、建築職、電気職、機械職、その他専門職(科学職、林業職、水産技術職、心理職)があり、県庁や市役所、市営の施設に勤務します。
技術系公務員の平均年収は400万円~600万円で、自治体や分野によって差があります。
土木職、建築職、電気職、機械職は採用人数が多いため四代技術とも呼ばれていますが、地方自治体によっては、採用人数が数名なんてこともあるので、より規模の大きい仕事がしたい場合は都道府県庁へ就職するほうが良さそうです。
公安職
公安職とは、国や地方自治体の治安維持のために従事する公務員です。
国家公務員の公安職は、海上保安官や皇宮護衛官、入国警備官、法務教官、刑務官などであり、地方公務員の公安職は、警察官や消防士が該当します。
警察官の平均年収は、700万円~800万円で消防士の平均年収は、720万円です。
警察官も消防士も危険が伴う仕事であるが故に、夜勤手当など○○手当と呼ばれるものが複数ついて、行政職や資格免許職の公務員と比べて給与額が高くなっています。
警察官も消防士も、階級によって年収が上がっていく制度になっており、公務員でありながら年収1000万円も狙える職種です。
福利厚生も整っており、警察官は20代前半でも家のローンが組めるようになっています。
地方上級公務員の仕事は楽?肉体的・精神的に負担が少ない理由や国家公務員との負担の違いを解説
地方公務員の生涯年収は?
生涯年収とは、人が一生涯の間に得られる給与の合計です。
公務員の生涯年収は職種や学歴によって異なりますが、おおまかに約2~3億円と言われています。
地方公務員を「行政職」「資格・免許職」「技術職」「公安職」に分け、それぞれの生涯年収をまとめました。
| 行政職 | 資格・免許職 | 技術職 | 公安職 | |
|---|---|---|---|---|
| 大卒 | 約2億6千万円 | 約2億5千万円 | 約2億6千万円 | 約2億8千万円 |
| 高卒 | 約2億2千万円 | 約2億1千万円 | 約2億3千万円 | 約2億3千万円 |
地方公務員の生涯年収を職種別にみると、最も高いのが公安職でその次に技術職・行政職が続き、最も平均金額が低いのが資格・免許職でした。
また学歴によって多少の差もあり、全体的に大卒の方が生涯年収は多いようです。
国家公務員の生涯年収と比較
地方公務員と国家公務員の生涯年収を比較し、まとめました。
| 地方公務員 | 国家公務員 | |
|---|---|---|
| 大卒 | 約2億6000万円 | 約2億8000万円 |
| 高卒 | 約2億1000万円 | 約2億5000万円 |
地方公務員と国家公務員の生涯年収を比較すると、大卒・高卒ともに国家公務員の生涯年収の方が高くなります。
国家公務員の場合、30~40代の比較的若い時からから高収入を得られる「キャリア」という特別な待遇のシステムがあることが、生涯年収の高さに繋がっているようです。
民間企業の生涯年収と比較
地方公務員と一般企業の生涯年収を比較し、表にまとめました。
分かりやすく一般企業は1,000人以上を大企業、それ以下を中小企業としています。
| 地方公務員 | 大企業 | 中小企業 | |
|---|---|---|---|
| 大卒 | 約2億6000万円 | 約3億3000万円 | 約2億6000万円 |
| 高卒 | 約2億1000万円 | 約2億7000万円 | 約2億1000万円 |
地方公務員と同じく、一般企業でも学歴で生涯収入に差が見られました。
最も生涯年収の平均が高かったのが大企業の大卒の生涯年収約3億3000万円で、最も低いのは中小企業の高卒で約2億1000万円です。
地方公務員の生涯年収は一般企業と比較すると平均的な金額でした。
公務員の給与の仕組み
ここまで、年齢や職種別で地方公務員の給与を見てきました。
職種によっても異なりますが、地方公務員の基本給は平均水準よりも高くなっています。
地方公務員の給料は、給料表の「級」と「号給」の組み合わせで支給額が決まります。
職種に応じて適用される給料表は異なります。
級は1~8級(9,10級)、号給は1~125程度まであり、給料表から列と行を合わせて参照します。
「級」とは、職務の複雑度、困難さ、責任の重さなどによって設定されます。
級が上がることを昇格といい、昇格すると給料が上がります。
「号級」とは、級を細分化した概念で、職務経験年数による職務の習熟を給与に反映させるものです。
公務員の手当
公務員の手当には、以下のようなものがあります。
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 生活補助給的手当 | 扶養手当/住居手当/通勤手当/単身赴任手当 |
| 地域給的手当 | 地域手当/広域異動手当/特地勤務手当/慣例手当 |
| 職務の特殊性に基づく手当 | 俸給の特別調整額/管理職員特別勤務手当/特殊勤務手当 |
| 時間外勤務等に対して支給する手当 | 超過勤務手当/休日給/夜勤手当/宿日直手当 |
| 賞与等に相当する手当 | 期末手当/勤勉手当 |
| その他 | 本府省業務調整手当/初任給調整手当/専門スタッフ職調整手当/研究員調整手当 |
引用:国家公務員の諸手当の概要
その他手当の中には、初任給調整手当や本府省業務調整手当、研究員調整手当や専門スタッフ職調整手当などが含まれています。
また、暮らすのに必要な手当もかなり手厚いです。
寒冷地手当などの地域特有の手当や、住居手当や単身赴任手当などもあります。
民間企業にも手当はありますが、公務員の方が種類が豊富なのが特徴です。
※参考:内閣官房人事局「国家公務員の諸手当の概要」
公務員にも残業代として時間外勤務手当が支払われる
地方公務員と国家公務員には時間外勤務手当という名前で残業代が支給されています。
残業代の計算方法としては地方・国家共に一緒になっており、定時以外に働いた時間について毎月の自分の給与を基に計算された額が加算されます。
| 区分 | 平均月残業代 |
|---|---|
| 都道府県職員 | 37,286円 |
| 政令指定都市職員 | 41,653円 |
| 市区町村職員 | 32,193円 |
国家公務員のデータはでてきませんでしたが、地方公務員の月の平均残業代はこのようになっているようです。
民間企業と異なりサービス残業の色合いは薄くしっかりと残業代が支給されるため、給料が伸びやすいのは大きな魅力です。
地方公務員になるには
地方公務員になるには地方公務員試験を受けて合格する必要があります。
という流れが一般的です。
一次試験は4月~11月に行われ、二次試験はその一か月後くらいに行われます。
地方公務員試験の内容
地方公務員試験の一次試験は【筆記試験】、二次試験は【面接・小論文】となっています。
自治体によって選抜方法が異なっており、面接を2回行ったり、プレゼンテーションによって合否を出すこともあります。
したがって、行きたい自治体がどのような試験方式を採用しているのかを確認し、それに合わせた対策をすることで内定へつながるでしょう。
地方公務員試験は独学でも合格できる?
地方公務員試験は、難易度が高いというよりは科目数が多いため、勉強時間が必要になります。
地方上級の場合は出題科目が30科目にも及ぶので、「できる気がしない…」と思われる方もいるかもしれませんが、公務員試験は暗記が多いため、力を入れる科目と軽く触れる程度の科目を上手く戦略立てることができれば、独学でも合格することはできます。
事務職や技術職を希望している場合、地方公務員試験は「上級(大卒程度)」「中級(短大卒程度)」「初級(高卒程度)」に分けて行われます。
どれも平常時で3~4時間、直前期は8時間以上勉強するペースで、半年~1年間かかるとされています。
もちろん、これより短い時間(3か月程度)で合格されている方もいますし、逆にこれ以上かかる人もいるので、参考程度に考えてください。
しかし、独学では戦略を立てて勉強をしていても、誤った方法で演習を続けていては合格することはできないので注意が必要です。
予備校や通信講座では、必要十分な勉強量で合格できるようにカリキュラムが設定されているので、無闇に勉強して時間が無駄になってしまうということはありません。
あまり勉強計画を立てるのが得意ではない、という方はプロの力を借りて無理のない勉強計画で合格を目指すのが良いでしょう。
地方公務員を目指すならアガルート

地方公務員になるために予備校や通信講座を使うのであれば、アガルートの公務員講座がおすすめです。
アガルートは大手予備校で、2021年の日本コンシューマーリサーチが実施した調査で支持率と口コミ評価、サポート体制で1位を取っており、多くの人から信頼されている予備校となっています。
アガルートの公務員講座

アガルートの公務員講座の基本情報を表にまとめました。
| 対象 | 市役所・国立大学法人を目指す方 大卒(予定) |
|---|---|
| 学習形式 | オンライン |
| コース | 教養+専門型ワイド対策カリキュラム(大卒) 教養+専門型スタンダード対策カリキュラム(大卒) 【限定オプション】定期カウンセリング 教養+専門型,教養型等(大卒/定員50名) |
| 受講料金 | 299,200円(ワイド対策) 272,800円(スタンダード対策) 110,000円(限定オプション) |
| 学習方法 | 映像授業+テキスト |
| 質問 | Facebookでいつでも質問可能(無料) |
| サポート | 模擬面接あり(回数無制限) 講師による添削 カウンセリング 定期的な動画コンテンツ レッスン無料体験 |
| 公式サイト | 公式サイトはこちら |
アガルートには国家公務員向けの講座と地方公務員向けの講座があり、地方公務員向けの講座では教養試験のみで受験する市役所や国立大学法人を目指す大卒の方が対象となっています。
面接対策へのサポートが特に充実しており、プロの講師から面接試験のノウハウをしっかりと学習でき、模擬面接を何回でも受けることが可能です。
範囲の広い公務員試験ですが、全ての範囲を網羅した万全のカリキュラムで、どなたでも地方公務員を目指せる講座と言えるでしょう。
公式サイトから無料で資料請求やレッスン体験もできるので、気になる方は資料請求や体験をしてみて自分に合うのか確認することをおすすめします。
キャンペーンを使ってお得に受講
予備校や通信講座のデメリットとして、独学と比べて費用がかかるという点があります。
しかし、アガルートには様々な割引キャンペーンがあり、それらを活用することでお得に受講することが可能です。
再受験割引や他校乗り換え割引、また家族割引などがあり、最大で20%も割引できるので、金銭面で不安を感じている方でも安心できるでしょう。
キャンペーンごとに条件や割引金額が異なるので、詳しくは公式サイトから確認することをおすすめします。
地方公務員の年収・給与は比較的安定している
今回は、地方公務員の職種ごとの年収や給料の仕組み、公務員と民間の比較について見てきました。
地方公務員の年収は職種や学歴によってそれぞれ異なりますが、40歳前後の収入は平均660万円~690万円程度もらえるものとなっています。
また地方公務員の平均の生涯年収は約2億円と言われており、一般企業と比較しても平均もしくはやや高い方にあたると考えられます。
加えて公務員は倒産のリスクがないので、民間企業と比べると年y集や給与は安定しているといったメリットがあります。
しかし地方公務員になるためには地方公務員試験に合格しなければなりません。
地方公務員試験は独学でも合格可能ですが、アガルートなどの予備校や通信講座を使うと効率よく学習することができ、合格する確率も上がるのでおすすめです。
地方公務員に就職・転職したいと考えている人は、この記事を参考にしてみてください。