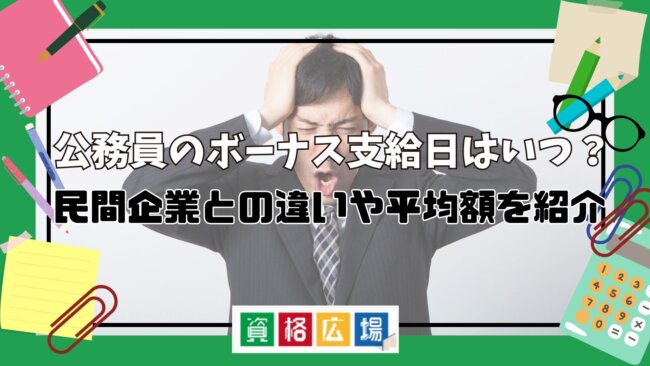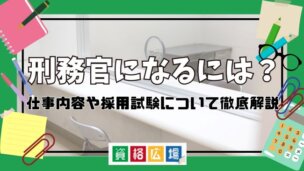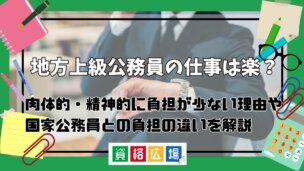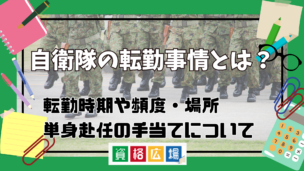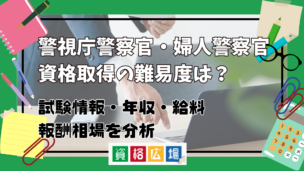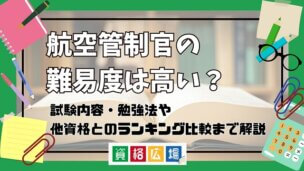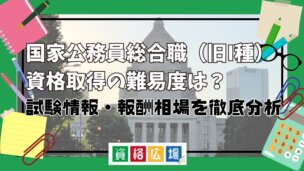公務員は、景気に左右されにくく民間企業のように不景気を理由としたリストラになることもないため、安定した仕事を求める方にとって憧れの職業の一つです。
また、福利厚生が充実しており、勤続年数が増えるごとに収入も増えていく傾向にあるため、公務員を目指している方は数多く存在します。
安定した収入を求める方にとって大切なのがボーナスの存在です。
公務員であっても民間企業と同じく、年2回のボーナスが貰えますが、実際にどの程度の金額が支給されるのか、支給日はいつなのか気になる方も多いはずです。
この記事では、公務員のボーナス支給日はいつなのか、どのようにしてボーナスの支給額が決定されるのかなどを詳しく解説します。
公務員のボーナス支給日やボーナスがいくら支給されるのか知ることで、これから公務員を目指す方のモチベーションアップにつながれば幸いです。
公務員の年収・給与は平均いくらぐらい?職種・年齢別の給与から年収推移・手当やボーナスまで紹介
公務員になるには公務員試験が必須!
公務員試験は倍率が高く、独学で合格を目指すのは至難の業です。
そこでおすすめなのが通信講座アガルートアカデミーの公務員試験対策講座!
地方公務員から国家公務員、一般職から総合職まで全ての試験対策講座を行っており、映像授業と独自のテキストを用いて1年での最短合格を目指せる指導を行っています。
合格実績も非常に高く、隙間時間での勉強で合格を目指せることから、学生さんは勿論、社会人の方にも高い人気を誇っています。
アガルートの公務員試験講座について知りたい方は以下の記事もご参考にしてください。
⇒アガルート公務員試験講座の特徴や評判、料金を詳しく解説!
そもそもボーナス(賞与)の定義とは?
ボーナス(賞与)とは、毎月支給される給与とは別に、勤務先が指定した特定の時期に支払われる特別な給与のことです。
一般的には夏と冬の年2回支給され、業績や個人の成果などによって支給されます。
公務員も、夏と冬に、それぞれの勤続年数や予算などによって算出されたボーナスが支給されます。
公務員のボーナスは「期末・勤勉手当」と呼ばれており、民間のボーナス同様に勤務する方のモチベーションアップにつながっているのです。
公務員のボーナス支給日
国家公務員のボーナス支給日は法律で定められていて、夏は6月30日、冬は12月10日に支給されています。
地方公務員は自由に条例で決められますが、たいていは国家公務員に合わせた日か近い日が支給日となることが多くあります。
法律により6月1日・12月1日(基準日)に在職している職員、基準日より1ヵ月以内に退職・又は失職・死亡した職員に対しても支給すると定められています。
なお公務員のボーナス支給日が休日になる場合は前日か前々日が支給日となります。
もし夏の支給日にあたる6月30日が日曜日であれば6月28日の金曜に支払われますし、30日が土曜日なら29日の金曜といった形です。
前倒しで支払われる理由として、条例や規則で前日支払いの取り決めがあり、福利厚生の一環だともされています。
毎月の給与支給日も休日にあたる場合は前倒しで支給されます。
民間企業のボーナス支給日との違い
民間企業の場合、ボーナスの支給日についての決まりがなく、基本的に企業が自由に設定できるようになっています。
現在ほとんどの企業が毎月の給与とは別日をボーナス支給日としており、夏季が6月下旬~7月下旬、冬季が12月中旬に支給されるケースが多い傾向にあります。
またボーナスは大きくわけて、「基本給連動型賞与」「業績連動型賞与」「決算賞与」の3種類があり、「業績連動型賞与」は支給のタイミングが決まっていないものの、「基本給連動型賞与」が夏と冬の年2回支給されるようになっています。
さらに「決算賞与」は決算月の前後で支給されます。
たとえば3月決算の企業では、夏季だと前年の10~3月、または11~4月、冬季のボーナスの査定期間を4~9月、または5~10月をボーナスの査定機関として設定していることが多いです。
公務員のボーナスの計算方法
民間企業のボーナスは大抵が基本給×1~2.5ヵ月分のように、各企業によりますが基本給×●ヵ月分といった計算方法になりますが、公務員は少し計算方法が違います。
国家公務員の支給月数は国の機関「人事院」がその年の支給月数を定める人事院勧告(毎年8月)を行う事で決めており、その後行われる人事委員会勧告で地方公務員の額が決まります。
月の給料には基本給に加算されるものとして、通勤手当や住宅手当などがあり、総じて月の基本の給料として計算方法に当てはめていきます。
公務員のボーナスは計算方法「(基本の給料+地域手当+扶養手当)×支給月数」で支給総額が決まります。
地域手当と扶養手当とは?
公務員の月給は、基本給と地域手当、扶養手当を足した総額となります。
扶養手当は民間企業にもありますが、地域手当はありません。
扶養手当とは妻子を養うために支給される手当として、東京都の場合で配偶者に6,000円、子には1人目9,000円(2人目からは1人に付き4,000円加算)貰えます。
地域手当は地方と比べて物価の高い大都市との格差が出ないよう調整するために支給される手当で、地域によりますが0%~20%が設定され、(基本給+扶養手当)×地域手当率で出た金額を加算して支給されます。
支給月数の決め方は?
人事院が毎年8月に決めているのですが、その基準は50人以上の民間企業を対象として、月給とボーナスの調査を行い、その調査結果を基準として計算方法に用いるのです。
ですから公務員は従業員50人以上の企業の平均に近い月給・ボーナスを受け取るということになります。
中小企業(常用雇用者10人以下)の多い日本の中で、50人以上の企業となるとなかなかの大企業ともいえる為、公務員のボーナスは高いイメージになるのです。
国家公務員と地方公務員の差は?
大抵は国家公務員とあまり差はありませんが、人口規模や財政状況が違う自治体も数多くあるので、差がある都道府県・市町村もあります。
昨年(2023年)のボーナス支給月数は4.45月分でしたが、これを夏と冬の2回に分けて2.2月分・2.25月分として計算します。
人口規模が多かったり財政状況が良い都道府県・市町村は0.2~0.1月分上乗せされていたり、逆に少ない都道府県・市町村は0.3~0.35月分差し引かれています。
公務員の新卒者のボーナスはいくら?
新卒者はいくら公務員といえど、入職・入庁したばかりの新入職員ですから、最初から大きな額のボーナスが貰える訳ではありません。
一般企業では消えようとしている「年功序列」の風潮が公務員の給料やボーナスの支給には残っているからということもありますが、仕事をした月・年数が少ない為です。
公務員としての階級や勤続年数が基本給になり、そこに地域手当と扶養手当を足したものが毎月のお給料となるため、新卒者の初めてのボーナスは少なくなるのが一般的です。
民間企業でも新卒者の初めてのボーナスは同じように低いですし、一般的だと言えるでしょう。
新卒者の夏のボーナス
公務員のボーナスは、先述した通りの月の給料に、国から指定されている支給月数を掛ける計算方法で算出されます。
ですが新卒者は4月に入職・入庁し、夏のボーナスが支給されるのが6月末なので、2ヵ月支給で計算されます。
都道府県や自治体により変わりますが、新卒国家公務員で約20~25万円、新卒地方公務員で約15~20万円程度とされています。
新卒者の冬のボーナス
新卒者の冬のボーナスは、国に指定されている平均支給月数の約4ヵ月勤務を越えて勤務しているのであれば満額支給されます。
夏と同じく月のお給料×支給月数の計算方法で国家公務員で約40~50万円、地方公務員で35~40万円程度とされています。
ボーナスは夏も冬も6ヶ月間の勤務日数によって決まりますので覚えておきましょう。
民間企業の新卒者ボーナスとの違い
民間企業で働く新卒者のボーナスは、夏の場合だと満額のボーナスを支給されることはほぼありません。
なぜなら、会社によっては4月の入社から数か月程度しかたっていないことから、試用期間としてみなしているケースがあるためです。
したがって新卒者の夏のボーナスはおおよそ7~10万円程度、場合によっては気持ち程度の金額になる可能性もあるとされています。
また冬の新卒ボーナスの平均は夏と違い通常通り、もしくは通常に近い金額が支給されることが多いです。
もちろん業種によってもバラつきがありますが、厚生労働省によると令和4年度の冬のボーナス平均は基本給の1,04ヶ月分といったデータがあります。
したがって、民間企業の新卒者の冬のボーナスはおおよそ1ヶ月程度だといった認識をしておくといいでしょう。
参照:厚生労働省
公務員でボーナスを多く受け取りたいなら5月後半か11月後半に退職がおすすめ
もし公務員として退職するなら、退職のタイミングは5月後半もしくは11月後半がおすすめです。
なぜならボーナスは先にも述べたように基準日に在籍している場合に支給され、基準の1ヶ月前までに退職したとしても支給されるからです。
したがって5月後半に辞めたとしても夏のボーナスが、11月後半でも冬のボーナスが受け取れるということですね。
公務員になるには
公務員は通常の月給は勿論、ボーナスも非常に安定している職業です。
そんな公務員になるにはそもそもどうしたらいいのでしょうか?
公務員になるために必要な『公務員試験』の話を中心にご紹介していきます。
公務員試験とは
公務員試験とは、公務員になるために必要な試験です。
まずこの試験に受からなければ公務員になる事はできません。
- 一次試験(筆記)
- 二次試験(面接)
試験の内容は職種によって異なりますが、主に『教養』『専門』『教養記述』の3つが出題されます。
合格難易度は職種によって異なるものの、国家公務員(総合職)は非常に難易度が高いことでも知られています。
逆に、国家一般職や、消防官・警察官などは比較的難易度が低く公務員試験の中では合格できる可能性が高くなっています。
公務員試験に合格する方法
公務員になるためになくてはならない『公務員試験』。
この公務員試験を合格するためには勿論勉強しなくてはなりません。
独学で勉強するための参考書なども販売されていますが、一番のおすすめは通信講座を利用して学ぶ事です。
過去の公務員試験の過去問や出題傾向から、勉強の進捗ペースの管理、分からない問題についての質問・相談対応してくれるおすすめの通信講座がアガルートアカデミーです。
最短1年での合格を目指せるカリキュラムが特徴的で、合格実績も多く人気が高い通信講座として知られています。
国家公務員から地方公務員まで、また最難関の国家公務員総合職講座まで展開しておりそれぞれ合格に必要なための知識が用意されています。
動画視聴を行い、勉強を進めていくだけでなく実際に講師がリアルタイムで公務員試験に関する最新情報や勉強方法を教えてくれる『公務員試験ホームルーム』も人気の高いコンテンツです。
公務員を目指している方は是非、アガルートアカデミーの公務員試験講座要チェックです!
公務員のボーナス支給日は法律によって定められている
今回は公務員のボーナス事情について解説してきました。
国家公務員は法律で決められた支給日があり、地方公務員もそれに準ずる日か近い日に支給日が設定される事が分かりました。
支給される月に在職していなくても貰える基準があると言う事も分かったので、もし転職を考えるのであれば基準日までは在職しておく方がお得ですね。
新卒者のボーナスが貰える月数も夏は2ヵ月と短いですが、冬は平均月数をクリアしていることから満額貰えるので楽しみになります。
今回の記事を読んで公務員に興味を持った方はぜひ目指してみてください。