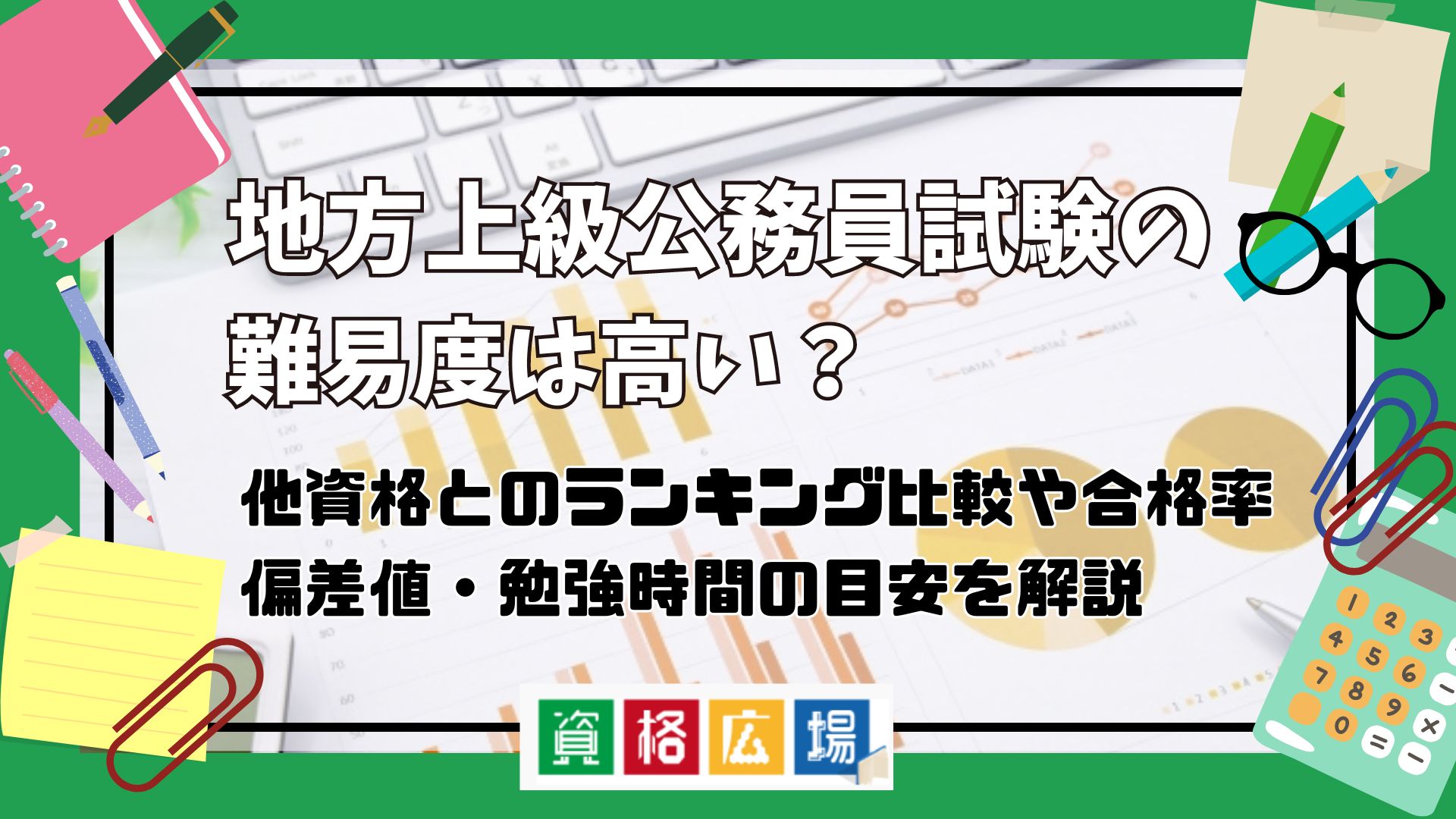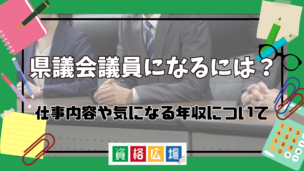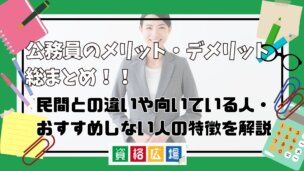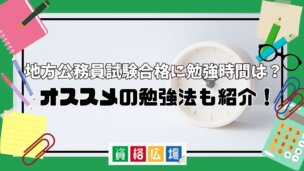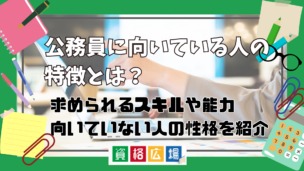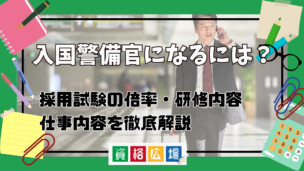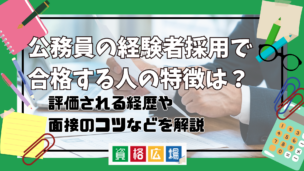公務員には国家公務員と地方公務員がありますが、地方公務員の中でも地方上級公務員は幹部候補であり、地方自治体で政治や社会インフラに関わる重要な職業です。
地方上級公務員の試験は、地方公務員の中でも難易度が高いことで知られており、相当な勉強と覚悟をもって試験に臨まなければなりません。
今回は、地方上級公務員とはどのような仕事なのか、具体的な仕事内容から試験対策まで幅広く解説します。
地方上級公務員試験を受けようか迷っている人は、是非参考にしてみてください。
- この記事でわかること
- 地方上級公務員とは
- 地方上級公務員の職種とそれぞれの仕事内容
- 地方上級公務員試験の難易度
- 地方上級公務員試験に合格するための勉強法
地方公務員の仕事は楽すぎ?肉体的・精神的にも簡単と言われる理由と実態を解説
【2024年】社会人の公務員試験対策におすすめ予備校・通信講座ランキング!人気15社の費用・評判を比較
公務員講座ならアガルート!
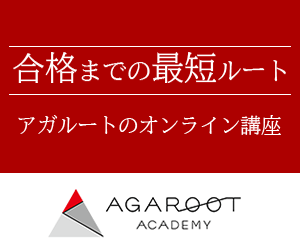
公務員試験合格を目指すならアガルートアカデミーがおすすめです!
アガルートでは、「地方上級」「国会一般職」「専門職」「裁判官」など、さまざまな公務員試験に対応したカリキュラムが用意されています。
通勤や家事の合間など隙間時間も活用することができるので、効率的に学習を進めることができる講座です。
地方上級公務員試験の難易度
地方上級公務員試験の難易度を確認しましょう。
地域によって差はあるものの、倍率も高く簡単に突破できる関門ではありません。
地方上級公務員試験は6~7倍程度
地方上級公務員試験は自治体によっても異なりますが、地方公務員試験の中では最難関とされており、おおよそ6~7倍程度となっています。
したがって、地方上級公務員試験の難易度はかなり高いと判断できるでしょう。
■地方上級公務員試験の地域ごとの倍率
| 地域 | 倍率 |
| 東京都 | 事務職:5.6倍 技術職:1.5~2.1倍 |
| 大阪府 | 行政職(事務):7.9倍 技術職:2.4倍 |
| 愛知県 | 行政職Ⅰ:5.9倍 専門職:1.3~10.4倍 |
| 福岡県 | 行政職:10.5倍 専門職:1.2~3.0倍 |
参照:試験選考実施状況|東京都
上記のように、基本的には専門職よりも事務職(行政職)の方が倍率は高くなる傾向にあります。
試験の難易度はもとより、応募者数に対する採用数が少ないことから、少しでも高得点が取れるよう、試験対策は念入りに行うことが大切です。
地方公務員試験の「初級」「中級」と比べて高い難易度
地方公務員試験の「初級」「中級」と比べて難易度が高いことは、地方上級公務員試験の特徴です。
高卒区分より低く、短大卒区分よりは高い倍率と難易度といえるでしょう。
高卒区分の採用予定者数がほかの区分より少ないことも、地方上級公務員のポイントです。
希望する自治体の倍率や試験内容を確認してください。
地方上級公務員試験の合格に必要な勉強時間は1,000時間程度
地方上級公務員試験の合格に必要な勉強時間は1,000時間程度です。
採用されるには大卒程度の学力が求められるでしょう。
1日5時間の勉強でも、1週間で25時間程度しか勉強できません。
少なく見積もっても1年から2年程度の勉強期間と考えてください。
ただし地方自治体によっては教養試験だけで受験が可能な場合があります。
地方上級公務員試験の概要
地方上級公務員になるには、地方上級公務員試験を受けて合格しなければなりません。
そこでここでは、地方上級公務員試験について詳しくご紹介します。
地方上級公務員試験の受験資格
地方上級公務員試験では、自治体により22〜30歳前後の年齢制限が一般的です。
なお一部では35歳まで認められているところもあり、各自治体の募集要項をチェックすることが大切です。
実際、ほとんどの試験には「大学卒業または卒業見込みの者」や「学歴は不問だが大学卒業程度の学力を有する者」が受験資格とされています。
また保育士や看護師といった一部の職種では、上記の年齢に加えて資格が必要な場合もあります。
地方上級公務員試験の試験日程
地方上級公務員試験の試験日程は自治体によっても異なりますが、5~6月中に1次試験日を設定しているところが多いです。
通年、試験が開催される年度の2~5月に試験内容が各自治体によって公表され、3~4月に申込受付が始まります。
また近年の傾向としてはインターネット受付しているところが主流となっており、スケジュールがかぶらなければ併願受験もできます。
地方公務員試験とは?試験内容・合格率・試験対策や独学受検のポイントを徹底解説!
地方上級公務員試験の試験内容
| 一次試験 | 教養試験(択一試験)・専門試験(択一試験)・論文試験 |
| 二次試験 | 個別面接・集団面接・グループワーク |
地方上級公務員試験では、一次試験で教養試験・専門試験・論文試験が実施され、二次試験で個別・集団面接、グループワークなどが行われます。
ただし、試験内容は自治体によって異なる部分があるので注意が必要です。中には、教養試験もしくは専門試験のいずれかのみを実施している自治体もあるので、受験する地域に合わせた試験対策が必要になります。
試験科目では、数的処理や文章理解を見極められるほか、専門試験で憲法や民法、行政法、経済学などの幅広い分野に関する知識が問われるのも特徴です。
出題範囲が広いため、計画的に勉強を進めなければ容易に突破できる試験ではないと考えておきましょう。
ここでは、それぞれの試験内容や範囲についてご紹介します。
教養試験
地方上級公務員試験の教養試験は「一般知能」と「一般知識」に分かれ、数的処理が重要視されています。
おもに教養試験の出題内容は以下のものが挙げられます。
・数的処理
・文章理解
・人文科学
・自然科学
・社会科学
・時事問題
特に数的処理は通常の数学と異なり、出題数が多いことから、地方上級公務員試験の学習を始める際には優先的に対策することが推奨されています。
専門試験
専門試験は職種によって試験科目が異なる特徴があります。
たとえば行政系であれば憲法や民放、経済原論といった法律系・経済系・行政系科目、心理・福祉系であればそれに準じた心理学、技術系であれば土木や高額、建築、機械、電気などが挙げられます。
なかでもとくに採用数が多い行政系で重要なのは、法律系の憲法や民法、行政法、そして経済系の経済原論です。
上記は専門試験があるほとんどの地方公務員試験で出題されます。
専門試験に関しては、それぞれの科目の問題数や配点によって、重点的に取り組むポイントを絞った対策がおすすめです。
論文・面接
地方上級公務員試験では、教養試験や専門試験と同様に論文や面接も重要です。
論文では時間内に適切な内容を執筆するスキルを磨き、添削を受けて向上させることが重要です。
また第三者にチェックしてもらうのもひとつですし、過去問を公開しているとこ炉もあるので確認しておくといいでしょう。
面接対策では志望動機を深掘りし、模擬面接を通じて実践的な経験を積むと良い。これらのスキルは早めに身につけることが合格への鍵となります。
地方公務員試験とは?試験内容・合格率・試験対策や独学受検のポイントを徹底解説!!
地方上級公務員試験が難しいと言われる理由
地方上級公務員試験が難しいと言われる理由は以下があります。
- 教養記述が出題される
- 面接対策にコツがいる
- 学習範囲が広い
それぞれのポイントを確認しましょう。
理由①教養記述が出題される
地方上級公務員試験では、教養記述が出題されます。
論文試験や小論文など、各自治体によって違うので注意してください。
1,000字〜2,500文字ほどの文章で解答できるように用意しましょう。
教養記述は、自治体ならではの課題が出題されます。
受験するエリアの現状や問題点などを、事前に調査することがおすすめです。
配点が高いことも、教養記述で気をつけたいポイントと言えます。
理由②面接対策にコツがいる
地方上級公務員の面接試験には以下のようなバリエーションがあります。
- 個人面接
- 集団面接
- プレゼンテーション
- グループワーク
- 集団討論
面接では人物像が重視されるので、言葉遣いや対応に気をつけてください。
内定を獲得するためには、面接対策をしっかり行いましょう。
地方上級公務員の面接試験は2回~3回行う自治体が多いです。
理由③学習範囲が広い
地方上級公務員の試験は、学習範囲が広いです。
学習範囲の広さが試験の難易度に影響しています。
問題数や試験科目をあらかじめ調べておきましょう。
本格的な勉強を始める前に、スケジュールを決めてください。
慎重になって、早めに対策を進めていくことがおすすめです。
地方上級公務員試験に合格するための勉強法
地方上級公務員は、国家公務員の一般職と同等の難易度があるため、効率良く勉強しなければ簡単に合格することはできない職業です。
そのため、以下のポイントを押さえて勉強を進めましょう。
- 勉強をしっかりと確保する
- 試験科目や試験形態を踏まえて計画的に進める
- 公務員試験対策講座を受講する
それぞれの項目で、具体的に意識すべき点について解説します。
勉強時間をしっかりと確保する
地方上級公務員の試験に合格するには、勉強時間をしっかりと確保する必要があります。
出題科目が多く、勉強しなければならない範囲が広いため、勉強時間が確保できていなければすべての出題範囲を網羅することはできません。
一般的に、地方上級公務員試験にかける勉強時間は1,000時間以上が目安と言われています。地方初級~中級であっても800時間程度は必要と言われているため、より難易度が高い上級になるとさらに時間を要するでしょう。
1日に何時間勉強時間を確保できるかによって、受験のタイミングを見定めることが大切です。
例えば、1日4時間なら約1年前から、1日8時間取れるなら半年前から勉強をスタートします。
また、平日は仕事で勉強時間をなかなか確保できないという場合には、土日祝日の勉強時間を増やすなどして調整すると良いでしょう。
地方公務員試験合格の勉強時間は?オススメの勉強法も紹介!
試験科目や試験形態を踏まえて計画的に進める
地方上級公務員試験は、受験する地域によって試験科目や試験形態に違いがあります。
受験地域の試験科目や試験形態を踏まえて、受験までの勉強を計画的に進めることが大切です。
例えば、二次試験の個別面接とグループワークでは、対策方法が全く異なります。まずは、受験地域の試験内容を確認した上で、勉強を進めましょう。
また、地方上級公務員試験では、教養記述問題の重要度が高い傾向にあります。
教養記述問題では、受験地域が抱える課題や問題をよく理解し、解決方法を回答できるようにしておくのも重要なポイントです。
公務員試験対策講座を受講する
地方上級公務員試験の受験勉強を効率良く進めるには、公務員試験対策講座を受講するのもおすすめです。
独学で参考書などを購入して学ぶ方法もありますが、公務員試験対策講座であれば勉強する上で重要なポイントをしっかりと押さえられる教材が揃っています。
また、独学で対策することが難しい記述対策講座が充実していたり、面接対策ができたりするのも特徴です。
独学で試験対策を進めるよりも短期間かつ効率良く勉強できるため、仕事との両立で時間がない方にも適しています。
地方上級公務員試験の難易度を他試験とランキングで比較
地方上級公務員試験の難易度を他試験と比べてみましょう。
| 区分 | 倍率 |
|---|---|
| 国家公務員の専門職・地方上級(都道府県)など | 所属機関によって差がある |
| 東京都庁・大都市圏県庁・政令都市・東京特別区職員(大卒)など | 3.6倍 |
| 国家公務員一般職(大卒)・国立国会図書館一般職・裁判所事務官一般職など | 3.4倍 |
| 市役所職員・消防官・警察官など | 所属機関によって差がある |
地方上級公務員の採用倍率は、所属機関によって差があります。
希望する自治体のデータをチェックしておきましょう。
同様に、試験難易度も所属機関によって開きがあることに注意してください。
地方上級公務員とは
地方上級公務員になるには、公務員を目指す人が通る登竜門にあたる「公務員試験」を突破する必要があります。
しかし、一口に公務員試験といっても初級・中級・上級の3つに分かれており、それぞれ難易度が異なる点が特徴です。
地方上級公務員は、地方公務員の中で大卒に相当する難易度区分のことを指します。
■地方公務員とは
都道府県や市区町村といった地方自治体に勤務し、地方自治体が住民のために行っている事業に関する行政施策の企画・立案、予算の編成から実際の業務にかかわる事務処理を担当する。
地方上級公務員は、地方公務員1類、地方公務員1種などと呼ばれることがあるのも特徴です。基本的に試験の難易度区分ごとの通称であり、採用後に地方上級公務員と呼ばれることはありません。
初級・中級との違い
「初級」「中級」「上級」の3つに分かれている地方公務員試験の中で、上級と初級・中級との違いは難易度にあります。
高卒程度の「初級」、短大や専門学校卒程度と言われている「中級」、大卒程度とされる「上級」と、難易度ごとに3つの試験区分が用意されています。
| 区分 | 特徴 |
| 地方初級公務員 | ・「Ⅲ類」「3種」「C」に該当 ・高卒程度の難易度 |
| 地方中級公務員 | ・「Ⅱ類」「2種」「B」に該当 ・短大・専門学校卒程度の難易度 |
| 地方上級公務員 | ・「Ⅰ類」「1種」「A」に該当 ・大卒程度の難易度 |
このいずれかに合格すると、各都道府県や政令指定都市の職員になることができます。
ただし、地方上級公務員の試験が大卒程度の難易度に相当するとは言え、大卒でなければ受験資格がないということではありません。
中卒や高卒であっても、試験を受けること自体は22歳~30歳前後の人であれば誰でも可能です。
一部の専門職では学歴に制限が設けられている場合もありますが、試験の受験そのものに関しては学歴に関係なく受験することができます。
市役所職員・国家公務員との違い
地方公務員という職業がある一方で、国の行政機関などで勤めている職種を国家公務員と言います。
また、地方公務員には市役所職員も含まれていますが、詳細に分類すると異なる点があるので注意しましょう。
| 職種 | 特徴 |
| 地方公務員 | ・都道府県や市区町村全般で働く職員のこと ・地方上級は「政令指定都市」「都道府県庁」の職員を指す |
| 市役所職員 | ・市役所職員のこと ・政令指定都市以外の市役所職員 |
| 国家公務員 | ・国家機関(中央省庁など)で働く職員のこと ・転勤の辞令が出る場合がある |
地方上級公務員と市役所職員・国家公務員は、上記のように勤め先に違いがあります。試験の難易度にも差がありますが、どの職種もすべて公務員です。
たとえば市役所職員は、市役所での業務全般を担う仕事です。
基本的に、政令指定都市の職員は地方上級公務員が担っているため、市役所職員は政令指定都市以外の市役所で働く職員のことを指します。
市役所職員になるには、市役所試験を受ける必要があるため、地方上級公務員とは異なり、勤め先も異なります。
また国家公務員とは、文字通り国の中枢に関する業務が主な仕事です。
彼らは中央省庁と呼ばれる国の行政機関(内閣府や防衛省、警察庁など)や国会、外局(金融庁や気象庁、海上保安庁など)、裁判所などに勤めています。
具体的には司法府における裁判所事務官、立法府(国会)の場合では事務局職員や法制局職員、また国税捜査官や労働基準監督官といった職種がメインです。
日本だけに留まらず、国際社会に関する仕事も多々あるため、責任の重さが異なるほか、試験の難易度も高くなります。
国家公務員と地方公務員の違いとは?年収・試験難易度・仕事内容の違いをわかりやすく解説
地方上級公務員試験の独学合格が難しい理由
地方上級公務員試験は、独学での合格が難しいと考えましょう。
一人でペースを守りながら勉強できる人でも、つまづいてしまうことが多くあります。
ここからは地方上級公務員試験の独学合格がなぜ難しいのか、詳しくまとめました。
独学が難しい理由①試験科目の頻出分野が見分けにくい
各科目の頻出分野が見分けられないと、勉強に時間がかかってしまいます。
頻出分野を知ることは試験合格に近づくでしょう。
しかし、頻出分野を知るには過去問を揃えるところから始めなくてはなりません。
自分一人では思うように勉強が進められないことも、公務員試験の注意点です。
独学が難しい理由②学習教材の選び方が難しい
地方上級公務員試験の学習教材の選び方にはコツがあります。
公務員試験対策ができる参考書や問題集をしなくてはいけません。
しかし、自分だけではどのような学習教材がベストかわからない人もいるでしょう。
紙のテキストは相性があるので、実際に開いてみることがおすすめです。
学習教材選びや独学に限界を感じたら、早い段階で講義の受講などを考えてください。
社会人向け講座のほか、高校・大学に在学中から学べる講座もあるため、将来を見据えた試験勉強にもおすすめです。
独学が難しい理由③モチベーションの維持が難しい
地方上級公務員試験対策はモチベーションも維持も重要です。
社会人の場合は、仕事をしながらの勉強となります。
仕事と勉強、生活のバランスに気を付けることも大切です。
思うように勉強が進まなくても、毎日継続して学習してください。
平日の勉強時間が足りない場合は、週末にカバーするといった努力をしましょう。
講義の受講や通信講座などと比べると、独学ではモチベーションの維持が難しい場合もあります。
地方上級公務員の仕事内容
地方上級公務員は、地域住民の生活に密着し、課題解決やよりよい暮らしの実現に尽力する仕事がメインです。
ただし、都道府県庁に採用になるか政令指定都市の市役所・区役所に採用になるかの違いによって、仕事内容には異なる点があります。
それぞれ、どのような仕事内容になるか以下で詳しく見ていきましょう。
都道府県庁での仕事内容
都道府県庁の職員として採用された場合を見てみましょう。
都道府県庁で働く場合、一般的にはあまり携わることのできない大規模公共事業などを担当することが多い傾向にあります。市役所と比べて動かす予算規模が大きいためです。
例えば以下のような事柄が挙げられます。
・学校や図書館、公民館等の設置・管理、教育や文化にまつわる事業の運営
・病院や療養所、児童福祉施設といった福祉施設の管理
・大気汚染、水質汚濁、騒音といった公害の防止
・区画整理や農地開発といったまちづくりの運営
扱う仕事のスケールが大きいので、地域全体を管理しているという責任感が必要になる仕事です。
区役所・市役所・政令指定都市での仕事内容
政令指定都市の配属となった場合、市民・区民の要望や相談に対応したり、役所サービスを提供したりと、都道府県庁で働くケースと比べて住民と近い距離での仕事がメインです。
業務のすべてが市民や区民の身近な生活を守ることに直結するため、仕事の成果を実感しやすいといえます。
加えて、転勤があったとしても市内か区内での異動になるため、転居を伴う転勤が少ないのも魅力の1つです。
区役所・市役所での仕事は、具体的には以下のようなものがあります。
・道路や公園といった施設の保護・管理
・ゴミの処理やリサイクル
・救急対応
・高齢者介護、ケースワーカー
都道府県庁での仕事は規模感が大きい一方、区役所や市役所での仕事ではよりきめ細やかな業務が多くなる点が特徴です。
公務員の仕事の種類はいくつある?地方・国家公務員の職種一覧・仕事内容・それぞれの適性
地方上級公務員の平均年収
総務省が令和5年に発表した「令和4年地方公務員給与実態調査」によると、全国の地方公務員のうち、地方上級公務員にあたる「政令指定都市職員」の平均給与月額は約38万円でした。
民間企業の賞与(ボーナス)にあたる期末手当・勤勉手当の平均は、約150万円です。
参照:令和4年地方公務員給与実態調査結果等の概要<平均給与額>|総務省
参照:令和4年地方公務員給与・定員等の調査結果等<期末・勤勉手当の支給状況>|総務省
合算すると、地方上級公務員の平均年収は約600万円であることがわかります。
一般の企業に勤めるよりも高年収だと感じるかもしれませんが、あくまでこの金額は平均です。
地方公務員は勤続年数に比例して給与が高くなるため、若手や転職後間もない職員の場合、上記よりも低くなるでしょう。
地方公務員の年収・給与はいくら?ボーナス・手当を含む給与額と年齢別平均額を紹介
地方上級公務員試験合格を目指すならアガルート

| 商品名 | アガルートアカデミー公務員講座 |
| 対応職種 | 地方上級 特別区Ⅰ類(一般方式) 東京都Ⅰ類B 国家一般 国税専門官 裁判所事務菅 労働基準監督官 |
| 地方上級公務員向けパック料金 | 教養+専門型ワイド対策カリキュラム/フル(大卒) 295,020円(税込) |
アガルートアカデミーのおすすめポイント
- パック型教材だけでなく単科講座での受講も可能
- 模擬面接・質問回数無制限
- 内定すると受講料全額返金
アガルートアカデミーの公務員講座は、模擬面接や記述問題対策も充実しているオンライン講座です。
模擬面接や質問も回数無制限で利用でき、苦手克服に向けた単科講座の受講にも対応しています。
社会人向け講座のほか、高校・大学に在学中から学べる講座もあるため、将来を見据えた試験勉強にもおすすめです。
アガルートの公務員試験講座について知りたい方は以下の記事も参考にしてください。
アガルートの公務員試験講座の評判は?内容や割引特典について解説!
【2024年】社会人の公務員試験対策におすすめ予備校・通信講座ランキング!人気15社の費用・評判を比較
地方上級公務員に向いている人
地域の住民のために重要な仕事を担っている地方上級公務員は、重い責任が伴う仕事です。
そのため、地方上級公務員は以下のような資質がある人に向いています。
- 真面目に働ける
- 社会貢献意欲が高い
- 責任感がある
- 論理的思考ができる
- 優しさをもって人と接することができる
一言で言うならば、地方上級公務員に向いているのは「世のため人のために働ける人」です。
地方上級公務員は、国家公務員と比べて地域の人との距離が近いため、市民や区民たちが何を思い、何を求めているのかを直接聞く機会が多くあります。
生活していくうえでの不満や不便なことを聞いたり、より良く生活していくための要望を聞いたり、ときには無理難題なことを言う人もいるでしょう。
そうした1人1人のために、優しさと忍耐力を持って働ける人こそ、地方上級公務員となるのに相応しい人材です。
地方上級公務員と国家公務員一般職はどちらが難しい?
地方上級公務員と国家公務員一般職のどちらを受験すべきか判断するには、難易度や仕事内容の違いを把握しておくことが大切です。
ここからは、地方上級公務員と国家公務員一般職の試験難易度の違いや、職務上で異なる点について解説します。
試験の難易度は同等程度
地方上級公務員と国家公務員一般職の試験難易度は、同等程度と言われています。
国家公務員には総合職もありますが、総合職はいわゆる「キャリア官僚組」と呼ばれ、公務員試験の中でも最難関クラスです。
そのため、総合職と比べると地方上級公務員の方が難易度は低いと言えます。
難易度だけで判断した場合、地方上級公務員と国家公務員一般職はほぼ同等です。
しかし、仕事内容は大きく異なるため、自分の得意分野やキャリアパスを具体的にイメージして選択することが大切です。
地方上級公務員と国家公務員一般職の違い
地方上級公務員と国家公務員一般職の違いは、仕事内容にあります。
基本的に地方上級公務員は、3~5年単位で部署移動を繰り返しながらあらゆる業務を担うため、いわゆる「ゼネラリスト」のような働き方をするのが特徴です。
一方で、国家公務員は専門知識をフルに活かして働くため、専門分野に特化した「スペシャリスト」として働くことになります。
地方上級公務員や国家公務員一般職は、どちらも地方自治体や国の運営に関わる重要な職業であり、自身の専門性や希望の働き方、キャリアパスを考慮した上で選択することが大切です。
国家公務員と地方公務員の違いとは?どっちがいい?年収・試験難易度・仕事内容の違いをわかりやすく解説
地方上級公務員の仕事内容を理解して合格を目指そう!
地方上級公務員とは、地域住民のために日々活躍する職業の1つです。
「安定している」というイメージが先行しがちな職業ですが、不景気によって財政難となった地方自治体で働く地方上級公務員も数多くいます。
しかし、難しい仕事だからこそ誰にでもできるものではなく、やりがいを実感できるのも確かです。
「自分も社会や誰かの役に立ちたい」という熱い思いを持っている人は、ぜひ地方上級公務員を目指して勉強を始めてみてはいかがでしょうか。