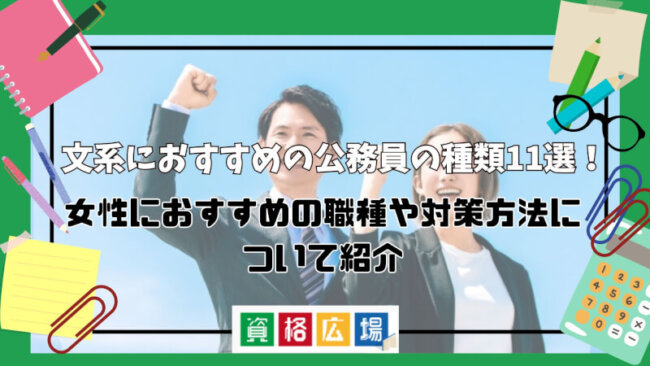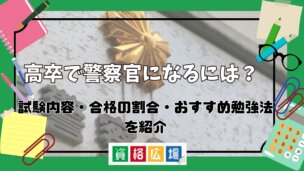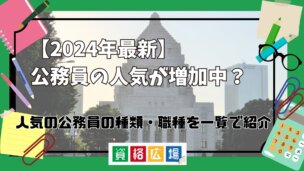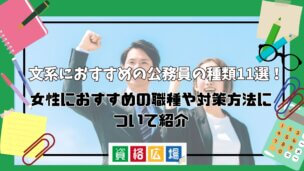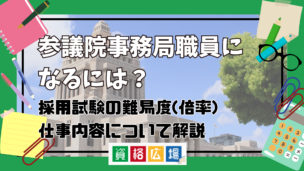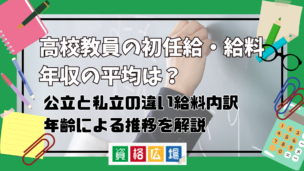文系の方にとって、公務員は将来的にも安定しており人気の就職先の一つです。
物価高騰や不況など様々な不安要素が存在する中でも、公務員の安定性や福利厚生の手厚さ、世間体の良さなどから、とても魅力的です。
文系は理系に比べ就職が困難とされがちですが、文系でも公務員志望の際に有利になる学科はあります。
今回は文系の方が公務員を目指す上でおすすめの学部や、文系で培ったスキルや知識が活かせる職種について解説します。
さらに出産・育児などのライフステージの変化がある女性の方でも、安心して働けるおすすめの職種についてもご紹介しているので、ぜひ参考にしてください。
【2025年】公務員のおすすめ予備校・通信講座ランキング15選を徹底比較!
アガルートアカデミーがおすすめ!
 当サイトで最もおすすめするのはアガルートアカデミーです。
当サイトで最もおすすめするのはアガルートアカデミーです。
徹底して洗練された充実カリキュラムと手厚いサポートが魅力的なんです!
カラーで見やすいテキスト教材と分かりやすい動画講義で、公務員試験勉強を初めてする方でも充分合格が目指せるカリキュラムになっています。
通信講座で選ぶなら
アガルート公式HPはこちら
文系におすすめの公務員の種類・職種11選
ここでは、文系におすすめの国家公務員職についてご紹介します。
国家一般職(大卒行政)
国家一般職は総務省や財務省などの中央省庁に所属しており、事務処理などの定型的な業務を担当する一般職員として採用されるポジションです。
法律、政治、経済などの文系学部出身者が活かせる場面も多く、おすすめです。
配属先も行政制度の管理など、文系職になることが多いのもポイント。
採用試験については一般職は高卒〜大卒程度の試験レベルで実施されていますが、公務員採用試験の中ではやや難易度が高い試験といわれています。
地方上級(行政職)
地方上級は、都道府県や政令指定都市における採用試験の区分の一つで、試験では大学卒業程度の学力が求められます。
合格後は受験地の地方公務員として地域振興や行政を担当する部署に配属される可能性が高いです。
試験には行政系の専門科目が含まれているため、法学や行政学を専攻していた場合は有利になる面があります。
地方公務員は特定の都道府県や市区町村に限定されますが、3~4年ごとに異動を繰り返し、採用された自治体のゼネラリストとして活躍することが期待されています。
特に地方上級に合格して採用されると、将来の幹部候補生と見なされ、責任あるポストに配属され、昇進のスピードや昇進の上限、給与などの待遇面で優遇される可能性も高いです。
特別区Ⅰ類(東京23区)
特別区Ⅰ類は東京23区内で行政職員として働く試験区分の一つであり、大学卒業程度の学力が求められます。
具体的な仕事内容としては企画や政策立案などの文系業務が多く含まれており、文系出身者で法学、行政学、経済学を学んできた方はその能力を発揮できるでしょう。
難易度は公務員試験全体と比較して一般的とされており、採用地が東京であるからといって特に難易度が高いわけではありません。
ただし、採用年の4月1日時点で22~31歳の方、または21歳以下の大学卒業見込みの方が対象となり、年齢制限があるため注意が必要です。
裁判所事務官(一般職)
裁判所事務官は裁判所内で事務や書記作業を行う仕事です。
裁判部門と司法行政部門に分かれ、裁判部門に配属されると、裁判所書記官の指導の下で裁判関連文書の送付などの裁判事務を担当します。
一方、司法行政部門に配属される場合、事務局(総務課、人事課、会計課など)で裁判が円滑に進行するように、人材や設備の面で裁判部門を支える業務をするといった違いがあります。
裁判所事務官は法律関連の業務が主となるため、文系の中でも法学部の学生に人気があり、女性合格者も多数輩出しています。
転勤はありますが、比較的異動希望が通りやすく、県をまたぐ異動が少ないため、働きやすいメリットがあります。
他の国家公務員と同様に、院卒者区分を除けば学歴制限はないため、高卒でも総合職を受験することができます。
学歴や学科にとらわれずチャレンジしやすいですが、採用難易度は公務員試験の中でも高めであるため、しっかりとした試験対策が必要です。
国税専門官
国税専門官とは国税局や税務署などの税金に関連する省庁で国税業務に携わる職員を指します。
具体的な仕事内容としては納税申告が不十分な人や脱税の疑いがある企業に対して立ち入り検査を行ったりします。
国税専門官の仕事には税金と法律に関する知識が求められるため、経済学部や法学部で学んだ方におすすめです。
また例年の合格率は30〜40%程度であり、公務員試験の中では比較的挑戦しやすい点もおすすめできるポイントです。
さらに、23年間勤務することで税理士の資格を取得できるメリットもあります。
財務専門官
財務専門官は財務省の出向機関である財務局において、財政や金融などの専門家として業務に従事する国家公務員です。
財務局は各省庁の地方支部分部局と連携し、財務省の重要施策を地域に広報したり、地域の意見や要望を財務省に伝えることで国と地域をつなぐハブ的な役割を果たしています。
採用試験の専門科目ではミクロ経済学やマクロ経済学など、経済分野に関する専門的な知識が問われるため経済学部出身者には特におすすめです。
財務専門官には転勤がありますが、その範囲は基本的に採用局の管内と財務省や金融庁のある東京に限られます。
財務専門官の合格率は約40%であり、公務員試験としては一般的な難易度といえるでしょう。
国家総合職(法律区分)
国家総合職の法律区分は、いわゆる「キャリア官僚」になるための一つのルートです。
高度な法知識が求められるため、他の区分と比較して難易度は高めですが、文系キャリアの頂点とも言われており人気の職種となっています。
ただし東大などの難関大学出身者が受験する試験であるため、かなりのレベルの高いので注意が必要です。
国家総合職の主な業務は政策の企画及び立案、調査、研究に関わる事務です。
国家総合職の法律区分試験は、一次試験「基礎能力試験」「専門試験(択一式)」から構成され、二次試験は「専門試験(記述式)」「政策論文試験」「人物試験」から成り立っています。
また、試験とは別にTOEICやTOEFLなどの外部英語試験の結果に応じて、別途15点〜25点の加点を受けることがあり、最終合格の判定に用いられることもあるため、語学力に自信がある方には狙い目だといえるでしょう。
国家総合職は各省庁の幹部候補として登用され、通常2年ごとに部署を異動し、省庁のジェネラリストとしてのキャリアを歩むのが一般的です。
労働基準監督官
労働基準監督官は厚生労働省に所属する専門職であり、労働基準に関連する法令に基づいて、さまざまな業種の事業場に立ち入り労働条件の確保と向上、働く人々の安全や健康を促す仕事です。
さらに不幸にも労働災害に遭った方々に対する労災補償の業務を行っています。
これまであまり注目されていませんでしたが、労働問題が取り上げられ、ブラック企業の摘発が相次いでいる現在、需要が高まりつつあります。
また、今後「働き方改革」が進展するにつれてますます労働基準監督官は期待が高まると予想されます。
労働基準監督官の採用では法学部出身者が多く文系におすすめです。
理由としては試験で労働基準法や労働安全衛生法などの法律に関する問題が出題されること、さらに業務上で法律の知識が必要とされるためです。
また、出身大学は年度によって異なるものの、早稲田、慶応、中央、同志社、阪大、東北、九州大学などの難関大学出身者が多い傾向があります。
国立国会図書館職員
国立国会図書館職員の仕事は出版された書籍の収集・保存、蔵書の整理、政策立案のための資料収集などが挙げられます。
一般的な図書館で働くには司書の資格が必要ですが、国立国会職員の場合、一般の図書館とは異なり、司書の資格がなくても就職することができます。
基本的には国立国会図書館が位置する永田町からの転勤はなく、転勤を望まない方にとっては理想的だといえるでしょう。
本に携われる仕事ですので、昔から本が好きな方や文系出身者にはおすすめです。
市役所職員
市役所職員は地方公務員の一形態であり、全国各地に設置されている市役所で働いています。
公務員は所属する機関によって「国家公務員」と「地方公務員」に分かれ、地方公務員はさらに「都道府県職員」と「市区町村職員」に分類されます。
主な業務内容には住民登録や戸籍管理の事務、小中学校の運営、保育所への入所、消防や水道の整備、ごみの収集や処理などが含まれ、幅広い業務を扱う特徴があります。
また、試験は3つの種類に分かれ、1種は大学卒業程度、2種は短大卒業程度、3種は高校卒業程度の学力が求められます。
しかし、同等の学力があれば必ずしも「大卒」や「短大卒」といった学歴が必要というわけではありません。
自治体によっては転職を希望する社会人向けの試験枠が設けられている場合もあり、文系出身者や学歴に自信がない方にとっては狙い目といえるでしょう。
独立行政法人職員
独立行政法人で勤務する職員は準公務員として扱われますが、採用試験にSPIなどを取り入れている機関もあるため、民間企業との併願がしやすい点が魅力です。
さらに、ノルマなどをそれほど追求しなくても良い機関が多いため、業務が比較的楽であるケースが多いという点でも働きやすいメリットがあります。
独立行政法人の職員は法人ごとに採用方法が異なり、公務員試験が必須ではありません。
正規雇用の職員も多いですが、契約社員や任期付き職員として雇用されることもあります。
学歴などがあまり重視されないケースも多いため、学歴や文系出身者には狙い目となります。
公務員試験の難易度は?合格率・勉強時間・難しい理由についても解説
女性におすすめの公務員職4選
続いて、女性におすすめの公務員職を見ていきます。
公務員試験の受験資格に性別の条件はありませんが、男女で対応が異なったりすることはあるのでしょうか?
市役所職員
市役所職員は男女両方におすすめできる公務員職で、そのメリットは転居が必要になる部署の移動がほとんど無いことです。
移動が行われるとしても市役所内の部署で移動するか、勤務場所が変わるとしても同じ市内になることが多くなっています。
これによって家庭と仕事を両立しやすくなるため、特に女性におすすめの公務員職となっています。
さらにフレックス制や時短勤務を取り入れている市役所も多いため、仕事の融通が他の公務員職に比べて働きやすい職場になっています。
市役所の公務員試験の倍率は高い?難易度・試験内容・試験日程も解説【2024年】
国立大学法人等職員
国立大学法人等職員は正式な公務員ではありませんが、採用や給料計算などは公務員と同じように扱われます。
仕事内容は大学生のサポートや大学にある図書館の管理といった国立大学を運営する内容になっています。
そしてこの国立大学法人等職員は女性の比率が高くなっており、女性が重要な役職に付きやすい公務員職でもあります。
働いている女性に対する配慮が職場全体でされている可能性が高いため、働きやすい職場を探している方にはおすすめです。
裁判所事務官
裁判所事務官の仕事は、裁判を行う際に必要となる手続きのサポートや裁判所で発生する事務作業となっています。
仕事内容的には男女関係ありませんが、裁判所事務官は採用の際に女性を半分以上採用する一方受験者は男性の方が多くなっているため女性の方が合格率が高くなっています。
また定期的に転勤がありますが異動希望を尊重してくれるため県をまたぐことは少なくなっており、これも人気のポイントとなっています。
小中学校事務職員
小中学校事務職員は、小中学校の教師とは違い学校で使用される備品を購入したり施設を管理したり職員に関する事務作業を行ったりする職業です。
仕事内容を見て分かる通り基本的にはデスクで事務作業をすることになるため、体力的に楽という特徴があります。
さらに女性が働いていることも珍しくないため育休や産休を取りやすく、家庭との両立に理解がある職場も多くなっています。
国家公務員試験の合格率
| 試験名 | 申込者数 | 1次試験合格者数 | 最終合格者数 | 合格率(最終合格者数/申込者数) |
|---|---|---|---|---|
| 総合職試験(院卒者試験) | 1,350人 | 1,057人 | 668人 | 49.5% |
| 総合職試験(大卒程度) | 12,249人 | 10,141人 | 1,285人 | 10.5% |
| 一般職試験(大卒程度) | 24,240人 | 17,463人 | 7,557人 | 31.2% |
| 国税専門官採用試験(大卒程度) | 12,161人 | 5,910人 | 3,358人 | 27.6% |
| 一般職試験(高卒程度) | 9,681人 | 4,269人 | 3,132人 | 32.3% |
参照:国家公務員採用総合職試験実施状況、国家公務員採用一般職試験実施状況
国家公務員採用総合職試験は、財務省、総務省、外務省などいわゆる「キャリア組」と呼ばれるところが難易度が高いといわれています。
上記を見ると合格率は40.6%と高いのではと一見思いますが、総合職試験は東大など難関大学出身者が受ける試験であることからかなりレベルが高いでしょう。
また国家公務員採用一般職試験は大卒者の合格率が31.2%、高卒者の合格率は27.8%となっています。
一般職試験(大卒程度試験)では受験者が24,240人に対して合格者が7,557人とおおよそ3人に1人の割合で合格したということになります。
ちなみに地方公務員の場合、基本的に地元で働きたい方や地元貢献を考える人が多く、採用枠よりも受験者数のほうが多くなり合格者の数も狭まる傾向にあります。
各自治体のホームページでは過去の試験実地状況を見ることができるので、自分が受験を考えているところをチェックするようにしてください。
地方公務員試験の難易度は高い?他資格とのランキング比較や合格率・偏差値・勉強時間の目安について解説
文系から公務員を目指すメリット
文系で公務員を目指す際、理系が講義や研究で忙しいのに対し、文系は比較的自由な時間を持つ傾向があるため、その時間を就職活動に充てることができるというメリットがあります。
なかには大学の講義を通じて得た法律や経済学の知識がそのまま試験勉強や業務に活かされるケースもあるため、公務員試験の対策はしやすいといえるでしょう。
さらに、公務員として採用された後も仕事のイメージが文系寄りであるため、そこまでハードになりにくいといった傾向があります。
基本的に9時~17時で終わる仕事が多く、民間企業と比べると比較的楽であるといった声もあります。
また公務員はワークライフバランスを重視している立場にあることから、有給休暇や産休・介護休暇などの取得がしやすい点も魅力だといえます。
文系から公務員を目指すデメリット
文系で公務員を目指すことの主なデメリットとしてまず、公務員試験に失敗した場合、就職がスムーズにできにくいといったものが挙げられます。
研究室の教授のコネを利用してメーカーなどの一般企業に就職できる理系と比べると、文系の場合は公務員試験に失敗すると就職浪人になるリスクがあります。
また、専門的な知識が求められる民間のIT企業や公務員の技官採用などは受験が難しくなるため、就職活動の中で選択できる業界や職種の範囲が狭まってしまうという点も懸念すべきです。
ただし、公務員試験には共通する科目や受験方法が多いため、他の公務員職への転職という選択肢もあります。
民間企業に興味がない方や首尾よく公務員になれれば、それほど大きなデメリットとはいえないでしょう。
公務員のメリット・デメリット総まとめ!民間との違いや向いている人・おすすめしない人の特徴を解説
文系が公務員試験を目指す際のポイント3つ
ここでは、文系出身者が公務員試験合格を目指す際のポイントについて紹介します。
ポイント➀試験日まで逆算してスケジュールを立てる
最初に、試験日までの学習スケジュールを立ててみましょう。
一般的に国家一般職や地方上級を受験する場合、800〜1,200時間の学習時間が必要といわれています。
まずは試験日から逆算し、「いつ」「何を」「どのくらい」取り組むべきかを明確にしてみてください。
受験勉強の全体像を最初に把握することで、無理のないペースで学習を始めることができます。
特に社会人や学生などでほかにやるべきことがある中取り組む場合、確実なスケジュール管理が時間的な制約をうまく乗り越えるポイントとなります。
逆にあまりにも過密なスケジューリングだと続かないこともあるため、ある程度の余裕を持たせた日程を組むことが望ましいでしょう。
ポイント②面接対策を早めの段階からおこなう
公務員試験に合格を目指すのであれば、面接試験の準備は早めに行うことをおすすめします。
理由としては近年の公務員試験では面接試験の配点が年々増えており、公務員業界全体で知識よりも人物重視の傾向が強まっているからです。
公務員は国家や地方自治体にとって重要な業務を担うことが多いため、専門的な知識はもちろん重要です。
しかしながら、最近では公務員による情報漏洩などの問題も発生しており、重要な業務を担当するからこそ倫理観や責任感が求められる場面も多くなってきています。
知識の習得と並行して早い段階から自己分析を進め、説得力のある志望動機や自己アピールができるように準備するようにしましょう。
自力での対策に不安がある場合は通信講座や予備校の模擬面接などを利用するのもひとつです。
ポイント③通信講座・予備校を利用する
公務員試験対策には情報収集・受験先の選定・筆記試験の学習・面接準備を独学で行うには相当な労力と時間が求められます。
効率的に対策を講じて、エネルギーと時間を節約したいのであれば、予備校(通信講座)の利用を検討するのもひとつです。
通信講座・予備校を利用するメリットには「カリキュラムやスケジュールを立ててくれる」「質問や相談、添削をしてもらえる」「法改正や情報収集を受けられる」などたくさんあります。
独学に不安がある場合は、始める前に受講相談や体験レッスンを受けて独学と予備校利用のメリット・デメリットを考えて判断してみてください。
【2025年】公務員のおすすめ予備校・通信講座ランキング15選を徹底比較!
公務員を目指すのに不利になる学部は基本的にない
基本的に公務員になるのに不利な学部はなく、努力次第で誰でも公務員になることができます。
ただし、教育学部や外国語学部、人文学部などの文系学部は公務員試験に直接関連する講義が少ない傾向があり、法学部や経済学部出身者と比較すると相対的に不利とされることもあります。
しかし目指す職種によっては、異なる学部で培った専門知識や語学力は特定の職種で有益となる場合があり、学んだことが逆に大きなメアピールポイントになりうることも。
しかし、これは受験勉強で十分に補える部分なのでそこまで不安視する必要はないため安心して目指せます。
国際公務員になる難易度は高い?他資格とのランキング比較や合格率・偏差値・勉強時間の目安について解説
「文系だからとりあえず公務員」はNG
最後に文系で公務員を目指す方向けに「文系だからとりあえず公務員」という考え方をやめた方が良い理由をお伝えします。
公務員は中小企業と比較して給料も安くない上職も安定していますが、上記の考え方をやめた方が良い理由には何があるのでしょうか?
試験対策に長時間必要
公務員試験に合格するためには、勉強時間が教養試験のみで700~1,000時間、専門試験も含めると1,200~1,500時間が必要だと言われています。
1日3時間勉強するとしても専門試験を含めた場合1年~1年半という勉強期間が必要になり、民間企業の就職活動と比較して非常に労力がかかります。
さらにそれだけ勉強しても合格が保証されるわけではないため、民間企業の就職活動も同時並行で行うとなるととても大変な学生生活になってしまいます。
教師を目指す教育学部などに所属している場合は別ですが、「とりあえず」で目指すには労力とリスクが大きいようです。
お金と時間を無駄にするリスクがある
大学とは別に公務員を目指すとなると、公務員専用の予備校に通ったり通信講座を受講する人が多くいらっしゃいます。
しかし上記でご紹介した通り公務員試験対策の勉強には膨大な時間と労力が必要になり、予備校などに通って学習効率を上げてもそれは変わりません。
そんな中で「とりあえず」や「なんとなく」という動機で公務員を目指していると途中で挫折する人も多く、お金と時間を大量に無駄にしてしまうこともあるようです。
さらに公務員になった後も仕事にやりがいや楽しさを見出すことができず、モヤモヤした気分を抱えてしまう可能性もあります。
そのため「とりあえず」公務員を目指すのではなく、仕事内容に興味が持てるかなどをよく考えて公務員を目指すようにしましょう。
公務員試験の流れ
国家公務員採用一般職試験については人事院のホームページで確認できます。
また専門職は様々な職種があり、さらに大卒・高卒かどうかによって日程が異なり、こちらも人事院のホームページで見れます。
さらに地方公務員試験については各都道府県や自治体のホームページを見るか、「公務員試験総合ガイド」のサイトもおすすめです。
ここでは、一般的な公務員試験の流れについて紹介します。
出願(3月~4月)
一般的に2~5月あたりになると各自治体や人事院のホームページではその年の試験案内が公表されます。
そして3月~4月を締め切りとした受験申込がおこなわれます。
最近では郵送だけではなく、インターネットによる受験申込が主流となりつつあります。
1次試験(5月~6月)
5月~6月頃は一次試験(筆記試験)が行われます。
筆記試験として教養択一・専門択一・論文試験・専門記述試験が含まれます。
専門記述は国家総合職・外務専門職・東京都・裁判所一般職・国税専門官・財務専門官・労働基準監督官など、一部の試験種のみで実施されるので職種ごとの対策が必要です。
2次試験(7月~8月)
1次試験に合格した受験者を対象に、人物試験として個別面接が行われ、志望動機や自己PRに関する質問がされます。
個別面接はほとんどの公務員試験で実施され、集団面接や集団討論は地方上級や市役所などで行われることが一般的です。
2次試験を通過すると晴れて最終合格となります。
最終合格者には主に個別面接(15~30分程度)が行われ、受験生の意向を確認する場が設けられます。
具体的には併願の状況や複数の試験に合格した場合の対応について質問されます。
また、国家総合職や国家一般職(大卒)については、各府省や機関が実質的に採用面接として「官庁訪問」を実施します。
原則として翌年の4月1日からの採用ですが、既卒者・社会人は10月からの採用といったケースもあります。
【2025年】公務員のおすすめ予備校・通信講座ランキング15選を徹底比較!
アガルート公務員講座はサポートが手厚い

今回は文系の方が公務員を目指す上でおすすめの学部や、文系で培ったスキルや知識が活かせる職種について解説してきました。
公務員といってもさまざまな職種や業務内容があり、文系出身の方が有利になる仕事もたくさんあります。
特に、行政職や経済系の業種は文系的な知識が活用できる可能性が高いので狙い目です。
それなりの学習時間は必要ですが、対策と志望動機やアピールポイントを明確にしておけば合格率はぐっとアップするでしょう。
もし小論文や面接対策に不安があるようであれば、通信講座の利用もおすすめです。
アガルート公務員講座の評判まとめ
- テキスト・講師・サポート内容の質が高い
- 合格特典や割引制度が豊富にある
- 講義やテキストがわかりやすいという声があった
- 実績が少ないので少し不安という声もあった
- 初心者~上級者の幅広い方におすすめできる講座
難関資格の合格実績のあるアガルートでは、受講すれば公務員試験合格の距離がぐっと縮まります。
実力はの講師陣夜指導や手厚いサポート、充実したオリジナルテキストはアガルートにしか出せない持味で、大きなアドバンテージになってくれるはずです。
アガルートでは合格特典やお得なキャンペーンも実施されているのでぜひチェックしてみて下さい。