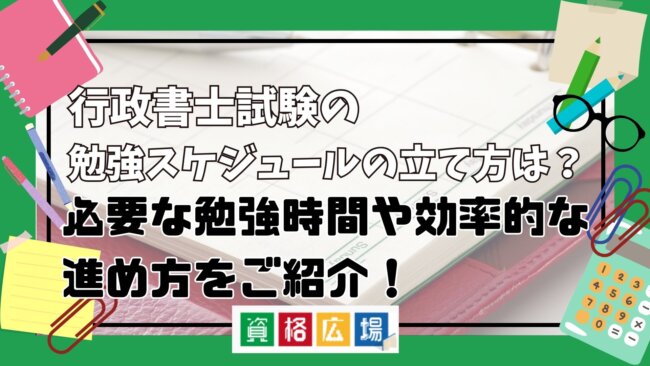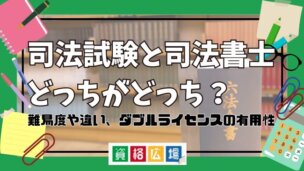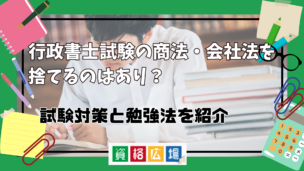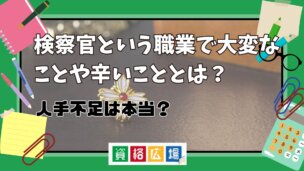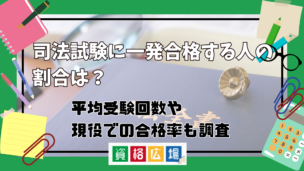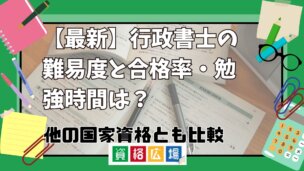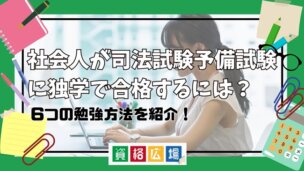国家資格である行政書士に合格するには、合格率10%の門をくぐり抜けなければなりません。
そのため、いくら受験資格がないからといって決して簡単な資格ではないと言えます。
行政書士になるためには、闇雲な勉強ではなく計画的・効率的に勉強を進めることが必要になります。
そこでこの記事では、行政書士試験に合格するために必要なスケジュールの立て方や効率の良い勉強の進め方をご紹介していきます。
行政書士試験におすすめの予備校・通信講座TOP3
行政書士試験の合格までに必要な勉強時間
行政書士試験に合格するには、ある程度のまとまった勉強時間が必要です。
予備校や通信講座を利用している方は500~600時間、知識のない方が独学で勉強すると800~1,000時間は必要だと言われています。
合格日から逆算すると毎日3時間程度の勉強をしても半年から1年程度かかるので、ある程度の覚悟が必要と言えるでしょう。
行政書士試験の勉強スケジュールの立て方
前述膨大な勉強時間が必要になる行政書士試験では、スケジュールを立てるときにもポイントがあります。
効率的な勉強をするためにも、以下の3つのポイントを覚えておくようにしてください。
逆算して計画を立てる
スケジュールを立てるときに非常に大切なのが「逆算」して考えることです。
「逆算」とは試験日をゴールとしてそこまでの間に自分が使える時間を計算し、その時間の中でやりくりするという考え方です。
具体的には、勉強を完成させるには自分は1日どれくらい勉強する必要があるのかを計算します。
ただ人によって勉強スピードも理解度も違うため、一概に「1日〇時間勉強すれば間に合う」ということは決められません。
自分のペースを把握した上で「平日は1日〇〇時間」「休日は1日〇〇時間」というようにざっくりとスケジュールを作成しましょう。
半年・月・週単位と細分化していく
スケジュールを組むときに意識したいのが「試験日から逆算し、細かい時間ではなく大まかな時間で考える」ということです。
つまり、1週間ごとに細かく計画を立てるのではなくまずはざっくりと勉強期間を「半年」と定めて、大まかに勉強する分野を決めるのです。
| 1か月目 | 憲法・民法 |
|---|---|
| 2か月~3か月目 | 民法・行政法 |
| 4か月目 | 商法・基礎法学・過去問 |
| 5か月目 | 一般知識・過去問・記述対策 |
| 6か月目 | 模試・過去問・本試験 |
といったように大雑把に行うことを決めるのがおすすめです。
ちなみに試験科目の中でも憲法・民法・刑法のいわゆる「上三法」は行政書士試験の肝となるため、最初に取り掛かって出来る限り早くマスターする必要があります。
スケジュールを組むときには最優先で配置しましょう。
そして半年の予定が立てられたら、次に月単位の内容を決めます。
| 1か月 | 憲法・民法の全体像を把握し、過去問を用いて理解度を深めていく。 |
|---|---|
| 2か月 | 民法の復習をしつつ行政法の全体像を把握し、過去問を用いて理解度を深めていく。 |
上記のように1か月単位の勉強スケジュールを立てます。
月単位の予定が立てられたら、最後は1日の予定内容を考えます。
| 1日 | テキスト・参考書を読んで行政書士試験の全体像を把握する。 |
|---|---|
| 2日 | テキスト・参考書を読んで行政書士試験の全体像を把握する。 |
| 3日 | 憲法 テキスト・参考書の内容を理解しながら読む(30分) 過去問で確認する(30分) テキスト・参考書の内容を理解しながら読む(30分) 過去問で確認(30分) 休憩(15分) テキスト・参考書の復習と暗記(60分) |
毎日のスケジュールは自分の得意不得意や理解度によって進捗状況が変わるため、1週間ごとに見直しを行い全体が遅れないように調整しましょう。
スケジュールには予備日を用意しておく
行政書士試験の勉強を進めていく中で、スケジュールが全て計画通りにいくとは限りません。
自分で立てた計画を達成できなくても落ち込まないように、リカバリーができる予備日を1日用意しておくことがおすすめです。
例えば1週間のスケジュールの中で土曜日を「空き日」とし、金曜日までにできなかったものを挽回するというイメージです。
行政書士試験講座ならアガルートアカデミーがおすすめ!
行政書士試験合格を目指すならアガルートアカデミーがおすすめです!
フルカラーで見やすいテキスト教材と分かりやすい動画講義で、初めて資格勉強をする方でも充分合格が目指せるカリキュラムになっています。
合格者には受講費全額返金orお祝い金5万円の特典もあるのでモチベーションの維持も期待できます!
最短ルートで合格が目指せる!
アガルート公式HPはこちら
行政書士試験の科目別の勉強スケジュール
行政書士試験は民法・行政法・基礎法学・憲法・商法・一般知識の6科目から出題されます。
行政書士試験の出題科目と配点の割合は基礎法学3%、憲法9%、民法25%、行政法37%、商法7%、一般知識19%となっています。
それぞれ同じ比率で問題が組まれているわけではないため、配分の大きな科目を軸にして勉強する工夫が大切です。
配点が6割の「民法」を最優先で勉強する
民法は試験全体の25%を占める科目です。
具体的な事例が出題され、事例に合った条文や判例が分からなければならないためただ暗記するだけでは解答できません。
民法の出題内容は難しい上、記述式は2問・計40点と配点が大きいため確実に押さえておきたいポイントです。
過去問を練習して傾向をつかむと良いでしょう。
最重要科目「行政法」を押さえる
また、行政法は試験全体の37%を占める科目で最も重要な科目です。
行政法は条文と判例について細かい知識が問われる科目となっており、出題形式は択一式・多肢選択式・記述式の3種類です。
記述式の問題は内容を理解しないと解けないため、必然的に知識量が豊富になります。
そのため、記述式の勉強は早めに始めることが得策です。
行政法は1問あたりに必要な勉強時間が他の科目と比べて長いため、試験勉強の初期段階で勉強を始める必要があります。
その他科目(基礎法学・憲法・商法・一般知識)は合格ライン程度でOK
その他科目には基礎法学・憲法・商法・一般知識があります。
しかし民法や行政法よりは重要度が低いため、勉強時間を割きすぎないようにしましょう。
ただし、一般知識の科目は足切りがあるので注意が必要です。
政治経済から時事問題と出題範囲が幅広いため対策が難しいと言われている一般知識は、56点満点中24点未満だと足切りになってしまいます。
民法や行政法の勉強を優先し、一般知識やほかの科目は適度な勉強時間が確保できるよう調整しましょう。
一般知識を完全把握することは難しいため、完全把握を目指すのではなく足切り回避のための勉強をするのもお勧めです。
行政書士試験の学習を効率的に進める方法
出題範囲の広い行政書士試験の学習を闇雲にやっていては、時間がどれだけあっても足りなくなります。
長時間ダラダラと勉強するよりも、短時間集中して効率的に学習を進める方法を取るのが勝利への近道です。
スケジュールの確認と修正
スケジュールは立てて終わりではありません。
1度決めたスケジュールに固執する必要はなく、学習状況に合わせた臨機応変なスケジュールの確認・修正が大切です。
最低でも週に1回はスケジュールの確認・修正を行い、最終目標に向けた計画が遅れすぎないよう気を付けてください。
参考書の活用
独学で勉強する方は参考書の使用が必須です。
参考書内で重要とされている部分は重点的に勉強しましょう。
参考書の内容には可能な限り目を通し「解説」や「ポイント」と記載されている重要箇所を見落とさないように注意してください。
「スッキリわかる行政書士」シリーズ
大手資格学校のTACが出版している「スッキリわかる行政書士」シリーズは、初心者の方にもわかりやすく基礎を解説してあります。
分かりやすい解説・図版・豊富なイラストでスイスイ理解が進みます。
また確認テストがあるので理解度の確認もできるのがおすすめです。
「うかる!行政書士民法・行政法解法スキル完全マスター」
伊藤塾が出版している「うかる!行政書士民法・行政法・解法スキル完全マスター」は、勉強しているのに問題が解けない・点数が伸び悩んでいるという方向けの本です。
過去の出題傾向をもとに、問題のどこに着目すれば点数が伸びるのかが解説されているのが魅力と言えます。
過去問には司法試験や司法書士試験で出題された問題も収録されているので、法律知識の底上げも図ることができるでしょう。
「合格革命 行政書士 基本テキスト」
フルカラーで圧倒的に分かりやすい基本書を探している人にはこちらがおすすめです。
重要語句は赤シートで隠して覚えることができるのも使いやすいポイントです。
行政書士試験に必要な知識はギュッとこれ1冊に詰め込まれているため、試験勉強開始から合格までずっと使える1冊となっています。
過去問の活用
行政書士試験は試験範囲が広いため、短期間で試験範囲を網羅することは難しいでしょう。
参考書を隅から隅まで読み込むよりも、過去問を分析して重要な分野やポイントを押さえて重点的に勉強することが必要になります。
過去問は試験の出題傾向が把握でき、何度も解いていると重要な分野がどこなのか理解できるようになってきます。
最初は過去問を見てもよくわからないことが多いですが、できる限り早い段階で過去問に手を付けてください。
過去問のテキストは大手予備校LECから発売されている「出る順行政書士 良問厳選 肢別過去問題集」が良問かつ解説も手厚いのでおすすめです。
模試の活用
自分の実力を測るためにも模試を受けることは忘れずにやっておきましょう。
模試を活用することで、自分の苦手科目の把握や試験の時間配分に慣れることができます。
また模試は苦手分野の分析や振り返りを行うことで知識が定着するため、同じミスを防ぐ効果もあります。
ただし模試の結果に一喜一憂しないように注意してください。
記憶定着の勉強法
人間の脳は記憶しても端からどんどん忘れていくため、復習を繰り返して脳に定着させて長期記憶にしなくてはなりません。
復習をしないと1週間後には77%、1か月後には79%も忘れてしまうという研究結果があります。
復習を繰り返すことでこの忘却率は減少していくので、1度覚えたこともこまめに復習して長期記憶にしていきましょう。
復習のタイミング(24時間以内の復習と1週間以内の総復習)
復習のタイミングは「夜寝る前」と「翌朝」の2回をお勧めします。
脳内に中期的な記憶として内容が残っている間に反復学習をして長期記憶にすることで定着率が保たれます。
記憶の定着率を更に上げるには「平日には2回復習をし、週末に総復習として問題を解いてみる」ことがお勧めです。
参考書や資料を読むだけではなく、書いたり声に出して読むことも記憶定着には有効な方法のためぜひ試してみてください!
行政書士試験の勉強スケジュールまとめ
- スケジュールは逆算して立てる
- 民法と行政法の勉強時間は長くとる
- スケジュールは臨機応変に修正する
行政書士試験に合格するためには、目標に向けたスケジュールを立てて都度確認・修正を行うことが重要です。
試験日から逆算してスケジュールを立てるようにしましょう。
得点配分の多い民法・行政法は重要科目のため早めに勉強を始め、勉強時間を長く取れるように調整する必要があります。
苦手科目に手間取ることがあるかもしれませんが、過去問や参考書を活用して自分の苦手科目を把握しスケジュールの調整に役立てていきましょう。
足切りのある科目もあるため、民法・行政法だけに気を取られず一般知識やその他科目の勉強時間が疎かになりすぎないようなスケジュールを立てて合格を目指してください。