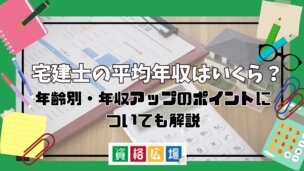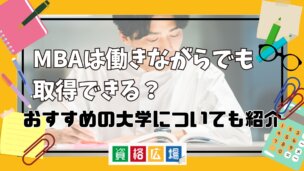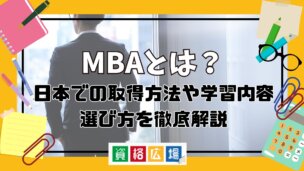宅建試験が間近に迫る直前期には一体何をすればいいのか迷いますよね。
全範囲を総復習するには時間が足りないし、かといってヤマを張るのもリスキーです。
何をすればいいのかわからず誤った勉強法に走らないように、宅建試験直前期の勉強法や予備校の直前講習、宅建試験直前の過ごし方について解説します。
宅建試験の詳細

宅建試験直前期の勉強法をご紹介する前に、宅建試験がいつ行われるのか、またどのような試験形態なのか、その他試験料など宅建試験の詳細をご紹介します。
宅建試験の基本情報を以下にまとめました。
| 試験形式 | マークシート式(4択) |
|---|---|
| 試験日時 | 2023年度10月15日 13:00~15:00 ※5点免除者は13:10~15:00 |
| 試験地 | 各都道府県の指定会場 |
| 申込み方法 | インターネット 郵送 |
| 申込み期間 | 2023年7月1日(土)~7月中旬※ネット 2023年7月1日(土)~7月下旬※郵送 |
| 受験票発送日 | 2023年9月下旬 |
| 受験資格 | 特になし |
| 合格発表日 | 2023年11月下旬 |
| 受験料 | 8,200円(税込み) |
宅建試験の出題範囲
宅建の試験範囲は「権利関係」「法令上の制限」「税・その他」「宅建業法」の大きく4つに分けられます。
下に出題範囲を分かりやすく表にまとめました。
| 出題範囲 | 出題科目 | 配点 |
|---|---|---|
| 権利関係 | 民法 借地借家法 建物区分所有法 不動産登記法など | 14点 |
| 法令上の制限 | 国土利用計画法 都市計画法 建築基準法 農地法など 土地区画整理法 宅地造成等規制法 | 8点 |
| 税・その他 | 税金に関する法律 鑑定評価基準・地価公示 住宅金融支援機構・景品表示法・統計 土地・建物 | 8点 |
| 宅建業法 | 宅建業法 特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保に関する法律 重要事項の説明 37条書面など | 20点 |
宅建試験の5点免除とは?
宅建試験では定められた2つの条件を満たした方のみ46~50問目が免除される特別な制度があります。
この制度を使用すると問題数が5問少なくなり合格ラインも5点引き下げられますが、それに伴い試験時間も10分短くなるので注意が必要です。
5点免除の制度を利用するための条件は受験時に宅地建物取引業に就業していることと、従業証明書を持っていることになります。
宅地建物取引業とは土地や建物の売買代理行為などを行う不動産専門の職業で、従業証明書は宅地建物取引業者が従業者に交付する証明書です。
宅建試験直前の間違えた勉強法3つ

宅建試験の直前の勉強はとても大切です。
試験直前に方向性の間違った勉強法で時間を取られては勿体ないですし、せっかく努力しても無駄となってしまいます。
直前期の時間が限られている期間だからこそ、効率的に知識の定着を高めたいものです。
ここでは多くの人がしてしまう宅建試験直前期の間違えた勉強法3つについて解説していきます。
・細かい知識まで網羅しようとする
・アウトプットに偏った勉強法
間違った勉強法①新しいテキストを買う
宅建試験直前期には何度もやりこんだテキスト、問題集だけで本当にいいのかと不安になってしまいます。
宅建試験の直前期にしてはいけない勉強は、もしかしたら知らない情報が載っているかもしれないからと別のテキストに手を出すことです。
市販のものでも予備校独自のものでも、極端に情報が厳選されたものでなければ合格するための情報量に大差はないので、新しいものに取り掛かる必要はありません。
宅建の試験直前期の勉強は反復がとにかく大事です。
新しいテキストを一から始めるよりも、使い慣れたテキストで弱点をおさらいする時間に回すことがおすすめです。
ただし、法改正や模試を収録した直前対策本は総仕上げ用のサブテキストとして買い足してもいいでしょう。
間違った勉強法②細かい知識まで網羅しようとする
新しいテキストを買ってしまう心理と似ていますが、本当にこれだけでいいのか?と不安になるあまり、試験直前に重箱の隅をつつくような情報にまで手を付けるのは間違った勉強法です。
テキストや問題集の重要度表示で「重要ではない」に関しては飛ばして問題ありません。
目標は「試験に受かること」であって、満点を取ることではないのです。
本試験で全く知らない情報が出てきたら、他の受験生も全員知らないことだと思って気にしないようにしましょう。
宅建の試験は出る項目が明確ですので、直前期は何に注力すべきかを理解して試験に受かるための勉強が大切になります。
間違った勉強法③アウトプットに偏った勉強法
実戦に慣れるためにも、宅建試験直前期はアウトプットに重点を置いた勉強法が良いとされています。
ただし、とにかく数だけこなすような勉強は効果が薄く、そのような極端にアウトプットに偏った勉強方法はしないように注意が必要です。
また、アウトプットの勉強に集中するあまりインプット作業を怠らないようにすることにも気をつけなければなりません。
暗記項目は日々繰り返さないとどんどん忘れてしまうので、暗記項目を見直す時間は、試験前日まで毎日設けることがおすすめです。
過去問は、実戦演習をしながら苦手分野をおさらいし、理解を深めるのが目的なので、インプットとアウトプットのバランスを考えながらしっかりと向き合うことが重要になります。
宅建試験直前期の勉強方法6つ

宅建試験直前期になったら、今まで以上に計画的に勉強に取り組むようにしましょう。
宅建試験直前期に大切なことは、何をすればいいのか・何を優先すべきか等を明確にして万全な体制でいることです。
ここでは、その大切なことを踏まえた上で、宅建試験直前の勉強方法6つをご紹介していきます。
・過去問の取り組む
・回答の順番を決めておく
・時間配分の確認をする
・頻出項目を抑える
・通信講座を利用する
勉強法①苦手な分野を詰める
インプット作業の最中や、問題集・過去問を何度も解くうちに、「何度やっても覚えられない暗記項目」「何度解いても間違える問題」は必ず出てきます。
日々の勉強に追われているうちはついつい後回しにしてしまうかもしれません。
しかし、宅建試験直前となれば目を逸らさずに向き合う必要があります。
おすすめの試験直前期の勉強法は1週間~2週間、毎日必ず苦手分野に取り組む時間を設けることです。
覚えたと思っても試験日まで毎日反復することで、苦手だった分野が試験直前には自信を持って回答できる得意分野になっているはずです。
勉強法②過去問に取り組む
試験の直前期になると、過去問を解く中で何度も間違えてしまう問題、理解できていない問題、後回しにしている問題などが浮き彫りになってくると思います。
過去問でよく間違える問題の傾向を把握・分析し、重要な問題であるならばしっかりと対策しておくことが大切です。
難問・奇問は思い切って捨ててしまって構わないですが、重要度の高い問題をそのままにしてしまうのはいけません。
直前期で時間は限られていますがここには時間を割くべきなので、解説を理解できるまで読み、テキストに戻って本文を読み返すなどしてしっかり問題と向き合うことをおすすめします。
また、前後の並びやページの位置などで答えを覚えてしまっている場合もあるので、年代別の過去問や模試を本試験と同じ制限時間の中で解くのも効果的です。
»宅建合格のための上手な過去問の使い方を紹介!おすすめの過去問題集7選
勉強法③回答の順番を決めておく
宅建試験直前期の勉強法として挙げられるのが、回答の順番を決めておくことです。
宅建試験は全50問あり、以下の5つの順番で出題されます。
②法令上の制限の問題(第15問~第22問)
③「税・その他」のうち税・鑑定評価の問題(第23問~第25問)
④「宅建業法」の問題(第26問~第45問)
⑤「税・その他」のうち5問免除対象の問題(第46問~第50問)
1問目から順番に解かなくてはいけないという決まりはないので、自分の得意な分野や分かりやすい問題から解くことをおすすめします。
難しい問題や解くのに時間がかかりそうな問題に最初から取り掛かると大幅な時間のロスになってしまう可能性が高いので、そのような問題は最後に回すのが効率的です。
勉強法④時間配分の確認をする
宅建試験直前期の勉強法として、時間配分の確認も忘れてはいけないものです。
宅建試験の時間は120分で問題数は50問なので、1つの問題にかけられる時間は約2分半しかありません。
どの問題に時間をかけるのか、かけないのかを予め決めておかないと全ての問題に取り掛かることなく試験が終わってしまうこともあり得ます。
試験本番と同じ時間で過去問を解き、どのようなペースになるのか確認して、最も効率の良い解き方を見つけておくことがおすすめです。
勉強法⑤頻出項目を抑える
宅建の試験は、毎年出題される頻出項目がわかりやすい点が特徴的です。
これを知っているのと知らないのとでは大きく差が出るので、得意不得意など関係なく絶対に抑えていかなければならないポイントとなります。
インターネットで検索するか、過去問を解いていくうちに自然と頻出範囲は分かってくると思うので、しっかりと抑えておきましょう。
勉強法⑥通信講座を利用する
宅建試験直前期におすすめの勉強法として、通信講座を利用することも挙げられます。
宅建試験に精通したプロの講師が過去問を徹底的に分析した上で講義を提供しているため、本試験でも出題される過去問や似た問題に取り組むことができます。
また、これまで学習してきて分からないところがあったら質問してすぐに解決できるのも嬉しいポイントです。
宅建試験対策の講座を開いている通信講座はたくさんありますが、迷っている方は大手通信講座のアガルートアカデミーがおすすめとなります。
通信講座ならアガルートアカデミー

前述の通り、おすすめの通信講座で挙げられるのがアガルートアカデミーです。
アガルートはオール・イン・ワンカリキュラムの提供のみで試験直前期には無駄が多いと思うかもしれませんが、テキストなしコースなら費用は比較的かかりません。
受講生の宅建試験合格率は高く、全国平均の3.50倍の59.5%にもなることから、アガルートの指導力の高さが伺えます。
| 学習形式 | オンライン |
|---|---|
| 問い合わせ | お問い合わせはこちら |
| コース | 入門総合カリキュラム 入門総合カリキュラム(テキストなし) 演習総合カリキュラム 演習総合カリキュラム(テキストなし) |
| 受講料金 | 54,780円(入門) 32,780円(入門・なし) 76,780円(演習) 54,780円(演習・なし) |
| 学習方法 | インターネットによる配信講座 オリジナルテキスト |
| 質問 | Facebookにて質問可能 |
| サポート | 無料資料請求 無料体験 各種割引制度あり 合格特典あり ホームルーム制度 |
| 公式サイト | 公式サイトはこちら |
入門総合カリキュラム
アガルートの入門総合カリキュラムは、初めて宅健士を目指す方や、基礎から学び直したい方におすすめのコースです。
基礎を学べる講座はもちろん、その他にも10年分の過去問講座や模擬試験もついているので入門総合カリキュラムだけでもしっかりとした実力を身につけることができます。
分からないところはFacebookで講師にいつでも質問できるなど、学習を支えるサポート体制も充実しています。
演習総合カリキュラム
演習総合カリキュラムは本試験で25点以上取る実力がある方や不動産関係の職種に就いている方、またインプットとアウトプットの反復学習をしたい方におすすめです。
入門総合と同じく模擬試験や過去問もついている他、直前答練や全科目の重要事項をまとめたテキストもあり試験本番までの対策を効率よく行うことができます。
アガルートの公式サイトにサンプル講座の動画があるので、気になる方はそちらも確認してみると参考になるかもしれません。
宅建スクールの直前対策コースには申し込むべき?

「間違えた勉強法」の中で少し触れましたが、直前期はアウトプットを主軸とした能動的な勉強法が望ましいです。
講義を受けることは受身の勉強法なので、講義を受ける目的がはっきりしている方や講義以外の時間にアウトプットの時間を割ける方は受ける価値があるでしょう。
また、直前対策コースは価格が跳ね上がるので、ご自身の財布とも相談して選びましょう。
宅建スクール1:TAC
短期合格を狙うコース、演習問題だけのコース、頻出論点コース、法改正コース、試験問題の解き方コース、予想問題コースなど、直前対策だけで10種類近くのコースが用意されており、それぞれの目的は多岐に渡ります。
コース内でさらに科目ごとに選択できるものもあります。
費用はコースにより異なり約1,900円~70,000円までと幅広くなっています。
講義数は3時間のものから全20回のものまで様々で、コースの種類が多く、自分の目的に合ったコースを選択できるのは魅力的です。
コースの目的が細分化されているので無駄な時間を過ごす心配がなく、自分の知りたい情報だけを得ることができるでしょう。
通信講座の用意も豊富なので都合のいい時間に視聴することができます。
論点だけを述べるような講義は移動時間などの隙間時間を有効活用できるでしょう。
宅建スクール2:日建学院
直前対策コースは以下の3段階になっており、料金は100,000円です。
日建学院の直前対策コース
①重要論点を抜粋して解説する講義形式(全14回・Web受講)
②演習問題と解説(全14回・通学受講)
③本試験直前の3週間で厳選問題・予想模試・公開模試(全11回・通学受講)
また、③のみの「直前攻略コース」もあり、こちらは50,000円と直前対策コースの半額となっています。講義などはなく、実践演習だけ受けたい方はこちらを選択できます。
重要論点を解説する講義はWeb上での受講になるため、都合のいい時間を使って受講することができます。
一方演習問題の段階は通学での受講ですが、このような演習は自宅でやるよりもより本番に近い状況で問題を解くのが望ましいので最適な形でしょう。
通信・通学のいいところ取りなコースでバランスがいいですね。
宅建スクール3:LEC
直前対策向けの講義を組み合わせたパック形式で3種類の用意があります。
①弱点補強パック
重要論点講義、一問一答演習、予想問題講義、頻出論点講義の4つの講座を組み合わせたコースです。重要論点に絞った講義と演習をバランスよく組み合わせています。
②追い込み逆転パック
難易度別の模試3回分に、一問一答演習、予想問題講義、頻出論点講義の3つの講義が加わったコースです。
模試3回を通して弱点をあぶり出し、自分のレベルを知ることができます。
③直前3兄弟パック
一問一答演習、予想問題講義、頻出論点講義の3つがパックになったコースです。
この3つの講義は①と②のコースには必ずついてくる講義でもあり、演習問題を中心にコンパクトに対策したい方向けのコースですね。
費用は通信・通学などの形態にもよりますが25,000円~70,000円前後です。学習状況に応じて必要な講義が含まれているパックを選びましょう。
予備校に関しましては下記で紹介していますので、ぜひご覧くださいませ。
»【宅建予備校ランキング】宅建おすすめ予備校9選!予備校の特徴と費用紹介
宅建試験の過去問例題3つ

前述の通り、宅建試験の直前対策として過去問に取り掛かることは大切です。
ここでは、以下に科目ごとの頻出項目を一部過去問と共に3つ載せますので、最終チェックの意味も込めておさらいしてみましょう。
例題①宅建業法
●頻出項目 35条(重要事項の説明)、37条(書面の交付)
過去出題例(平成28年‐問30)
Q.宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明及び同法第37条の規定により交付すべき書面(以下この問において「37条書面」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1.宅地建物取引業者は、建物の貸借の媒介における重要事項の説明において、借賃の額並びにその支払の時期及び方法について説明するとともに、37条書面に記載しなければならない。
2.宅地建物取引士は、重要事項の説明をする際に、相手方から求められない場合は、宅地建物取引士証を提示しなくてもよい。
3.宅地建物取引業者は、37条書面を交付する際に、相手方の同意があった場合は、書面に代えて、電磁的記録で交付することができる。
4.宅地建物取引業者は、宅地建物取引士をして37条書面に記名押印させなければならないが、当該書面の交付は宅地建物取引士でない従業者に行わせることができる。
答え:4
「借賃の額・支払時期・方法」は、37条書面の記載事項ですが重要事項説明書の記載事項ではありません。
このように、両方の内容を細かく暗記していないと解けないひっかけ問題が頻繁に出題されます。
35条・37条の中身は白紙の状態から全て書き出せるくらい覚え込んでも無駄にはなりません。試験日までに完璧に頭に入れておきましょう。
例題②権利関係
●頻出項目 借地借家法(賃貸権との比較、民法の賃貸借の規定との比較)
過去出題例(平成26年‐問11)
Q.甲土地の所有者が甲土地につき、建物の所有を目的として賃貸する場合(以下「ケース1」という)と、建物の所有を目的とせずに資材置き場として賃貸する場合(以下「ケース2」という)に関する次の記述のうち、民法及び借地借家法の規定によれば、正しいものはどれか。
1.賃貸借の存続期間を40年と定めた場合には、「ケース1」では書面で契約を締結しなければ期間が30年となってしまうのに対し、「ケース2」では口頭による合意であっても期間は40年となる。
2.「ケース1」では、賃借人は、甲土地の上に登記されている建物を所有している場合には、甲土地が第三者に売却されても賃借人であることを当該第三者に対抗できるが、「ケース2」では、甲土地が第三者に売却された場合に賃借人であることを当該第三者に対抗する方法はない。
3.期間を定めない契約を締結した後に賃貸人が甲土地を使用する事情が生じた場合において、「ケース1」では賃貸人が解約の申入れをしても合意がなければ契約は終了しないのに対し、「ケース2」では賃貸人が解約の申入れをすれば契約は申入れの日から1年を経過することによって終了する。
4.賃貸借の期間を定めた場合であって当事者が期間内に解約する権利を留保していないとき、「ケース1」では賃借人側は期間内であっても1年前に予告することによって中途解約することができるのに対し、「ケース2」では賃貸人も賃借人もいつでも一方的に中途解約することができる。
答え:3
借地借家法では、問題文のケースに適用される法律は何か?をまずおさえなければなりません。
契約期間、対抗要件、解約の決まりごとなど、適用される法律が民法か借地借家法かで全て変わります。
とても複雑な部分ですが、土台となる暗記をしっかりした上で、問題文をよく読み何が問われているかを理解することが鍵となります。
例題③法令上の制限
●頻出項目 土地計画法の開発許可、建築基準法の建築確認
過去出題例(平成28年‐問17)
Q.都市計画法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、この問において「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時特例市にあってはその長をいうものとする。
1.開発許可を受けた者は、開発行為に関する工事を廃止するときは、都道府県知事の許可を受けなければならない。
2.二以上の都府県にまたがる開発行為は、国土交通大臣の許可を受けなければならない。
3.開発許可を受けた者から当該開発区域内の土地の所有権を取得した者は、都道府県知事の承認を受けることなく、当該開発許可を受けた者が有していた当該開発許可に基づく地位を承継することができる。
4.都道府県知事は、用途地域の定められていない土地の区域における開発行為について開発許可をする場合において必要があると認めるときは、当該開発区域内の土地について、建築物の敷地、構造及び設備に関する制限を定めることができる。
答え:4
都道府県知事に「許可を取る」ことと「届け出る」ことの違いを把握しておく必要があります。
また「都市計画区域の指定」は二以上の都府県にまたがる場合は国土交通大臣の許可、「開発許可」は二以上の都府県にまたがる場合でも都道府県知事の許可など微妙に異なる知識が多く、なんとなくなぞるだけの勉強法では太刀打ちできません。
細かい知識まで正確におさえ、丁寧に暗記しましょう。
税/その他分野
税法は毎年改正され、改正点は試験で特に狙われやすいポイントとなります。
分野ごとにまんべんなく出題されますが、それぞれの改正点は重点的におさえておくことがおすすめです。
不動産鑑定評価基準と地価公示法は交互に出題される傾向にあるので、その年に出そうな分野を予測し復習しておくと有利になります。
また、後回しにしてしまいがちな統計もしっかりと取り組んでおくことが大切です。
完璧に暗記するなど深入りは不要ですが、最新の情報は要チェックしておきましょう。
宅建試験直前の過ごし方

宅建試験直前は緊張でそわそわしがちです。
体調不良や忘れ物、遅刻などせっかく頑張って勉強したのが全て水の泡になってしまっては悔やんでも悔やみきれないと思います。
宅建は年に一度しかありません。後悔のないように、事前にしっかり準備して挑みましょう。
当日のスケジュールを作成する
試験会場までの交通機関、所要時間は必ず確認しておきましょう。
試験会場が大学の場合、敷地内に入ってからも結構歩きますし、受験生が多いので教室の数も多いです。
「駅から徒歩○分」と書いてあっても多めに見積もって行動すれば、なにかトラブルがあっった場合でも焦ることはありません。
忘れ物をしないように前日に持ち物を用意、当日再確認することも大切です。
また、移動時間や休憩時間などは特に何を勉強したらいいのかわからなくなるので、「ここだけは直前にもう一度チェック!」というような項目をいくつかピックアップしていくといいでしょう。
体調を整える
宅建の試験は毎年10月の第3日曜日に行われ、季節の変わり目で肌寒くなる時期なので、風邪など引かないように普段から気を付けておきましょう。
前日は余裕をもってベッドに入り、十分な睡眠時間を確保することをおすすめします。
当日は体温調節のできる羽織りを一枚持って行くと便利です。
また、試験中眠くなるのを防ぐために朝ごはんを食べすぎないようにするなど工夫しましょう。
まとめ:宅建試験直前の勉強方法と過ごし方
・2023年度の宅建試験は10月15日に行われる
・宅建試験直前期は間違った勉強法をしないように注意が必要
・宅建試験直前期には何を優先すべきかを明確にすることが大切
・宅建試験直前期の通信講座ならアガルートアカデミーがおすすめ
・宅建試験直前は慌てずに試験日の確認をする
2023年度の宅建試験は10月15日に行われます。
宅建試験直前期に新しいテキストの購入や細かいところまで網羅する勉強、またアウトプットに偏った勉強は控えましょう。
宅建試験直前期の正しい勉強法は苦手の克服や過去問、回答の順番を決めることや時間配分の確認、頻出項目を抑える他に通信講座を利用することが挙げられます。
通信講座の利用を考えている方は、合格率が全国平均の約3倍のアガルートアカデミーがおすすめです。
宅建の試験直前は迷いや不安が出るのは当然のことですが、何ヶ月も努力して勉強してきたのですから確実に力はついています。
直前期の追い込みも大事ですが、コツコツと積み重ねてきた日々が一番の強みなので、万全の準備を整えて自信を持って本試験に挑みましょう。