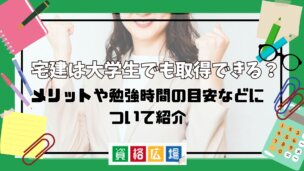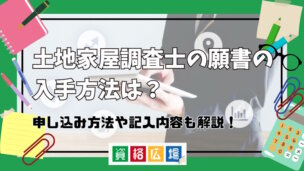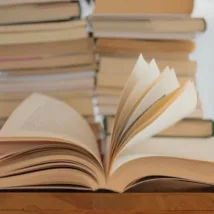不動産業界で非常に重要な責任を担っている土地家屋調査士は、近年では「需要が少ない」「将来性がないのでは?」と不安視されています。
そこでこの記事では、土地家屋調査士の現状や将来性について紹介します。
土地家屋調査士を志している方をはじめ、現在土地家屋調査士で将来が心配な方はぜひ参考にしてください。
土地家屋調査士講座ならアガルート!
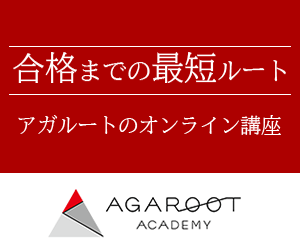
土地家屋調査士合格を目指すならアガルートアカデミーがおすすめです!
フルカラーテキストと動画講義で、初学者の方でも始めやすいカリキュラムです。
令和3年度の合格率は36.76%と全国平均の3.51倍だったり、一発受験での合格者全国一位など、多くの実績を出しています。
土地家屋調査士とは?

土地家屋調査士の概要は以下の通りです。
| 組織名称 | 日本土地家屋調査士会連合会 |
|---|---|
| 設立認可年月日 | 1950年(昭和25年)11月13日 |
| 管轄機関 | 法務省 |
| 扱う法律 |
基本六法 土地家屋調査士法 不動産登記法 上記に付随する判例、先例 |
| 独占業務 | 不動産の表示に関する登記 |
| 試験方式 | 筆記試験・口述試験 |
| 人数 |
土地家屋調査士:16,141名 土地家屋調査士法人:441法人 |
| 平均年収 | 500万~600万円 |
土地家屋調査士とは、土地や建物といった不動産を売買・取引する際に必要な「不動産の表題登記」を作成するプロフェッショナルです。
建物の構造や土地面積などの測量を行い、その不動産の所有者や用途などの情報を調査をしたうえで表題登記を作成することが土地家屋調査士の主な仕事です。
不動産鑑定士という一見似たような職業がありますが、土地家屋調査士は「不動産の測量や調査を行う」のに対して、不動産鑑定士は「不動産の鑑定を行い土地や建物などの価値を見出す」という点で大きく異なります。
需要が少ない?調査士の現状とは?

表題登記は土地家屋調査士のみが代行できる独占業務ですので、「土地家屋調査士の仕事がなくなる」「土地家屋調査士自体に需要がなくなる」ということはありません。
しかし時代や社会の変化に伴い、土地家屋調査士の働き方や役割というのも徐々に移り変わっており、近年では需要や求人が少なくなったのではないかと囁かれています。
その噂は本当かどうかを確かめるべく、調査士の現状について一緒に見ていきましょう。
土地家屋調査士の仕事が減少傾向に
土地家屋調査士に限りませんが、以前は国家資格保持者はその資格だけで一生食べていけるほど世の中に仕事が溢れていました。
しかし、バブル経済が崩壊し徐々に不景気になるに連れて、公共事業・不動産売買・土地取引などの数は大きく減少したのです。
そのため当然ながら土地家屋調査士の仕事や需要も減少し、全盛期では3,000万円ほどあった独立した土地家屋調査士の年収が近年では1,000万円程度に落ち込んできていると言われています。
他の業種に比べれば年収1,000万円は高い方ですが、単純に3分の1まで落ち込んだと考えると厳しい現状を伺うことができるでしょう。
加えて、近年では都市への人口集中・地方の過疎化・戸建ての減少などの社会情勢を受け、さらに活躍できる場が減ってきています。
土地家屋調査士の需要は決してなくなることはありませんが、現在では非常に厳しい立場に置かれています。
業務過多な土地家屋調査士もいる
不動産の調査は事前に地図や資料などを用いますが、測量は実際の現場に出向いて行うことになります。
夏の猛暑日や冬の寒空の下で測量を行うことも珍しくはなく、不動産の規模によっては測量に長時間かかることもあります。
このように肉体労働や長時間労働といった側面があってきついと判断されやすいことから、土地家屋調査士になりたいという人が少ないのです。
その結果、仕事が一部の土地家屋調査士に集中してしまい、業務過多となって苦労しているという現状もあります。
不動産関連のトラブルに巻き込まれることも
土地家屋調査士は職業柄、不動産関連の様々なトラブルに巻き込まれることもあり得ます。
例えば土地開発や宅地分譲のために測量を行って隣接地との境界線を引く際に、「隣家と境界線の認識が異なっている」「実は境界線が曖昧だった」というように紛争が生じることが考えられます。
そのため土地家屋調査士は登記申請・測量・図面作成といった基本的な業務に加えて、不動産関連の大きな訴訟にも携わることもあり、非常にハードな仕事内容となることがあるのです。
資格試験の合格率が低い
土地家屋調査士の試験は非常に難易度が高いことが特徴で、最近では4,000人ほどが受験しても合格者は400人程度と少なく、合格率は例年10%以下です。
ただでさえ試験が難しいことに加え、就職後に業務で必要となって資格取得を目指す受験生が多く、日々仕事をしながら試験勉強をしなくてはならないという苦境に立たされます。
そのため、効率のいい学習方法を提供して試験合格へ導いてくれて、かつ教室に通う必要がない通信制のスクールで学ぶとよいでしょう。
土地家屋調査士講座はアガルートアカデミーがおすすめ!
土地家屋調査士を目指すならアガルートアカデミーがおすすめです!
表題登記・筆界特定・測量といった専門的な知識・法律を覚えるのは難しいですが、フルカラーで見やすいテキスト教材と分かりやすい動画講義で、初めて資格勉強をする方でも充分合格が目指せるカリキュラムになっています。
初受験の方の合格率は28.46%と実績もあるので安心です。
合格者には受講費全額返金orお祝い金5万円の得点もあるのでモチベーションの維持も期待できます!
最短ルートで合格が目指せる!
アガルート公式HPはこちら
土地家屋調査士に将来性がある理由
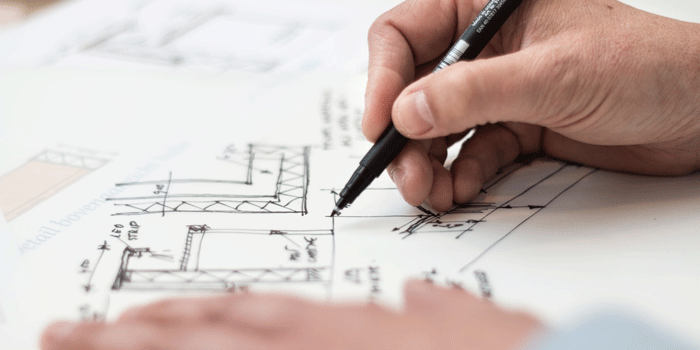
以上で紹介した通り、土地家屋調査士の現状は近年非常にシビアなものとなっています。
しかし、土地家屋調査士には将来性があり、今後も需要は伸びていくことが期待できます。
土地家屋調査士に将来性があると言える理由をご紹介します。
独占業務があるから
日本では建物を新しく建てたり増築工事を行ったりした場合には、「不動産の表題登記」を新たに申請する義務が不動産登記法で定められています。
この「不動産の表題登記」の業務は土地家屋調査士にしか行えない独占業務とされているため、大幅な法改正がされない限り土地家屋調査士の需要もなくなることはないでしょう。
今後日本で建物の開発がすぐになくなる見込みはないため、土地家屋調査士は将来性のある職業といえるのです。
高齢の土地家屋調査士が引退して需要が集まるから
現在、全国に土地家屋調査士は約16,000人ほどいますが、その内の4割以上が60歳以上です。
土地家屋調査士は30代でも新人とされるほど高齢者が多い業界であり、今後20年~30年も経つと現役の調査士は引退してかなり数が減ると考えられます。
また、少子高齢化に伴い土地の相続件数も増えるため、土地の測量業務や分筆(分割)・合筆・売却などの依頼も増えていくでしょう。
土地家屋調査士の数が減って相続件数が増えれば、必然的に一人当たりに舞い込む仕事も多くなるため、今後需要は上げやすくなると言えます。
ドローンを使ってキャリアアップできる可能性があるから
近年多くの業界で活用されている「ドローン」は、不動産の調査や測量の現場に置いても非常に活躍が期待されている技術です。
以前は従来の技法で不動産の調査や測量が行われてきましたが、ドローン技術の活用によって業務の簡略化・効率化が実現して土地家屋調査士の負担は減少してきています。
特に独立を考えている方、もしくはキャリアアップを目指している方はドローン操作の免許をとることによって作業の幅も広がり他社との差別化にもつながるので、将来性に期待できるでしょう。
AIに完全に代替される仕事ではないから
近い将来、書類作成の代行や測量の簡略化など一部の業務がAIに取って代わられるでしょう。
しかし、土地家屋調査士が行うすべての仕事がAIに代替されるということは無いです。
例えば土地の境界線を確認する「筆界特定」は隣の土地の所有者と協議する必要があり、筆界特定が難航して裁判が開かれるとなれば弁護士と協力して臨む可能性もあります。
このように土地家屋調査士は人を相手にして充分なコミュニケーションを取る業務があるので、「AIに完全に仕事を奪われるのでは」と心配しなくてよいでしょう。
今後も活躍できる土地家屋調査士の特徴

いくら土地家屋調査士に将来性があるといっても、常に業務内容やスキルをアップデートしないと需要がなくなってしまう恐れがあります。
今後も活躍すると期待できる土地家屋調査士の特徴を紹介しますので、参考にしてみてください。
最新の測量技術を習得する
科学技術は日進月歩で発展しており、測量技術も常に新しいものが登場しています。
例えばドローンの導入でより広範囲の土地を早く正確に測量できるようになり、3Dスキャナーを活用した製図技術では目視できない歩道の傾斜のデータも入手可能となりました。
最新のテクノロジーに常に対応できれば今までの測量方法と比べてグッと効率的になり、より多くの仕事をこなせるでしょう。
新しい制度に順応する
筆界特定は2005年に、裁判になる前に土地の所有者同士が話し合いによって解決を図る「ADR(裁判外紛争解決手続き)」は2006年に導入された制度です。
今よりも少子高齢化が進み相続件数が増えるとなると、必然的に土地の分割や売却の数も増えるので、不動産のトラブルの件数も増えると予想できます。
筆界特定やADRといった不動産トラブルに関連した制度の新設・改正が行われると見込めるため、最新の制度に順応できると業務の幅が広がるでしょう。
その地域の特性を学ぶ
測量は所有者の土地と行政が管理する道路との境目を見極めることが大切です。
ただし道路の扱い方は行政によって異なるので、その地域の特性を学んでいく必要があります。
しかも備えられている書類や確定するまでの手順も異なることがあり、その地域特有の土地の歴史に配慮しなければならない場合も考えられます。
地域の事情に精通していれば、スムーズに筆界特定や書類の準備ができるといったメリットがあるので、地域密着型の土地家屋調査士は需要が高くなるでしょう。
コミュニケーション能力を磨く
前述したように、土地家屋調査士には近隣の不動産所有者や弁護士などとコミュニケーションを取る能力が求められます。
ですから不動産所有者の意見をちゃんと汲み取ったり、弁護士に正しい情報を余すことなく伝達できたりするようにコミュニケーション能力を磨きましょう。
また司法書士や税理士など弁護士以外の士業とタッグを組んで仕事をすることも主流となってきたので、幅広い職種の人と交流が持てるように努めることもおすすめします。
ダブルライセンスを取得する
もっと不動産業界で幅広く活躍できるよう、ダブルライセンスを取得することもおすすめです。
複数の資格を持っていると同じ案件を一貫して受け持つことができ、希少な人材として価値が上がることで需要アップが見込めるでしょう。
例えば司法書士や行政書士は土地家屋調査士と業務内容が近しいため、比較的取得しやすい資格と言えます。
「土地家屋調査士だけで食べていけるか不安」「不動産業界でマルチに働きたい」とお考えでしたら、ダブルライセンス取得を目指すことをおすすめします!
土地家屋調査士の現状や将来性まとめ
今回は土地家屋調査士の現状をはじめ、需要や将来性について紹介しました。
実際のところバブル崩壊前に比べると土地家屋調査士の仕事は減ったと言われていますが、今後決して需要がなくなることは無く社会の中で大変大きな役割を担っています。
現在土地家屋調査士を目指している方は、キャリアアップにつなげるためにも最短で合格できるメソッドと高い実績を誇るアガルートアカデミーの通信講座を受講してみてはいかがでしょうか!