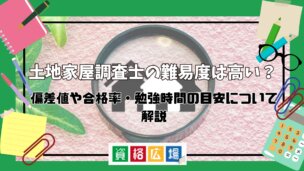宅建試験は、毎年合格点・合格ラインが変動します。
あらかじめ合格点が決まっている「絶対評価」ではなく、全受験生の得点次第で合否が決まる「相対評価」となっています。
宅建士試験は50点満点の試験で、合格点は「31~38点」にレンジで推移しています。
結果的に「1点で泣く」という受験生が多いため、本試験においては1点でも多く取る姿勢と意識が重要です。
こちらの記事では、宅建試験の合格点の推移や決め方、合格点が低い年度の試験難易度などを解説していきます。
これから宅建士試験を受ける方に役立つ内容となっているので、ぜひ最後までご覧ください。
宅建士講座ならアガルート!
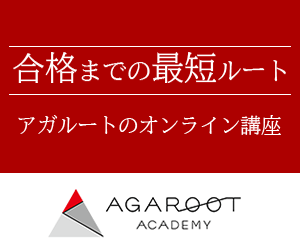
宅建士試験合格を目指すならアガルートアカデミーがおすすめです!
令和4年度は全国平均の3.50倍の59.5%と高い合格率が出ています。
通勤や家事の合間など隙間時間を活用して、効率的に学習を進めることができる講座です。
宅建試験の合格点・合格率の推移

| 年度 | 合格率 | 合格点 |
|---|---|---|
| 2013年 | 15.3% | 33点 |
| 2014年 | 17.5% | 32点 |
| 2015年 | 15.4% | 31点 |
| 2016年 | 15.4% | 35点 |
| 2017年 | 15.6% | 35点 |
| 2018年 | 15.6% | 37点 |
| 2019年 | 17.0% | 35点 |
| 2020年(10月) | 17.6% | 38点 |
| 2020年(12月) | 13.1% | 36点 |
| 2021年(10月) | 17.9% | 34点 |
| 2021年(12月) | 15.6% | 34点 |
| 2022年 | 17.0% | 36点 |
宅建試験は50点満点なので、「全体の7~8割程度の得点」が概ねの目安となります。
年度によって合格点に大きな差はないことから、目標が立てやすい試験と言えるでしょう。
ここ10年に関しては、合格率は15~18%、合格点は31~38点のレンジで推移していることから、「約6人に1人しか合格できない」難易度です。
2020年よりコロナウイルス感染症の影響で年に2度試験が実施されていましたが、2022年より例年通り年1度の開催に戻りました。
宅建試験の合格ラインの決め方は?

宅建試験の合格を目指している方にとって、例年の合格ラインの決め方については気になるポイントなのではないでしょうか。
以下より、宅建試験の合格ラインの決め方や特徴を解説していきます。
宅建試験はそもそも相対評価
行政書士試験やFP試験では、「○点以上の得点」などの合格基準点が決められていますが、
宅建試験は相対評価なので、明確な合格基準点が決められているわけではありません。
毎年の宅建試験の合格基準点は「35点前後」で推移していますが、その年の正確な合格基準点は受けてみるまで分かりません。
試験終了後に合格基準点が発表される
宅建試験は合格基準点が決められているのではなく、試験が終わった後に受験生全体の成績を鑑みた上で合格基準点が決められます。
試験問題が難しい年度であれば受験生全体の平均点も下がるため、合格基準点は低くなります。
一方で、試験問題が易しい場合は受験生全体の平均点が高くなるため、合格基準点も高くなる可能性が高いです。
合格者を多く出してしまうと、宅建資格の価値が落ちてしまう一方で、合格者が少なすぎると受験者が減ってしまう恐れがあります。
つまり、合格者数を適正に保つために、採点終了後に合格基準点を決定しているのです。
合格率を一定のレンジに収めるようにしている?
合格者数に加えて、合格率を一定のレンジに収めている可能性も高いです。
実際に、宅建試験の合格率は例年「15〜18%のレンジ」で推移しています。
試験の難易度を一定に保たないと、年度によって不公平感が出てしまうため、公平性を保つために調整されていると言われています。
宅建士試験講座ならアガルートアカデミーがおすすめ!
宅建士試験合格を目指すならアガルートアカデミーがおすすめです!
フルカラーで見やすいテキスト教材と分かりやすい動画講義で、初めて資格勉強をする方でも充分合格が目指せるカリキュラムになっています。
合格者には受講費全額返金orお祝い金1万円の特典もあるのでモチベーションの維持も期待できます!
最短ルートで合格が目指せる!
アガルート公式HPはこちら
合格点はどのように決まる?

相対評価で合格点が決まる宅建士試験ですが、合格点が相対評価でどのように決まるか気になりますよね。
例えば2018年の宅建試験の合格基準点は「37点」で比較的高いですが、合格率は15.6%と、そこまで高いわけではありません。
逆に、2014年の宅建試験の合格基準点は「32点」で比較的低いですが、合格率は17.5%とやや高めの結果です。
以下より、過去のデータから毎年の宅建士試験の合格点がどのように決まっているのか解説します。
合格点が低い年は試験問題が難しい傾向
合格点と合格率には明確な相関性があるかはわかりませんが、試験問題の難易度は合格点に大きく影響します。
試験問題が易しければ全受験生の得点は伸びますが、合格基準点は高くなる(厳しくなる)ため、合格率が大きく跳ね上がることはありません。
逆に例年より試験が難化した場合、合格点は下がると考えられます。
実際に本試験を受けている最中に「今年の問題は難しいだろうから、合格基準点も低いだろう」と考える余裕はありませんが、諦めることなくベストを尽くすことが重要です。
宅建試験に合格するためのコツ

続いて、宅建試験に合格するためのコツをご紹介します。
宅建士試験は合格率が15~18%程度の難関試験ではありますが、しっかりと勉強すれば誰でも合格を狙うことが可能です。
宅建試験で効率よく得点するためのコツはいくつかあるため、得点が伸びずに悩んでいる方は参考にしてみてください。
宅建業法と法令上の制限を得点源にする
- 権利関係:14問前後
- 宅建業法:20問前後
- 法令上の制限8問前後
- 税・その他:8問前後
中でも、「宅建業法」と「法令上の制限」は暗記しているだけで解ける問題が多いため、得点しやすい特徴があります。
特に、宅建業法の出題数は20問前後と多く、宅建試験における最重要科目です。
宅建業法と法令上の制限は問題の難易度も低いため、インプットとアウトプットの量をこなせば自然と得点源にできるでしょう。
実際に、宅建業法と法令上の制限は判断に迷うような引っかけ問題も少ない(出題側も出しづらい)ことから、「とにかく勉強量をこなす」ことで自然と得点力を高めることができます。
権利関係は理屈を理解する
権利関係の科目では、民法上のルールに関する問題が中心に出題されます。
具体的には、不動産売買における権利関係や詐欺、脅迫、錯誤などの場合における権利変動のルールが出題内容となっています。
宅建業法と法令上の制限とは異なり、権利関係は暗記だけで対応するのは難しい科目なので、権利関係に関しては「条文を読んで理屈を理解する」ことを意識することが効果的な対策です。
権利関係は毎年14問前後が出題される重要科目ではありますが、学ぶ内容が難解なので「本質的な部分」を理解できないと得点するのは難しいです。
また、権利関係は勉強範囲が広い特徴があり、宅建士試験で最も難易度が高い科目と言えます。
特に、法律に関する勉強が初めての方にとって、権利関係は鬼門となるため、じっくりと時間を割いて勉強することが大切です。
権利関係で10問以上の得点ができれば十分ですが、もし苦手意識が拭えない方は「半分の7点以上」を目標にすると良いでしょう。
過去問を有効活用する
宅建試験は過去問の焼き直しや類似問題が多く出題されるため、過去問演習をこなすことで得点力アップに繋がります。
- 宅建業法と法令上の制限は完璧を目指す
- 権利関係はインプットとアウトプットを繰り返す
上記のポイントを意識すれば、着実に得点力は伸びていくでしょう。
インプットをしただけでは理解できなかった箇所も、実際に問題を解いて解説を読むことで理解できるケースは多いです。
「過去問5年分3周」を目安にして、できるだけ多くの問題演習に取り組むことを意識してみてください。
余裕があれば模擬試験や予想問題を解く
同じ過去問を解いていると、解答を覚えてしまい勉強がマンネリ化してしまうことがあります。
そこでおすすめなのが、模試や予想問題の活用です。
模試や予想問題は、いわゆる「初見の問題」なので、自分の今の学力を試すことができる優良な学習教材です。
本試験で解く問題はいずれも初見ですから、本番前に初見問題に取り組んで「自分が何点採れるのか」を把握することは非常に有効です。
もしうろ覚えの箇所や理解不足の箇所が見つかった場合は、本番前に対策して万全の状態に仕上げることを目標にしましょう。
普段の演習では40点を目指す
過去の試験データを見ても、40点以上取れれば安全圏と言えるため、普段の演習では40点の獲得を目標にすると良いでしょう。
宅建試験は相対試験なので、合格基準点が発表されるまで自分が合格できたかどうか分かりません。
つまり、同じ35点でも「去年の基準であれば合格できたのに、今年は合格できなかった」という事態が起こる可能性はあるため、合格基準スレスレを狙うのは危険です。
宅建試験では「1点に泣く受験生」が非常に多いため、日頃から高いレベルを目指して勉強する意識を持ちましょう。
ある程度の苦手は許容する
宅建試験には、他の資格試験のような「科目ごと」の合格点(足切り基準)はありません。
そのため、「どれだけ勉強しても理解できない超苦手箇所」がある場合は、捨ててしまっても大丈夫です。
苦手分野が多すぎるのは問題ですが、限られた勉強時間を使って効率よく得点力を伸ばすためには、ある程度の苦手を許容することも大切です。
完璧を求める余り、重要な箇所の対策がおろそかになってしまうのは本末転倒なので、非効率な勉強をしないように意識してみてください。
予備校や通信講座を利用する
宅建試験は、合格率が15~18%程度の難関試験です。
独学での合格は不可能ではありませんが、「独学だと不安がある」という方は躊躇なく予備校や通信講座を利用すると良いでしょう。
予備校や通信講座には、分かりやすく教えてくれる講師がいる上に、市販の教材よりも理解しやすい教材で勉強できるメリットがあります。
また、多くの講座では不明点や疑問点があるときに質問できるサポートを備えているため、独学よりも効率よく勉強できるでしょう。
- 少しでも合格できる可能性を高めたい
- 独学だと不安がある
- 絶対に今年の試験で合格したい
宅建試験の合格点の推移|まとめ
宅建試験の合格点は、ここ10年「31~38点」で推移しています。
試験が難しい年度は合格点も低い特徴がありますが、試験が終わってみないと合格点が分からない、という点が厄介なポイントです。
日頃の勉強では40点を目指しつつ、本試験では1点でも多く取る意識を持って勉強すれば合格できる可能性が高まります。
こちらの記事でご紹介した合格点の決まり方や合格するためのコツを参考にしながら、宅建士試験の合格を目指してみてください。