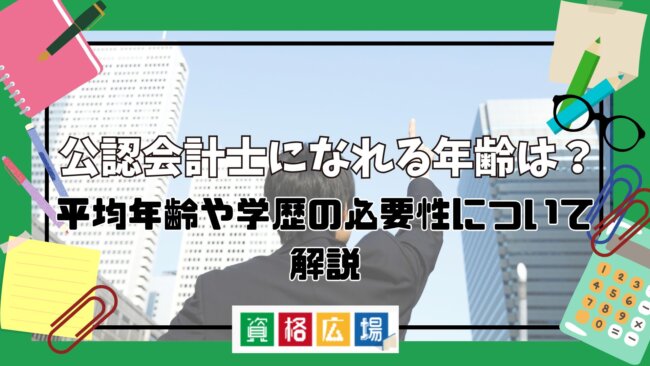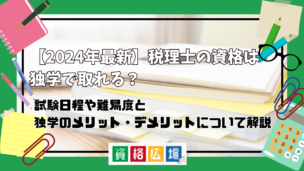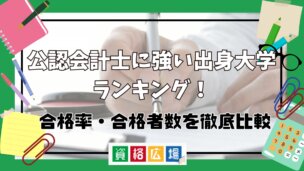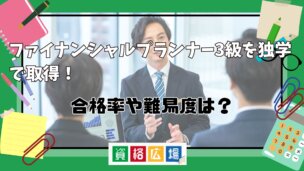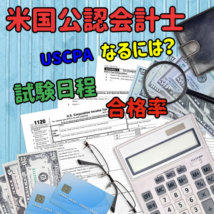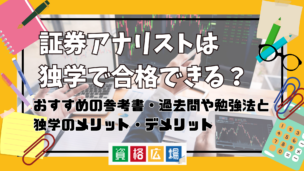企業が決算書類を作成したり会計処理を行う場合、書類に間違いがないかを細かくチェックして証明するのが”公認会計士”の仕事です。
公認会計士になれる年齢や、必要な学歴、有利な条件などはあるのでしょうか?
ここでは、公認会計士になれる年齢や、就職先などについて詳しく紹介していきます。
公認会計士を目指している方は参考にしてみて下さい。
公認会計士とは?

公認会計士とは、会計および税務に関する高度な専門知識と技術を有し、企業や個人の財務諸表の監査や税務相談を行うことができる国家資格を指します
公認会計士は「各企業の財務情報の信頼性を保証する」という重要な社会的責任を担っています。
多様化した企業活動により企業が公開する財務情報に誤りや隠蔽の兆候があれば、投資家や金融機関、消費者、取引先など、すべての利害関係者はその企業に対して適切な評価を行うことができません。
このような状況では、利害関係者が不利益を被るだけでなく、経済システム全体が正常に機能しなくなる危険性もあります。
したがって、社会経済システムが円滑に機能し、人々が安心して経済活動を行うために、公認会計士の役割が重要となります。
会計士と比較されることが多いですが、公認会計士との違いは名簿への登録の有無に過ぎず、会計士は基本的に誰でも名乗ることができます。
業務内容は公認会計士と会計士でほとんど同じであるため、基本的には大きな違いは存在しません。
公認会計士になれる平均年齢は?
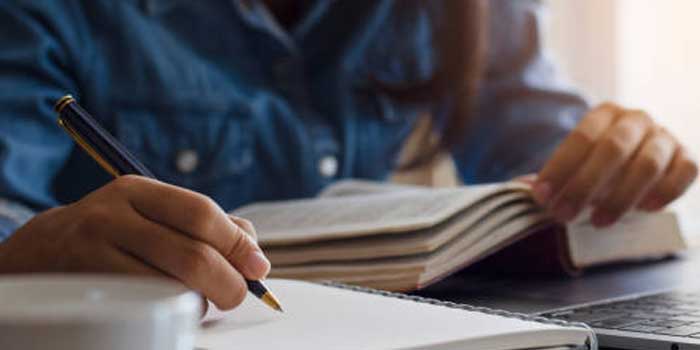
公認会計士として就職し、活躍している人の年代は様々です。
就職のために大学生や大学院生が資格の取得を目指したり、まだ若い年齢の人も公認会計士に転職することがあります。
公認会計士になるためには国家試験に合格する必要がありますが受験資格はないため、公認会計になれる年齢に制限はなく、何歳でも公認会計士になることができます。
では、就職するにあたって適齢期とされる年齢はあるのでしょうか?
公務員試験の合格者の年齢や適齢期を紹介します。
合格者の平均年齢は?
公認会計士の合格者の平均年齢は2021年度試験では24.5歳となっています。
大学在学中から公認会計士を目指す方が多く、合格者の平均年齢は比較的低めとなっています。
平均受験年齢自体は、20代後半となっていますが、30~40代の方でも仕事をしながら合格を目指す方も多くいます。
次に年別の合格者数について見ていきます。
年代別の公認会計士の人数は?
平成三十年度の時点の公認会計士の合格者を年代別でまとめてみました!
以下が、20未満から60未満での合格者数となっています。
| 年代 | 人数 |
|---|---|
| 20歳未満 | 21人 |
| 20~25歳未満 | 782人 |
| 25~30歳未満 | 295人 |
| 30~35歳未満 | 123人 |
| 35~40歳未満 | 345人 |
| 40~45歳未満 | 19人 |
| 45~50歳未満 | 6人 |
| 50~55歳未満 | 6人 |
| 55~60歳未満 | 2人 |
上記を見て分かるように、20代が最も合格者数が多くなっています。
しかし、30,40代以上の方も合格者はいるので、特に年齢が関係ないことが分かりますね。
年齢が若い方が有利?
公認会計士試験の受験者の多くが若い世代である理由は、資格を取得するための道のりが高いことも挙げられます。
公認会計士の試験は筆記試験ですが、これに合格すればすぐさま資格をもらえるわけではないのです。
合格後は、会計を専門とする企業や監査法人において2年間以上の「業務補助経験」と3年間の補習所通学を行う必要があります。
その実績を積んだら、補習所で所定の単位を取得した後に受けられる、年に一度の「修了考査」という筆記試験を受験し、合格しなければなりません。
「修了考査」の試験をパスできた人だけが、公認会計士として登録されるのです。
ここに辿り着くまで、実に3年から5年の月日はかかることが予想されます。こういった経緯があることから、受験者は若い世代が多いのです。
過去の経験が活かせる場合もある
また、公認会計士を採用するにあたっても、企業側や監査法人としては体力的な面や組織への馴染みやすさという理由で、比較的年齢が若い人材を求めている場合が多いです。
ですが、必ずしも年齢が高いから就職できないわけではありません。
公認会計士として就職する前に、会計や経営戦略の業務を行っていたという人も、その経験を活かして働ける可能性があります。
そういった点では、経験者は知識がある分だけ有利と言えるかもしれませんね。
年齢が低い方が有利なように見えるかもしれませんが、最終的にはいかに仕事ができるかで力を証明できます。
公認会計士になる上で有利な学歴はある?

公認会計士になる上で学歴は関係あるのでしょうか?
結論から言えば、公認会計士に学歴は関係ありません。
公認会計士の合格者の学歴を見てみると、大卒、短大卒、高卒など様々な学歴があり、学歴が良いからといって有利ではないことがわかります。
公認会計士において学歴は関係ないので、学歴がないからという理由で諦める必要はありません。
就職に学歴は関係ある?
公認会計士になる上で、学歴は関係ないと説明しましたが就職ではどうなのでしょうか?
就職においても学歴によって左右されない傾向にあります。
公認会計士は慢性的に人手不足であり、資格を保持している人間は非常に重宝されます。
公認会計士は資格を得る上でも、就職でも学歴は関係ありません。
公認会計士の就職先は?

無事に国家試験に合格できたら、次は公認会計士として就職できるところを探します。
公認会計士は、どのようなところに就職しているのでしょうか?
主な就職先は『監査法人』
公認会計士の主な就職先は、『監査法人』と呼ばれているところです。
『監査法人』とは、様々な団体や企業において、第三者の立場で監査を担当します。
監査法人は、ほとんどの顧客が大きな企業となっているため、多くの公認会計士は都市部に就職している傾向があります。
監査法人の中でも1,000人以上が監査を行い、上場会社を100社以上監査している監査法人を“4大監査法人”や“BIG4”と呼び、『新日本有限責任監査法人』『あらた監査法人』『有限責任あずさ監査法人』『有限責任監査法人トーマツ』がそれに当ります。
4大監査法人は規模や実績、クライアント数が優秀で公認会計士にとって人気が高くなっていますが、公認会計士として就職する際には様々な観点から自分にあったところをしっかり分析したうえで選びましょう。
コンサルティング会社
公認会計士の就職先としてコンサルティング会社もあります。
コンサルティングには様々な分野がありますが、会計分野のコンサル業務で多くの公認会計士が活躍しています。
また、監査法人の時に経験を積んでいればその経験を活かして、会計以外のコンサルティングも行うことができます。
独立する際の年齢は?
公認会計士は独立することができる国家資格となっていますが、独立する際の年齢はどのくらいが良いでしょうか?
結論から言えば、独立する際の年齢は何歳でも良いと言われています。
クライアントやある程度の資金や人脈を確保できていれば独立に年齢は関係なく、独立・開業して活動することができます。
公認会計士になれる年齢は?平均年齢や学歴の必要性について解説
公認会計士の試験概要は?

国家資格である公認会計士になるための試験は、とても難易度が高いことで知られています。
公認会計士として就職を希望する場合は必ず合格しなければならない試験ですが、受験資格などはあるのでしょうか?
受験資格はなし!
公認会計士の試験は、受験資格として年齢制限もなく、必要な学歴、資格などは問われず、誰でも受験することができる試験です。
過去の受験者では、16歳の合格者を出したこともあります。
そのため、公認会計士は最低年齢が無く、どの年齢でもなることができます。
受験者の年齢も20代から30代が大半を占めていますが、未成年から60歳近い方まで様々な年齢層が存在します。
年齢の低い合格者がいるとなると、試験そのものが簡単なのではないかと思うかもしれません。
しかし、繰り返しますが公認会計士は国家資格であり、難易度も司法試験に次いで難しいとされています。
合格のための試験勉強は怠れませんね。
公認会計士の合格率は?
公認会計士は難易度の高い資格となっていますが、合格率はどのくらいなのでしょうか?
公認会計士の試験の合格率について見ていきます。
| 年度 | 実施回 | 合格率 | 実質合格率 |
|---|---|---|---|
| 令和2年 | 第一回 | 12.1% | 15.7% |
| 第二回 | 9.7% | 12.9% | |
| 令和3年 | 第一回 | 16.8% | 21.6% |
| 令和4年 | 第一回 | 9.4% | 12.1% |
| 第二回 | 6.1% | 7.9% |
合格率が2種類ありますが、合格率には欠席者も含まれており、実質合格率が実際に受験した人を基に産算出した数字なので、実質合格率を参考にして下さい。
このように見てみると合格率は年によってバラつきが多くなっていますが、基本的に低いことがわかりますね。
やはり、公認会計士の試験は難易度が高くなっているようです。
年齢別!公認会計士のキャリアパス
公認会計士は20代から目指す人が多いことがわかりました。
そこでここでは、年齢別に公認会計士のキャリアプランについて紹介します。
20代公認会計士の場合
公認会計士の合格者の大多数は20代に集中しています。
20代で公認会計士の資格を取得した多くの人々は、監査法人に就職し、大手監査法人などで実務経験を積むことが一般的です。
将来的には独立を視野に入れている方もいるでしょう。 公認会計士に対する需要は非常に高く、20代の公認会計士や受験者向けの求人情報も豊富にあります。
なかには一部の監査法人では、勤務しながら公認会計士の資格取得を目指す制度を導入しているところもあります。
資格を支援してくれる企業に就職することで実務経験を積みながら資格取得に向けた学習を行うことが可能です。
転職市場においては20代の特性を活かしたポテンシャル採用が行われているため、積極的に転職活動を進めることをお勧めいたします。
30代公認会計士の場合
30代は、公認会計士として監査法人でのキャリアを継続する人と、一般事業会社への転職や独立を選択する人とに大きく分かれます。
現在、公認会計士は売り手市場が続いており、30代で資格を取得した場合でも、就職先を見つけやすいでしょう。
監査法人や一般事業会社でその資格を活かすことが可能です。 ただし、就職活動においては、前職での経験をどのように公認会計士として活用するかを明確にアピールすることが重要です。
また30代の公認会計士が転職を目指す際には、監査関連の実務経験に加え、M&Aやコーポレートファイナンス、コンサルティングの経験があると有利です。
ほかにも英語力に自信がある人材は特に重宝され、転職成功の大きなアピールポイントとなります。
40代公認会計士の場合
定年までの勤務を前提とした場合、40代はキャリアの重要な転換点と位置付けられます。
40代の公認会計士ともなるとこれまでのキャリアをどのように活用するかを再評価する人が増え、管理職としての役割を求められることも多くなります。
また、40代で公認会計士試験に合格し、新たに公認会計士としてのキャリアを築こうとする場合は過去の経験と公認会計士としてのスキルの両方を活かせる職場を選ぶことが望ましいです。
さらに、40代の公認会計士においてはマネージャーや管理職レベルのポジションに対する需要が比較的高く、反対に一般的な監査業務を行う人材としての採用は難しい傾向にあります。
なお、40代の公認会計士の年収は1,000万円から2,000万円程度であり、勤務先や役職によっても変わってきます。
一般的に監査法人は年収が高いため、監査法人から一般企業に転職する際には年収が減少するリスクがあるので注意が必要です。
50代以降の公認会計士の場合
50代以上の公認会計士は監査法人内で一定の地位を占めていることが多く、独立している場合にはクライアントの数が安定している世代です。
管理職としての役割が求められることが多く、未経験者が50代で新たに公認会計士として監査法人に入るのは難しいと言えます。
50代以上での転職においてはこれまでに専門的な業務を遂行し、多様な実績を積んでいるかどうかが重要な要素となります。
監査法人に固執せず、これまでの業界経験を基に事業会社で公認会計士としての知識と経験を活かすこともひとつです。
グローバルに活躍したいならUSCPA(米国公認会計士)もおすすめ
USCPAはアメリカの公認会計士資格を指し、日本を含む多くの国で受験できる国際的に広く認知されているビジネス資格です。
USCPAを取得することで、監査法人やコンサルティングファームへの就職や転職が有利になります。
試験はすべて英語で実施されるため、資格取得後は英語での監査業務を行えることをアピールでき、 国際的な業務に従事できるため、キャリアの選択肢が広がる点も大きな魅力です。
さらに、追加の研修を受けることで、USCPAの国際相互承認協定を結んでいるオーストラリア、カナダ、メキシコなどの国々で、現地の会計士と同様の業務を行うことが可能になります。
グローバルなキャリアを目指す方は、USCPA資格の取得を目指してみて下さい。
公認会計士の合格を目指すならCPA会計学院

年齢も関係なく、独立することができる公認会計士は魅力的ですが、難易度の高い資格となっています。
独学での学習が不安や、苦手な方は通信講座を利用してみてはいかがでしょうか?
CPA会計学院は、徹底的なサポートや合格率が特徴の通信講座となっています。
CPA会計学院の特徴
- 上位合格者多数輩出!
- 働きながら合格を目指すことができる!
- 合格者占有率が41.6%!
合格実績が優秀なCPA会計学院
CPA会計学院は主に公認会計士を中心とした通信講座となっており、これまで培ってきた経験を基に多くの合格者を輩出しています。
令和4年度の公認会計士試験では、CPA会計学院の受講生が606名合格しました。
公認会計士の全体の合格者は1,456名で、CPA会計学院では606名が合格したので、合格占有率が41.6%と、合格者の多くがCPA会計学院で学んだことになります。
また、CPA会計学院では全国1、2、4位で合格する受講生も輩出しています。
公認会計士になれる年齢や学歴|まとめ
公認会計士の試験は、司法試験に継いで難関だとされており、合格するためにはかなりの努力が必要になります。
過去には若い年齢での合格者も出していますが、その後、2年以上の「業務補助経験」を積み、それから年に一度の「修了考査」の試験に合格し、やっと公認会計士として登録される大変な職業です。
受験資格はとくにありませんが、公認会計士として無事に登録されるまでに3年から5年という長い時間がかかるため、若いうちから取得に励む世代が多いことは事実です。
CPA会計学院のような合格実績が優秀な通信講座を利用して、短期間で合格を目指すことをおすすめします。