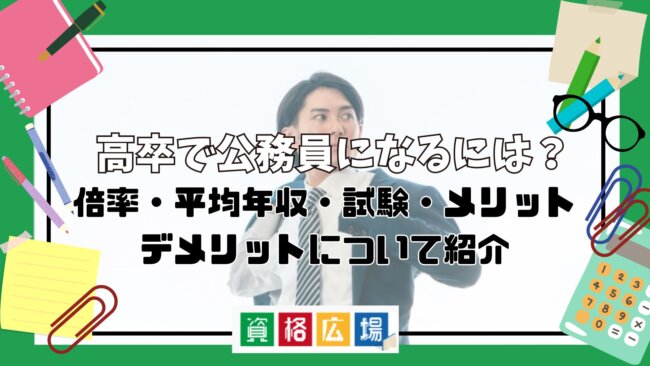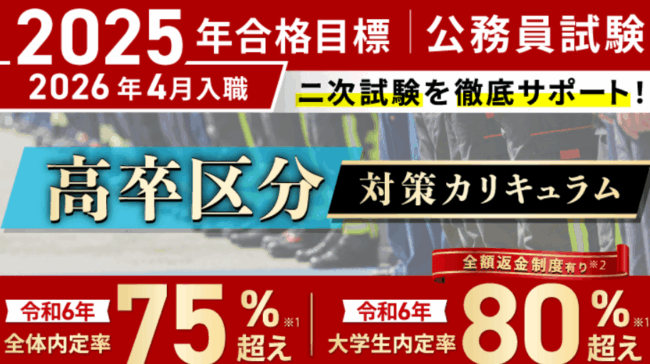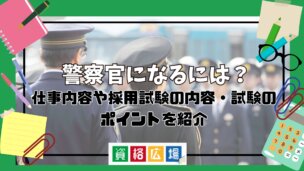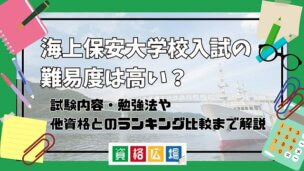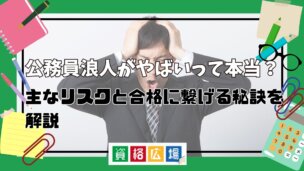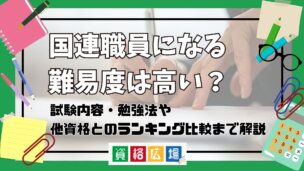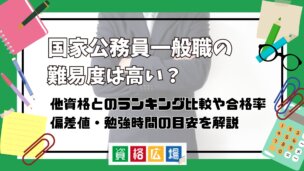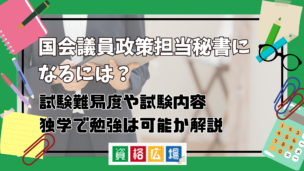安定した収入と充実の福利厚生によって、公務員の仕事に就きたい人はたくさんいます。
しかしなかには、「高卒でも公務員になれるの?」と学歴を理由に不安を感じる人もいるでしょう。
結論から言うと、公務員試験は学歴不問であることから、高卒や大学中退者でも公務員にはなれます。
そこで今回は高卒から公務員になる方法やメリット・デメリット・試験内容について解説していきます。
高卒でも公務員試験は受けられる
先にも述べたように高卒でも公務員は目指せます。
公務員試験には高卒者を対象にした枠があり、大学に進学せずに実際に公務員を目指す人もたくさんいます。
むしろ高卒という若さをアドバンテージにして、早めに公務員になり現場で経験を積み、スキルアップできるといったメリットもあります。
高卒から公務員になるには公務員試験をに合格する必要があり、大卒の場合と基本的な流れは同じですが試験内容は異なり高卒レベルとなっているので安心です。
もしこれから公務員試験にチャレンジする方は高卒から公務員を目指した人の話を聞いたり、高卒で合格した人のアドバイス本を読むなどでイメージを膨らませておくといいでしょう。
高卒から目指せる公務員の種類・職種
ひとえに公務員と言ってもさまざまな種類の職種があります。
ここでは、高卒から目指せる種類について国家公務員・地方公務員別に紹介していきます。
国家公務員
国家公務員とはおもに官公庁で働く公務員を指し、高卒からでも国家公務員として働くことができます。
高卒からなれる国家公務員の種類には以下のものが挙げられます。
- 国家公務員一般職
- 税務職員
- 裁判所億院一般職
- 刑務官
- 皇宮護衛官
- 防衛大学校
国家公務員一般職に関しては、省庁がそれぞれ採用を実施しています。
厚生労働省や文部科学省などの試験を受けて合格して各省庁に務める公務員として働く流れです。
ただし国家公務員は地方公務員よりも異動の範囲が広く、転勤の対象となるケースもがあるため注意が必要です。
地方公務員
地方公務員とは、地方自治体で採用している公務員のことです。
高卒からなれる地方公務員の種類には以下のものが挙げられます。
- 都道府県庁
- 市区町村役場
- 警察官
- 消防士
行政の仕事全般を請け負う事務職(行政職)や専門分野に特化した技術職なども高卒からでも目指せる職種となります。
技術職では土木や電気など、特定の領域に精通したスキルが求められます。専門性の高い分野であるため需要が高く、就職後には多くのやりがいを実感できるでしょう。
地方公務員は自治体内での異動はあるものの、全国を対象にした転勤がないので、決まったところで働き続けたい方にはおすすめです。
高卒程度区分の倍率はどれくらい?
先にも述べたように高卒で公務員を目指す場合、高卒程度区分での受験となります。
ここでは、高卒程度区分の倍率についてみていきます。
高卒程度区分の国家公務員一般職の倍率
| 年度 | 受験者数 | 一次合格者 | 最終合格者 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|
| 令和6年 | 6,990名 | 3,404名 | 2,379名 | 2.9倍 |
| 令和5年 | 7,046名 | 3,492名 | 2,538名 | 2.7倍 |
| 令和4年 | 8,061名 | 3,229名 | 2,341名 | 3.4倍 |
上記の表からも分かるように、国家公務員一般職(高卒程度区分)の倍率は約3倍程度で推移しています。
大卒区分も令和6年度の倍率は2.7倍程度であることから、そこまで変わらないと言えるでしょう。
ただし国家公務員一般職(高卒者試験)の採用は地域ごとに行われ、倍率が異なるため注意が必要です。
以下は令和6年度の事務職・技術職の倍率を地域ごとにまとめたものとなります。
| 地域 | 受験者数 | 一次合格者 | 最終合格者 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|
| 北海道(事務) | 466名 | 396名 | 240名 | 1.9倍 |
| 北海道(技術) | 74名 | 37名 | 34名 | 2.2倍 |
| 東北(事務) | 762名 | 223名 | 174名 | 4.4倍 |
| 東北(技術) | 157名 | 84名 | 74名 | 2.1倍 |
| 関東甲信越(事務) | 3,151名 | 1,767名 | 1,260名 | 2.5倍 |
| 関東甲信越(技術) | 203名 | 100名 | 79名 | 2.6倍 |
| 東海北陸(事務) | 438名 | 237名 | 157名 | 2.8倍 |
| 東海北陸(技術) | 87名 | 63名 | 55名 | 1.6倍 |
| 近畿(事務) | 347名 | 230名 | 170名 | 2.0倍 |
| 近畿(技術) | 61名 | 42名 | 39名 | 1.6倍 |
| 中国(事務) | 331名 | 168名 | 112名 | 3.0倍 |
| 中国(技術) | 51名 | 20名 | 17名 | 3.0倍 |
| 四国(事務) | 150名 | 80名 | 53名 | 2.8倍 |
| 四国(技術) | 37名 | 28名 | 24名 | 1.5倍 |
| 九州(事務) | 985名 | 219名 | 159名 | 6.2倍 |
| 九州(技術) | 328名 | 233名 | 192名 | 1.7倍 |
| 沖縄(事務) | 360名 | 84名 | 54名 | 6.7倍 |
| 沖縄(技術) | 9名 | 3名 | 2名 | 4.5倍 |
高卒の公務員の初任給は15万~18万円程度
人事院の「令和5年度国家公務員給与等実態調査」によれば、高校卒業者の公務員初任給は地方公務員で154,067円、国家公務員で180,720円となっています。
一方大卒の場合、地方公務員は187,623円、国家公務員は222,240円となっています。
一般的に大学卒業者の方が高卒者よりも初任給が高く、国家公務員の初任給は地方公務員よりも高い傾向が見られます。
高卒者は給料が他の職業と比較して低い水準になることが予想されるため、就職後の生活設計を行う際にはその点を考慮する必要があるでしょう。
高卒で公務員を目指すメリット
ここでは、高卒で公務員を目指すメリットについて紹介します。
メリット1】競争率が低い
高卒程度の採用試験は、大卒程度に比べて合格するのがしやすいといったメリットがあります。
高卒の筆記試験は主に教養試験のみで構成されることが多いですが、大卒試験では教養試験に加え専門試験が課されます。
そのため、対策が必要な範囲が狭く、問題の難易度も大卒程度より低いため、試験対策の負担を減らせます。
また、高校での学業が得意な学生は大学進学を目指すことが多いことから、受験者のレベルが大卒程度よりも低くなる可能性が高いのもハードが低い理由として挙げられます。
もちろん、採用者数や倍率によっても異なりますが、高卒で公務員試験を受けることで合格しやすいのは否めないでしょう。
メリット2】早くから社会人経験を積める
高卒から公務員を目指す際のメリットのひとつには、大卒よりも早くから社会事件経験を積める点が挙げられます。
大卒よりも4年という若いうちから実践的な知識や技術を習得することで、早くから職場に貢献できる人材となる可能性が高まります。
また、公務員の職務は基本的に高卒と大卒で差がないため、できることが増えれば業務に対するやりがいも感じやすくなります。
公務員の仕事に興味がある方や少しでも早く仕事に慣れたいと考える方は高卒からチャレンジしてみるのもひとつです。
メリット3】大学進学にかかる学費がかからない
高卒で公務員になれば大学や短期大学の費用を支払う必要はありません。
例えば私立大学の文系学部に通うとなると、学費だけでも4年間で400万円程度、理系や医学部などであれば1,000万円以上かかることもあります。
中には奨学金を借りて大学に通う方も少なくありません。
しかし高卒で公務員になれば大学進学の費用はかりません。
また生涯賃金は大卒の職員と比べても大きく変わらないため、単純に給料を得て稼げるようになる点は魅力です。
以上のことから大学進学を特に考えていない方にとって公務員は、経済面で大きなメリットがあります。
高卒で公務員を目指すデメリット
ここでは、高卒で公務員を目指すデメリットについて紹介します。
デメリット1】キャリアアップしにくい面がある
高卒で公務員になった場合、キャリアアップしにくいといった面があります。
公務員のキャリアアップとして大卒が昇進の条件となることもあり、一定の役職に就けない場合も考えられます。
そのため、具体的に希望する職務や目指す役職があっても、高卒であることを理由に諦めなければいけないケースも。
もし就きたい職種が明確である場合、高卒か大卒かどのような条件で募集しているのかを見ておくといいでしょう。
デメリット2】公務員以外のスキルが身につかない
高卒で就職した場合、公務員以外のスキルを習得できないリスクがあります。
公務員は一般企業とは異なり、その職場で必要とされるスキルが限られていることが多いため異業種への転職がしづらくなるおそれがあります。
また、高卒という学歴が転職先を制限する要因となることも懸念されます。
将来的に公務員以外の職業に就く可能性が少しでもあるのであれば、大学に進学するなど、一般的な学歴や知識・技術を身につけるのもひとつです。
公務員試験に年齢制限はある?地方公務員・国家公務員・試験種別に紹介
国家一般職(高卒)の試験について
ここでは、令和7年度の国家公務員採用一般職試験(高卒者試験)の日程を参考に紹介します。
| 受付期間 | 6月13日~6月25日 |
|---|---|
| 第1次試験日 | 9月7日 |
| 第1次試験合格者発表日 | 10月9日 |
| 第2次試験日 | 10月15日~10月24日 |
| 最終合格者発表日 | 11月18日 |
参照:国家公務員採用一般職試験(高卒者試験)|国家公務員試験採用情報NAVI
例年であれば、試験日程はほぼ変動せず、1次試験は例年9月第1日曜日に実施されています。
1次試験について
国家一般職(高卒)の一次試験では、基礎能力試験、適性試験、作文試験が行われます(理系の試験区分では、さらに専門択一試験も実施)。
基礎能力試験は一般的に教養択一試験と呼ばれ、高校で学ぶ内容に加えた範囲について五肢択一形式のマークシート試験が行われます。
- 知能分野20題 文章理解⑦、課題処理⑦、数的処理④、資料解釈②
- 知識分野20題 自然科学⑤、人文科学⑨、社会科学⑥
課題処理とは判断推理を指し、非言語分野として空間把握も含まれます。
また適性試験は事務処理能力を測定するもので知識は必要ありませんが、配点割合が設定されているので最終合格に影響を与えるため対策が必要です。
作文試験は「文章による表現力や課題に対する理解力」を測る論述試験であり、自分の意見を述べる形式のものなので過去問を解くなどしておくといいでしょう。
2次試験について
国家一般職(高卒)の2次試験では個別面接による人物試験が行われます。
面接は特定の省庁の選考ではないため基本的には国家公務員としての自己アピールについて聞かれることが多いためあらかじめ用意しておきましょう。
なお、採用面接(官庁訪問)は、2次試験の前後に実施されるのが一般的で官庁訪問で内定を得た場合でも2次試験に不合格となると採用されないため注意が必要です。
地方初級公務員(高卒)の試験について
地方初級公務員試験(高卒)日程の例年の一般的な流れは以下の通りとなります。
しかし自治体によって異なるため、自分が受験する自治体のホームページをチェックするようにしましょう。
| 項目 | 時期 |
|---|---|
| 試験案内配布 | 5~8月頃 |
| 出願受付期間 | 7~8月頃 |
| 一次試験 | 9月下旬 |
| 一次試験 合格発表 | 10月上旬~10月中旬 |
| 二次試験 | 10月中旬~10月下旬 |
| 最終合格発表 | 11月上旬~11月下旬 |
早い自治体では5月頃から試験案内の配布が始まるため、自治体のホームページをこまめに確認するようにしましょう。
出願から最終合格発表までの期間は約4か月程度なので、日程を把握したら併願の検討を進めてください。
たとえば東京都と特別区(23区)では例年9月上旬に、政令指定都市以外の多くの市役所では9月中旬または10月中旬に一次試験が行われます。
公務員試験では複数の自治体への併願が基本であり、併願を行うことで本命試験の予行練習ができるほか、受験の機会が増えるため合格率をあげることにもつながります。
1次試験
地方初級公務員試験(高卒)の1次試験ではほとんど全ての自治体で筆記形式の教養試験が行われます。
また、なかには一部の自治体では一次試験に適性試験や作文試験を加えることもあります。
一般知識を問う教養試験は、通常、複数の科目からなる択一式で、合計40〜50問が出題されます。
- 数的処理…数的推理・判断推理・空間把握・資料解釈
- 文章理解…現代文・英文
- 人文科学…世界史・日本史・地理・思想・文芸
- 自然科学…数学・物理・科学・生物・地学
- 社会科学…法律・政治・経済・社会
特に出題数が多い文章理解や数的処理に重点を置き、過去の問題を繰り返し練習することが対策となります。
2次試験
地方初級公務員試験(高卒)の2次試験では、面接試験が行われます。
ほかにも、自治体によっては集団討論や適性試験・作文試験を実施する自治体もあるため、試験概要が発表されたタイミングで確認しておくことが重要です。
面接試験では公務員として必要な人間性が評価されます。
公務員試験において内定を得るかどうかは一次試験の成績ではなく、二次試験の結果によって決まると言っても過言ではありません。
最近では人物重視の観点から二次試験の配点を高く設定している自治体が増えてきている傾向にあるため、模擬面接などを受けておくことをおすすめします。
高卒で公務員になるのに向いている人
ここでは、高卒で公務員になるのに向いている人の特徴について紹介します。
➀若いうちから社会や国に貢献したい人
若いうちから国や地方のために働き、貢献したい意欲がある人は高卒で公務員になるのに向いている人でしょう。
モチベーションの高さは仕事で活きるため、早く公務員として働きたい人は高卒からの就職がおすすめです。
実際地方自治体の求められる人材として「県民視点で物事を考える」などと設定していることも多いので、悩んでいる人をサポートしたい方や直接的なコミュニケーションが苦にならない人にはぜひチャレンジしてみて下さい。
一方で、勉学に力を入れたい人や、4年間の学生生活の経験を重視したい人は、大卒程度の試験から公務員になる方が向いています。
➁早くから安定した収入を得たい人
同年代よりも早くから安定した職に就き、給与を確保したい方高卒から公務員を目指すのも一つです。
高卒の学歴でも公務員であれば、ボーナスの削減や倒産のリスクがありません。
また民間企業と比べて景気の影響を受けにくいのも公務員の魅力です。
基本的に給与は継続的に上昇するため、安定した生活を維持しながら仕事に専念できます。
➂コミュニケーション能力がある人
公務員は同じ部署の職員だけでなく、他の部署の職員や民間企業のスタッフとも協力して業務をおこなわなければいけません。
そのため、誰とでもスムーズにコミュニケーションを図る能力がある方は公務員に向いていると言えるでしょう。
実際、多くの自治体では求める人材像としてコミュニケーション能力を重視しています。
④成長意欲がある人
とくに行政職として公務員になると数年ごとに異動があり、さまざまな業務を経験することになります。
部署が異なると業務内容も変わりますし、法改正や社会情勢の変化によっても業務が影響を受けることがあります。
そのため、常に学び続ける姿勢が求められます。
公務員はルーティンワークだと考える人もいますが、実際には異なる側面もあるため成長意欲がある人は向いているでしょう。
高卒で公務員対策をするならアガルート
数ある公務員試験の通信講座の中でも、最もおすすめできるのは近年急激に受講者を伸ばし続けているアガルートです。
地方公務員や国家公務員試験の対策ができるのはもちろん、幅広い試験種に対応しているためあなたのキャリアを間違いなくサポートしてくれます。
アガルート公務員試験講座の魅力
- 敏腕講師が効率を究めた講座内容
- 講師が自ら編集したテキスト
- 手厚い受講生サポート
- 他にない合格特典が魅力
アガルートの通信講座は効率性を最も重要視しており、完成度の高い講座と教材で学習できることから満足度の高さが特徴です。
無制限の質問制度や最大で全額が返金される合格特典など魅力が盛りだくさんとなっているため、気になった方はぜひ公式ページをご覧ください!
アガルートで現在開催中のセール情報

全ての方を対象に、2025年合格目標の対象講座の講座を20%OFFで販売しています。
さらに、対象者の方は最大20%OFFになる割引制度も併用してご利用できます。
| セール名 | 2025年合格目標アウトレットセール20%OFF |
|---|---|
| 割引額 | 20%OFF |
| 期間 | 2025年6月29日(日)まで |
| 対象講座 |
※定期カウンセリングはセール対象外です。 |
| キャンペーン詳細 | https://www.agaroot.jp/komuin/cp_sale/ |
高卒でも公務員を目指せる!
今回は、大学中退を含めた高卒の方が公務員になるための方法をまとめてご紹介いたしました。
地方公務員と国家公務員という2つの大きな区分がある中で、試験や業務内容を見比べてご自身にマッチする選択をしていただけると幸いです。
またもしこれから高卒の方が公務員試験の勉強をスタートするのであれば、効率よく学習できる通信講座の活用をおすすめします。
効率を最重要視したカリキュラムと手厚い受講生サポートが魅力のアガルートが少しでも気になった方は、ぜひこちらから公式サイトをご覧ください!