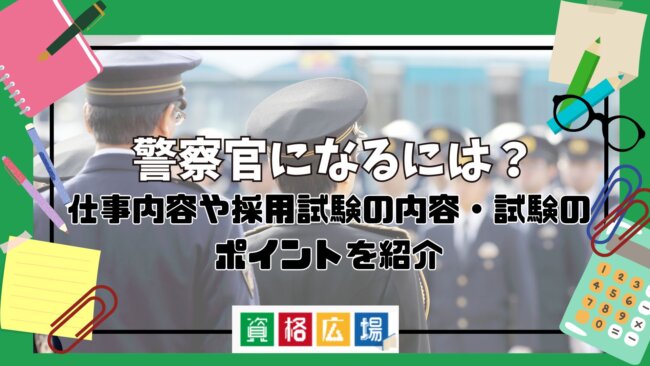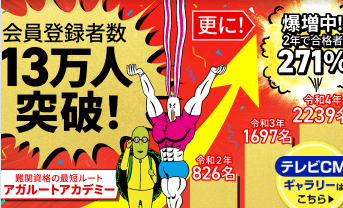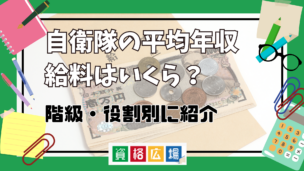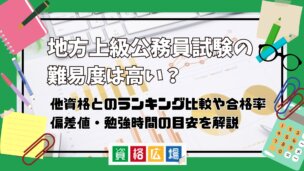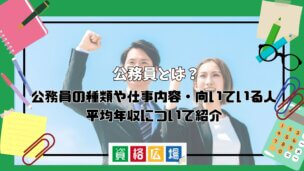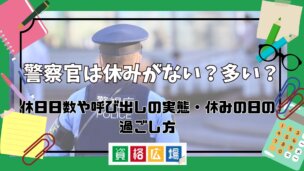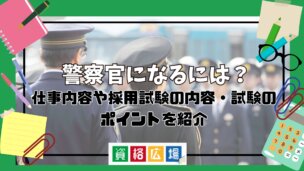日々の私達の生活の安全を守ってくれる警察官は、憧れる人も多くどの年度でも人気の高い職業です。
警察官になるには国家公務員試験もしくは各都道府県が実施する警察官採用試験に合格する必要があります。
そこで今回は、実際に警察官になるための条件や試験内容・採用試験の内容から難易度まで徹底的に解説していきます。
警察官とは
警察官とは皆さんご存じの通り、人々の安全を守る仕事です。
交通安全から民間の犯罪の取り締まり、テロ対策や落とし物の管理等、国民の生活の安全を保持する仕事を請け負います。
各職務内容により部署が分かれており、様々な警察官が分担をして街の安全を維持しています。
公務員に分類され、地方自治体に所属する地方公務員と、警察庁に所属する国家公務員の2つのパターンがあります。
都道府県の警察官(地方公務員)とは
警察官は全国の警察官の中で90%以上が都道府県警察に勤務する地方公務員です。
おもに交番での勤務やパトロールを通じて、地域住民の安全で安心な生活を守ります。
主に以下の部署に分かれて分担し、地域住民の安全を守っています。
- 地域警察…管轄地域のパトロールなど
- 生活安全警察…防犯・女性・子どもの安全対策など
- 刑事部…殺人・生涯・強盗・詐欺の操作や犯人の逮捕
- 交通部…交通違反の取締り・交通事故処理など
- 警備警察…大統領・首相などの容認の警護・国際テロ対策・災害救助など
- 総務…情報管理・広報・会計など
- 警務警察…人事・給与・警察運営など
実際に現場で対応することが多いのが特徴です。
ただし都道府県警察の中でも承認試験を受けて警視正になるとも国家公務員になることもできます。
地方公務員として働くには各自治体が実施している警察官採用試験に合格しなければいけません。
試験に合格すると、「警察官採用候補者名簿」に名前が掲載され、試験の翌年度の4月以降に順次採用され、「巡査」の階級が与えられます。
また採用後はすぐに現場に配属されるわけではなく、まずは警察学校で警察官に必要な基本的な知識、技術、体力を習得します。
警察学校は全寮制であり、大学卒業者の場合は6ヵ月間、それ以外の者は10ヵ月間の入校が求められます。
警察学校を卒業した後は交番勤務に従事し、その後は経験年数や実績、能力に応じてキャリアを積んでいくことになります。
地方公務員の採用試験は、試験を実施する自治体によって採用人数や条件、試験内容が若干異なります。
希望する自治体の警察官採用案内や警察署のウェブサイトを確認してみてください。
警察庁の警察官(国家公務員)とは
警察庁で勤務する警察官は国家公務員であり、警察組織の中心的な役割を果たすため、「警察官僚」や「キャリア」と呼ばれたりもします。
仕事内容は現場での業務はほとんどなく、警察組織全体の政策や企画の立案、各機関との調整などの役割を担っています。
また、警察庁と似た名称に警視庁がありますが、警視庁は東京都の警察を指し、警視庁の警察官は国家公務員ではなく地方公務員です。
警察庁で働くことを希望する場合、まず国家公務員試験(国家一般職試験または国家総合職試験)に合格しなければいけません。
さらに国家公務員試験に合格した後、警察庁への官庁訪問を行い、そこで合格すれば警察官として内定を得ることができます。
警察庁の採用試験に合格する者は毎年約30人と非常に難易度が高く、狭き門となっているためしっかりとした対策が必要です。
皇居警察本部
皇宮警察本部は1886年の創立以来、皇室守護を目的とした大きな使命と伝統を持つ国家機関です。
勤務先は主に皇居と赤坂御用地のほか全国の御用邸などの警備も行い、おもな以下の仕事内容となります。
- 護衛部門…天皇・皇后両陛下や皇族の護衛、国家にとって重要な来客や海外の大使が皇居を訪れる際の身辺警護など
- 警備部門…天皇がお住まいになる皇居や御所、御用邸、皇室行事などの警備
- 警務部門…皇宮警察の活動を円滑に進めるために、勤務体制・採用・人事管理・教養・予算・福利厚生などを担当
皇宮警察本部で働くには国家公務員試験である皇宮護衛官試験に合格しなければならず、大卒程度と高卒程度の区分があります。
警察官になるための受験資格
警察官になるには各都道府県で実施される警察官採用試験に合格しなければいけません。
警察官採用試験は学歴に応じて試験区分が設定されていますが、誰でも受験できるわけではなく、受験するための条件や受験資格があります。
ここでは大卒程度の警察官になるための受験資格について紹介します。
年齢要件
警察官採用試験(大卒程度)の年齢要件は都道府県によって異なりますが、年齢要件の上限はおおむね32歳~35歳程度となっています。
詳しい年齢要件について知りたい方は希望する自治体の警察官採用案内や警察署のウェブサイトを確認してみてください。
身体基準
| 男性 | 女性 | |
|---|---|---|
| 身長 | 160cm以上 | 154cm以上 |
| 体重 | 48kg以上 | 45kg以上 |
| 胸囲 | 78cm以上 | - |
| 視力 | 両目とも裸眼視力0.6以上または矯正視力1.0以上 | |
| 色覚 | 正常であること | |
| その他 | 警察官として職務遂行に支障のない身体状態であること | |
警察官の採用までの流れ
一般的に警察官の採用試験(大卒程度)は1次試験と2次試験の2段階で実施されており、1次試験では「筆記試験」が課されます。
1次試験に合格すると2次試験に進むことができ、2次試験は面接や集団討論等が実施されます。
ほかにも2次試験では体力検査、身体検査が行われ、全てにパスすることで晴れて最終合格となります。
第1次試験
| 教養試験 | 出題分野の内容は、おおむね次のとおりです。【五肢択一式、30題、1時間10分】 〈知能分野〉 文章理解、判断推理、数的処理、資料解釈、図形判断 〈知識分野〉 社会科学(政治、社会、法律、経済)、一般科目(国語、英語)、時事問題 |
|---|---|
| SPI(基礎能力検査) | 言語的理解力や数的処理能力、論理的思考力等についての択一式の検査を行います。 Ⅰ類:GAT-U(ペーパーテスティング方式)【択一式、70題、1時間10分】 Ⅲ類:GAT-H(ペーパーテスティング方式)【択一式、90〜95題、1時間10分】 |
| 論(作)文試験 | 課題式の論(作)文試験を行います。【1題、1時間】 |
| 資格経歴等の評定 | 所持する資格経歴等についての評定を行います。 (申請方法等は「資格経歴等の評定」を参照してください。) |
| 適性検査 | 警察官としての適性について、記述式等の方法により検査を行います。 |
参照:採用案内(警察官) | 採用情報 | 令和7年度警視庁採用サイト
教養試験(択一式)や論作文、適性検査など、主に筆記試験が行われます。
高校までに学んだ英語、国語、数学、理科、社会などが出題される試験で、マークシート方式が採用されています。
論作文試験は字数が600字~1,200字程度、時間が60分~120分程度となっており、警察官としての職務に関連する課題や最近の犯罪についての考察が出題されるのが一般的です。
適性検査は警察官としての適性を判断するために、クレペリン検査や性格検査などが実施されます。
教養試験は多岐にわたる科目が出題され、合格レベルに達するまでに時間がかかることがあるため、通信講座や予備校の利用を検討するのもひとつです。
第2次試験
| 面接試験 | 人物についての面接試験を行います。 |
|---|---|
| 身体検査 | 警察官としての職務執行上、支障のある疾患の有無等について検査を行います。 |
| 検査内容 | 視力検査、色覚検査、聴力検査、運動機能の検査、医師の診察、身長測定、体重測定、レントゲン検査、血液検査(貧血検査、肝機能検査、血中脂質等検査、血糖検査)、尿検査 |
| 視力 | 裸眼視力が両眼とも0.6以上、又は矯正視力が両眼とも1.0以上であること |
| 色覚/聴力 | 警察官としての職務執行に支障がないこと |
| 疾患 | 警察官としての職務執行上、支障のある疾患がないこと |
| その他身体の運動機能 | 警察官としての職務執行に支障がないこと |
| 体力検査 | 職務執行上必要な体力の有無について検査を行います。(種目は変更する場合があります。)種目:腕立て伏せ、バーピーテスト、上体起こし、反復横跳び |
| 適性検査 | 警察官としての適性について、記述式等の方法により検査を行います。 |
参照:採用案内(警察官) | 採用情報 | 令和7年度警視庁採用サイト
全ての警察官採用試験で、口述試験(個別面接)や体力検査が実施されます。
口述試験(個別面接)では面接の時間が面接カードを基に進められ、志望動機や自己PR、併願状況などについて多角的に質問が行われます。
また、時事に関する難問の口頭試問を行う自治体も存在するため自己分析や仕事分析はもちろん、日常生活の中で新聞やニュースに目を通し、自分の意見を整理しておくことも合格の道です。
体力検査は1次試験または2次試験で全ての自治体において実施され、自治体によって異なるものの腕立て伏せや反復横跳び、バーピーテストなどが行われ、受験者の体力を測定します。
勉強はもちろん重要ですが、勉強の合間にリフレッシュの一環として、ある程度の筋力トレーニングを行うことをお勧めします。
2次試験の配点比率はどの自治体でも高い傾向にあり、1次試験を通過してから2次試験の対策を始めるスケジュールでは間に合わないのが現状です 。
したがって、早い段階から筆記試験対策と並行して人物試験の準備を進める必要があります。
警察官の年収は600万円程度
令和7年度警視庁採用サイトによると、警察官の給与は初任給で302,100円(Ⅰ類採用者)、264,700円(Ⅲ類採用者)となっています。
ちなみに年収例は実務2年目で6,152,000円(Ⅰ類)となっています。
警察官の採用試験に合格するための勉強法
教養試験、論文試験、体力試験の3つの主要な部分から構成されており、各部分に対する適切な準備が求められます。
以下では、それぞれの試験部分において、合格に向けた効果的な勉強方法を提案します
勉強方法➀教養試験対策を問題集を使って徹底的に対策する
警察官採用試験の教養試験は、一般知識、法律、社会情勢など幅広い分野から出題されます。
この部分で高得点を獲得するには、問題集を使った徹底的な対策が必須です。
市販されている警察官採用試験専用の問題集は、過去に出題された問題や、試験に頻出する重要なポイントを網羅しています。
毎日一定の時間を問題集に割くことで、試験の形式や問題のパターンに慣れるとともに、知識の幅を広げることができます。
また、解説を読むことで、正解の理由だけでなく、なぜ他の選択肢が間違っているのかの理解も深めることが重要です。
勉強方法➁論文作成のスキルを身に着けて実践する
論文試験は、受験者の思考力、判断力、表現力を評価するための重要な部分です。
この試験に対策するには、まず論文作成の基本的なスキルを身につけることから始めます。
具体的には、論文の構成方法、主張の立て方、根拠の提示の仕方など、基本的なライティング技術を学びます。
次に、実際に過去の試験問題や想定されるテーマについて論文を書いてみる実践を行います。
論文を書く際には時間を計って実際の試験と同じ条件下で行うことで、時間管理の練習も同時に行うことができます。
また、できれば、専門家や信頼できる人に添削してもらい、フィードバックを得ることで、書き方をさらに改善していくことが重要です。
勉強方法➂体力試験の項目に合わせて体力づくりをする
体力試験は、警察官としての基本的な体力を評価するための試験です。
試験項目には、短距離走、長距離走、腕立て伏せ、座り込みなどがあります。
これらの試験項目に合わせて、日常的に体力づくりを行うことが必須です。
具体的には、各試験項目に特化したトレーニングプログラムを組むことがおすすめです。
例えば、短距離走ではスプリントトレーニングを、長距離走では持久力をつけるためのジョギングやインターバルトレーニングを行います。
また、腕立て伏せや座り込みでは、筋力トレーニングを定期的に行い、体力の基礎を強化します。
これらのトレーニングを継続することで、試験当日に最高のパフォーマンスを発揮することができます。
警察官の採用試験を受ける際の注意点
ここでは、警察官の採用試験を受ける際の注意点について紹介します。
注意点①試験の条件は自治体によってさまざま
警察官採用試験は自治体ごとに受験資格や試験内容が異なるため、採用情報の確認が不可欠です。
採用試験情報では具体的に試験日、受験資格、試験内容、募集人数などを見ておくようにしましょう。
特に、試験を受けることができるかどうかを確認するために、受験資格は必ず確認しておくことが重要です。
また、募集人数の変動によって合格倍率が大きく変わるため、過去の試験の合格倍率を見ておくこともおすすめします。
興味のある自治体があれば早めに試験情報を整理し、いつどの自治体を受験するのかや合格するためにどのような試験対策が必要かを考えておきましょう。
注意点➁試験に有利になる資格や経歴がある
採用試験における試験経歴等の評価では各自治体が指定する資格や経歴を持っている場合、試験の得点に加点がなされます。
対象となる資格や経歴は自治体によって異なるものの、主に剣道や柔道などの段位、スポーツ大会への出場歴、実用英語検定(英検)や中国語検定などの語学関連資格、ITパスポートなどの情報処理関連資格が加点の対象となります。
加点対象の資格を持っていなくても他の試験の成績が優れていれば合格することはできますが、合格の可能性を高めるために加点対象となる資格の取得を検討しておくのもひとつでしょう。
注意点➂事前に試験のスケジュールを抑えておく
警察官採用試験は多くの自治体で年に数回行われます。
早い自治体では、3月から試験の申し込みを受け付け始め、4月には最初の一次試験を実施しますので気になるところがあれば試験情報を逃さないようにするのが重要です。
試験のスケジュールが把握できれば、4月には警視庁の採用試験、5月には神奈川県警察の採用試験といった具合に複数の自治体を併願する計画を立てることができます。
特に行きたい自治体がある場合は、合格するまで何度でも受験することが許されるケースもあります。
また、受験地から遠く離れた場所に住む方でも受験しやすいように、複数の自治体が共同で採用試験を実施することもあります(男性警察官)。
例えば、警視庁は東京都以外にも1道18県で採用試験を行っています。
いくつかの自治体を受験する際はいくつものスケジュールを確認する必要があるため、スケジュール管理を徹底することが重要です。
警察官になるまでの学習期間の目指すは1年間
警察官になるまでに必要な学習時間の目安としては、1年間程度だとされています。
早い方で新年度を迎える前の2月に対策をスタートします。
ある程度ゴールを見据えたうえで対策をスタートさせた方が効率的です。
通信講座や予備校では最終合格に向けて逆算されたスケジュール、洗練されたテキスト・問題集、気軽に利用できる担任講師によるフォロー制度といった充実の仕組みがあり、最終合格可能性はぐんと高くなります。
警察官を目指すならアガルート

今回は、実際に警察官になるための条件や試験内容・採用試験の内容から難易度まで徹底的に解説してきました。
警察官になるには国家公務員試験か都道府県が実施する警察官採用試験に合格しなければなりません。
国家公務員試験も警察官採用試験も範囲が広いため、独学だと不安な方や時間がないといった方は通信講座の利用をおすすめします。
中で見アガルートは国家公務員試験の合格者を多数輩出しているので安心です。
実力はの講師陣夜指導や手厚いサポート、充実したオリジナルテキストはアガルートにしか出せない持味で、大きなアドバンテージになってくれるはずです。
アガルートでは合格特典やお得なキャンペーンも実施されているのでぜひチェックしてみて下さい。