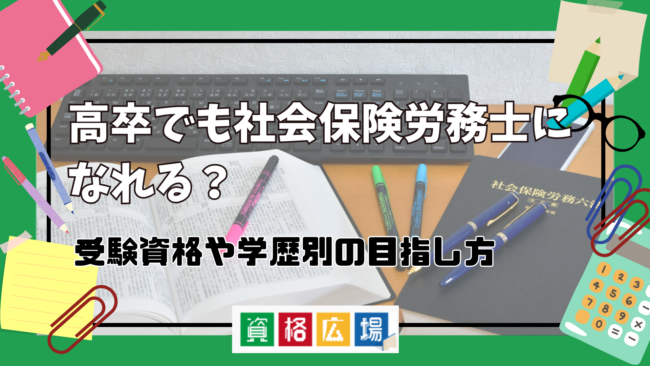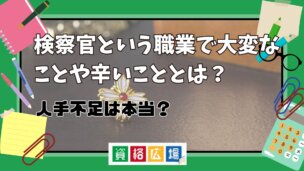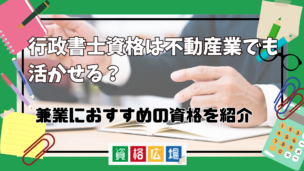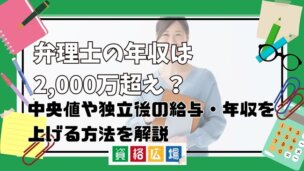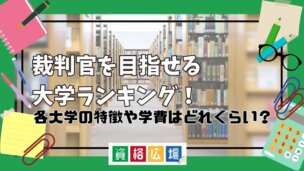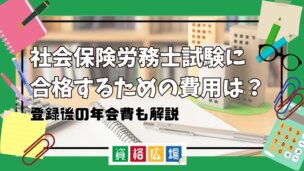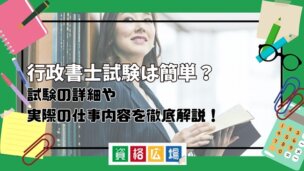国家資格の中でも人気が高い「社会保険労務士」の試験には学歴等で受験資格が細かく設けられており、無条件で受けられない試験となっています。
それゆえ、高卒で未経験の自分が社会保険労務士の資格を取得出来るのか不安な方も多いのではないでしょうか。
そこで本記事では、高卒で社会保険労務士を目指す方向けに「社会保険労務士の受験資格やおすすめの目指し方、活躍する方法」についてご紹介します。
どのような受験資格が設けられており、今から目指すならどんなルートが効率的なのか具体的に解説していきます。
司法試験・予備試験の通信講座・予備校おすすめランキング9選!料金費用の安さ・人気・評判を徹底比較【最新】
社会保険労務士試験におすすめの通信講座
高卒では社会保険労務士の受験資格はない
結論から申し上げますと、学歴が高卒の方は社会保険労務士の受験資格を満たしていません。
ただし、高卒の方でも他の受験資格を満たすことで社会保険労務士を目指すことが出来るため、簡単に諦めてしまっては勿体無い話です。
高卒では受験資格がないという事実がある上で、社会保険労務士を目指したい方はこれからどうすべきか本記事を参考にしながら検討してみましょう。
社会保険労務士試験の受験資格とは?
高卒の学歴では受験資格を満たせないことが分かりましたが、社会保険労務士を目指せる受験資格にはどのようなものがあるのでしょうか。
こちらの項目では「社会保険労務士に必要な受験資格の例」を以下の3つの項目に分けてご紹介します。
- 学歴
- 3年以上の実務経験
- 特定の国家資格所持者
上記、全ての条件を満たす必要はなくいずれか1つを満たすだけで良いとされています。
取得しやすい試験資格・条件はあるのか具体的に見ていきましょう。
受験資格①:学歴
受験資格の1つ目は「学歴」です。
単純に大卒や院卒など高学歴であれば良いという訳ではなく、以下のように細かく条件が決められています。
| 学歴に関する受験資格 | 留意点 |
|---|---|
| 国公立大学・私立大学・通信制大学・短大・専門職大学(前期過程修了者でも可)・専門職短期大学・高専(5年制高校)の卒業者 | 専攻学部・学科・コースの指定はない |
| 62単位以上の卒業要件単位を取得済みの者 | 卒業生に限らず現役生や編入生、中退者でも可とする内容 ※短大は含まれない |
| 一般教養科目36単位以上、かつ専門科目等の単位を加え48単位以上の卒業要件単位を取得済みの者 | 一般教養科目の比重が大きい大学2年生までや高専生をメインの対象とする内容 ※短大は含まれない |
| 高等学校高等科や大学予科を卒業した者 | 昭和時代前期頃の高等教育機関 |
| 厚生労働大臣が認める学校を卒業した者 | 省庁大学校や養成学校、海外の学校などを対象とする内容 |
上記の表からも、受験資格に高卒は含まれず学士や短期大学士以上の学歴が求められることが分かります。
後述の「オススメの方法」にて、学歴に関する受験資格を得る方法について詳しく解説するのでチェックしてみて下さい。
受験資格②:3年以上の実務経験
受験資格の2つ目は「3年以上の実務経験」です。
どのような実務経験を持つ場合に、社会保険労務士の受験資格として認められるのかについて以下の表にて確認しましょう。
| 実務経験に関する受験資格 | 留意点 |
|---|---|
| 労働社会保険法令の規定に基づいて設立された法人の役員や従業員 | 健康保険組合や労働保険事務組合などが該当 |
| 国又は地方公共団体の公務員や日本郵政公社の役員と職員 | 労働局、市区役所や町役場などの職員を対象とする内容 |
| 全国健康保険協会や日本年金機構の従業者 | 非常勤の者を除く |
| 社会保険労務士や弁護士の補助者 | それぞれ法人も可 |
| 労働組合の専従役員や一般企業の労働組合職員 | 一般企業の人事労務担当者を対象とする内容 |
| 法人ではない社団や財団の労務担当役員 | 労働組合は除く |
公務員や弁護士補助など、社会保険労務士との関わりがある業務を「通算3年以上」経験されている方は受験資格の対象となります。
受験資格③:特定の国家資格所持者
受験資格の3つ目は「特定の国家資格所持者」です。
| 実務経験に関する受験資格 | 留意点 |
|---|---|
| 厚生労働大臣が認めた国家試験に合格した者 | 学歴に関する受験資格が必要な資格もあるので要注意 |
| 司法試験予備試験の合格者 | 法科大学院を卒業していない高卒の方でも対象者となり得る |
| 行政書士試験に合格した者 | 受験資格の制限なし |
土地家屋調査士や情報処理技術者試験など特定の国家資格を所持している方は、社会保険労務士の受験資格として認められています。
そのため、高卒の方でも取得済みの国家資格で受験資格を得ることが出来る可能性もあります。
社会保険労務士の出願から試験当日までの流れ
社会保険労務士試験への道は、計画的な準備と正確な手続きが求められます。
出願から試験当日までの流れ
- 4月半ばに願書配布
- 5月下旬までに願書提出
- 8月下旬に試験実施
- 11月上旬に合格発表
各ステップでの注意点をしっかり把握し、無事に試験日を迎える準備を整えましょう。
4月半ばに願書配布
社会保険労務士試験の願書は、毎年4月中旬に配布が開始されます。
この配布は、厚生労働大臣による官報公示後に始まるため、試験を受けたい方はこの時期に注意して情報を確認する必要があります。
願書は試験センターや都道府県の社会保険労務士会で直接受け取ることができ、また、郵送での請求も可能です。
令和6年度:第56回社会保険労務試験申込受付日
- 4月15日(月)から5月31日(金)
※受付期間終了
この段階で試験の日程や申込みに必要な書類のリストも確認しましょう。
5月下旬までに願書提出
願書の提出は5月下旬までとなっており、提出方法は郵送または直接試験センターの窓口での受付が可能です。
郵送の場合、5月31日の消印が有効とされており、窓口では5月の最終営業日まで受け付けられます。
土日祝日は窓口が閉まっているので、提出日の計画は慎重に行うことが重要です。
8月下旬に試験実施
社会保険労務士の試験は通常、8月の第4日曜日に実施されますが、年によってはこの日程が異なります。
令和6年度:第56回社会保険労務試験の試験日
- 8月25日(日)
試験会場は全国の主要都市に設けられており、受験者は事前に確認しておく必要があります。
なお、試験会場は申込願書に記入した試験地に基づいて決定します。
以下は、前年度に実施された社労士試験の試験会場になります。
| 試験地 | 試験会場名 |
|---|---|
| 北海道 | 札幌大学 |
| 宮城県 | 東北学院大学 |
| 埼玉県 | 埼玉大学 |
| 埼玉県 | JA共済埼玉ビル |
| 東京都 | 東京ビックサイト |
| 東京都 | 武蔵大学江古田キャンパス |
| 千葉県 | 幕張メッセ |
| 神奈川県 | 日本大学生物資源科学部 |
| 神奈川県 | 関東大学 八景 |
| 愛知県 | ポートメッセなごや第2展示館 |
| 京都府 | 立命館大学衣笠キャンパス |
| 大阪府 | インテックス大阪 |
| 大阪府 | 近畿大学 東大阪キャンパス |
| 大阪府 | 大和大学 |
| 兵庫県 | 神戸国際展示場 |
| 石川県 | 金沢工業大学 |
| 岡山県 | 岡山大学 津島キャンパス |
| 福岡県 | 博多国際展示会場 |
試験内容は労働法、社会保険法を始めとする複数の法律に関連する知識が問われ、広範な学習と準備が求められます。
11月上旬に合格発表
試験の合格発表は例年11月上旬に行われますが、第56回試験の合格発表は10月上旬に実施されます。
令和6年度:第56回社会保険労務試験合格発表日
- 10月2日(水)
合格者は官報で公示される他、合格証書が郵送されることになっています。
合格後は、社会保険労務士として登録手続きを行い、実務に入る前に必要な手続きや研修があります。
社会保険労務士としてのキャリアをスタートさせるためには、この試験の合格が第一歩となります。
高卒で社会保険労務士の受験資格を得るおすすめの方法
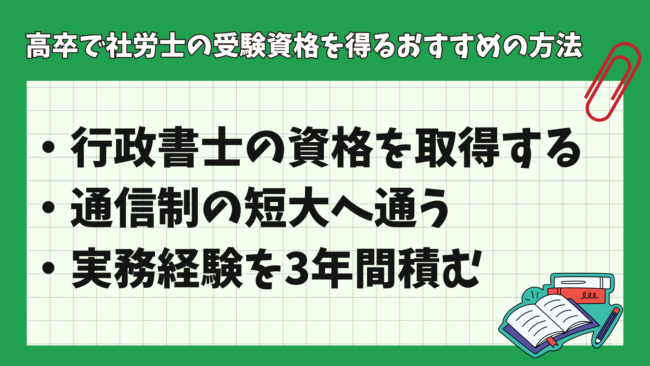
前述の「社会保険労務士の受験資格」を踏まえて、こちらの項目では高卒の方向けに「社会保険労務士の受験資格を得られるオススメの方法」について3つをご紹介します。
なるべく資金や時間の負担を減らし効率よく取得できる方法を厳選したので、それぞれチェックしてみて下さい。
行政書士の資格を取得する
おすすめの方法の1つ目は「行政書士の資格を取得する」ことです。
行政書士の試験には受験資格の制限がなく、高卒の方でも受験資格を得るために大学受験の勉強や転職活動を行う必要がないメリットがあります。
また、以下の表からも分かるように、他の法律系国家資格の中でも合格率が高く、比較的取得しやすい資格と言えます。
| 試験名 | 2023年の合格率 |
|---|---|
| 司法試験予備試験 | 3.58% |
| 行政書士試験 | 13.98% |
| 社会保険労務士試験 | 6.4% |
さらに、行政書士資格は認知度も高くダブルライセンスとしても有用性があることから、高卒の方に限らず多くの社会保険労務士が取得を目指す資格でもあります。
従って、効率の良さと実用面から考えて、行政書士の資格を取得する方法は最もオススメできる方法です。
通信制の短大へ通う
おすすめの方法の2つ目は「通信制の短大へ通う」ことです。
大学は卒業するまで4年かかるのに対して、通信制の短大は2年間で卒業できる上に通学授業以外は自宅学習となるため、社会人の方でも時間が確保しやすいメリットがあります。
また、大学に通う場合と比較し2年分短い分、入学金や授業料などの費用面においてもトータルで抑えることが出来る魅力もあります。
学んだ内容を試験勉強や実務に活かしたい方は、「産業能率短期大学」のように社会保険労務士に特化した大学もあるので検討してみてください。
実務経験を3年間積む
おすすめの方法の3つ目は「実務経験を3年間積む」ことです。
前述した実務経験に関する受験資格の何れかに従事している方や、新卒の方は一度実務経験を積む道が1番効率的と言えます。
効率的である理由として、給料も得ることが出来る上に実務をこなしながら試験内容の勉強が出来るため、費用を掛けずに試験勉強が可能ということが挙げられます。
3年という時間の縛りはあるものの、就職の際に優遇されるケースや独立開業後に役立つスキルを早期に習得できるメリットもあります。
社労士試験講座ならアガルートアカデミーがおすすめ!
社労士試験合格を目指すならアガルートアカデミーがおすすめです!
フルカラーで見やすいテキスト教材と分かりやすい動画講義で、初めて資格勉強をする方でも充分合格が目指せるカリキュラムになっています。
合格者には受講費全額返金orお祝い金3万円の特典もあるのでモチベーションの維持も期待できます!
最短ルートで合格が目指せる!
アガルート公式HPはこちら
高卒で社労士資格を取得しても就職はできる?
社会保険労務士の受験資格においては学歴を重視する傾向がありますが、就職の際にも高卒の学歴は不利に働くのでしょうか。
こちらの項目では「高卒で社会保険労務士の資格を取得した場合に就職可能なのか」について以下の4つの進路に焦点を当ててご紹介します。
- 社労士事務所
- 他士業の事務所
- 社労士として企業勤務
- 独立開業
就職可能な理由やそれぞれの進路先におけるメリットについて具体的に見ていきましょう。
高卒でも社労士事務所に就職は可能
進路先候補の1つ目である「社労士事務所への就職は高卒の社会保険労務士でも可能」です。
理由として、資格保有者であれば最終学歴は実務上問題にならないからです。
実際、就職・転職サイトの「求人ボックス」に掲載されている大半の求人が「学歴:高校卒業以上」となっています。
従って、高卒の方でも受験資格さえ取得できれば、社会保険労務士として活躍できる場が用意されているので諦めないようにしましょう。
高卒でも他士業の事務所に就職が可能
進路先候補の2つ目である「他士業事務所への就職は高卒の社会保険労務士でも可能」です。
社労士事務所に就職可能な理由と同様に、資格保有者は社会保険労務士に必要な学力があると認められるからです。
前述した行政書士資格とのダブルライセンスを目指せば、各士業事務所においてさらに活躍が期待できます。
高卒で社労士として企業勤務の場合は難しい
士業で働く場合には資格所持が優遇されるため学歴においては不問の場合が多かったですが、進路先候補の3つ目である「企業への就職は高卒の社会保険労務士では難しい」と言えます。
理由として、企業に就職する場合には社会保険労務士としてではなく人事や総務部門での雇用となるため、最終学歴が判断材料になる可能性が高いからです。
実際「求人ボックス」の求人においても、大卒以上の学歴が必要な場合や実務経験や年齢制限など、比較的条件が厳しいことが分かります。
従って、高卒の方が勤務社労士を目指す場合には、前述した「通信制の短大に通う」方法で学歴を上げると良いでしょう。
高卒社労士として独立開業するという道も!
進路先候補の4つ目である「独立開業は高卒の社会保険労務士でも可能」です。
士業事務所や企業に就職する場合と異なり、ご自身で社会保険労務士事務所を開業する場合には学歴で判断されなくなるメリットがあります。
また、就職したものの高卒であることをハンデに感じる場合には、一定の実務経験を積んだ後に独立開業するという考え方もあります。
この後、独立開業を成功させる方法や就職先で活躍する方法について詳しく解説するのでチェックしてみましょう。
高卒でも社会保険労務士として活躍する方法
高卒でも資格を取得すれば就職できる見込みはありますが、社会保険労務士の人数は年々増加傾向にあり就職が難しい状況にあります。
こちらの項目では、高卒の方向けに「社会保険労務士として活躍するための3つの方法」についてご紹介します。
- 実務経験を十分に積む
- ダブルライセンスを取得する
- 高卒の社労士講師として活躍する
学歴のハンデを乗り越え、社会保険労務士としてのキャリアを築く方法を詳しく見ていきましょう。
実務経験を十分に積む
活躍する方法の1つ目は「実務経験を十分に積むこと」が挙げられます。
近年、社会保険労務士の人口が増えたことで競争倍率が上がり、「即戦力になる人材」が求められています。
そのため、社会保険労務士としての実務経験を積むのはもちろんのこと、受験資格の対象となる職種における実務経験の重要性が高まっています。
社会保険労務士になる前に、資格未取得でも実務経験が出来る事務所への就職を検討してみると良いでしょう。
ダブルライセンスを取得する
活躍する方法の2つ目は「ダブルライセンスを取得する」ことです。
税理士や中小企業診断士など国家資格の中には社会保険労務士との親和性が高く、就職時にアピール出来る資格も多くあります。
例えば、税理士とのダブルライセンスは、企業における税務と労務の業務を一括で携わることが出来るため、独立後に活かせる顧客を得ることが期待できます。
また、中小企業診断士は社会保険労務士のコンサル業と相性が良く、人事労務の視点から経営者にアドバイスを行う経営コンサルタントとして活躍できます。
社会保険労務士としてキャリアアップを目指すためにも複数の資格取得を目指してみましょう。
高卒の社労士講師として活躍する
活躍する方法の3つ目は「高卒の社労士講師として活躍する」ことです。
現在、社会保険労務士を目指すための講座は多岐に渡りますが、難関大学卒の方が講師を担当する講座が一般的となっています。
そのため、高卒の社会保険労務士講師は希少価値が高く、従来のサービスと差別化を図ることが出来るため講師としても活躍が期待できます。
このように、高卒の方には大学を卒業しない方法で資格を取得したということを逆手に取り活かすことも可能と言えます。
社会保険労務士の受験資格取得が向いている方
社会保険労務士になるための受験資格を取得することは、労働問題に対して熱心な関心を持つ方に特に適しています。
社会保険労務士の受験資格取得が向いている方
- 労働問題に関心がある方
- 人事・労務関係のコンサルティング業務に関心がある方
- 将来的に独立を考えている方
これらの要素に魅力を感じる方は、社会保険労務士の資格取得に向けて、第一歩を踏み出すことができるでしょう。
労働問題に関心がある方
近年、働き方改革など労働問題が社会的に大きな注目を集めています。
このような背景の中、労働環境の改善や労働者の権利を守るための知識を深めたいと考えている方に社会保険労務士の資格は特に適しています。
社会保険労務士として、労働法規を駆使し企業と労働者の橋渡しを行うことで、より良い労働環境の実現に貢献できます。
人事・労務関係のコンサルティング業務に関心がある方
人事や労務管理は企業運営の根幹を成す重要な部分です。
社会保険労務士は、企業の人事戦略や労務リスクの管理、労働関連法規の適用について専門的なアドバイスを提供することが求められます。
この分野に興味を持ち、組織の効率化や職場の問題解決に貢献したい方には、この職業が適しています。
将来的に独立を考えている方
社会保険労務士の資格を取得することは、将来的に独立開業を目指す方にとって大きなメリットがあります。
自分自身の専門分野を生かし、自由な働き方を実現することが可能です。
独立開業した社労士の就労の例例えば、労働問題や年金設計に強みを持つ社会保険労務士として、特定のニッチ市場をターゲットにした事務所の開業。
このようなキャリアを築きたい方には、社会保険労務士という職業が最適です。
社会保険労務士の受験資格、高卒では無理?まとめ
今回、社会保険労務士の受験資格について「学歴・実務経験・国家資格」の3つの視点からご紹介した上で、高卒の方が受験資格を得るための方法や取得後の進路について解説しました。
受験資格がない高卒の方でも、以下の方法で効率良く受験資格を取得可能です。
- 行政書士の資格を取得する
- 通信制の短大へ通う
- 実務経験を3年間積む
また、資格を取得さえすれば最終学歴に関係なく各士業事務所や独立開業の道へ進むことも出来ます。
高卒であることを理由に社会保険労務士を諦めるのではなく、今回ご紹介した方法を参考に挑戦してみましょう。