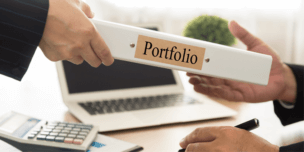日本のアニメ産業は、世界に誇る文化として海外でも高く評価されています。
作品の世界観や繊細で美しい描写は「ジャパニメーション」と呼ばれ、アニメの制作現場で多くの人々が関わって1つの作品として成り立っています。
そこで今回は、アニメーターになるには資格が必要なのか、どのような仕事内容なのか、気になる給料やバイト、学校などを解説していきます。
アニメーターになるには?

アニメーターとは、アニメーションの基本となるキャラクターや背景など原画に沿って絵を描く人のことです。
アニメーターになるには、特別な資格や学歴は必要なく、絵を描くことが好きな人なら誰でも目指すことができます。
しかし、アニメーターに求められるものは、自由に好きな絵を描くよりも、正確なデッサン力や模写力、絵を繋ぎ合わせる技術が求められます。
アニメーターになるには、アニメーション系の専門学校や芸術系の大学で基礎的なスキルを学んだ後に、アニメーションのプロダクションや制作会社に就職するケースが多いです。
またその他にも、直接プロダクションや制作会社でバイトをしながら、スキルを学んでステップアップしたり、フリーランスとして働くケースもあります。
アニメーションになるには、長い下積みを覚悟する必要がありますが、絵を描いたりアニメーションを心から愛する人にとって非常に魅力的で素敵な仕事ではないでしょうか。
アニメーターの学校・費用って?
アニメーターになるには、アニメーション系の専門学校に行くのが一般的でしたが、最近は大学でもアニメーション学科・アニメーション専攻がある学校が増えています。
また画力に自信があって独学で学び、アニメーターの見習いとして、アニメーションのプロダクションや制作会社でバイトをしながらスキルを高めていくケースもあります。
ここでは、アニメーターになるための学校やその費用について解説していきます。
専門学校の場合
アニメーション系の専門学校では、アニメーターをはじめとしてCGアニメーションや声優、映像制作、脚本制作などアニメーションに関するさまざまな学科があります。
2年制の学校が多く一部3年制もあったりと学校によってそれぞれ異なり、技術・知識を学んで就職するまでのカリキュラムが組まれています。
気になる費用ですが、2年制は100万~140万、3年制は150万程度となります。
どの専門学校を選べばいいのかわからないという方は、学校講師の実績や就職実績を確認したり、カリキュラムが自分に合っているのか見極めたり、体験入学することをオススメします。
大学の場合
アニメーション学科やアニメーション専攻がある大学では、アニメーションをつくる「制作分野」やアニメーションの研究を行う「研究分野」のほか、デッサンの理論や絵の歴史など幅広い知識を見つけることができます。
就職率に関しては、専門学校の方がより特化したサポートが受けられるものの、大学卒のアニメーターが大手プロダクションや制作会社に就職しているケースは多いです。
気になる費用ですが、私立の4年制で140~180万、公立4年制で80~100万程度となります。
アニメーターに関する技術や知識以外にも、企業が求める問題解決能力やマネジメント能力も学ぶこともできます。
独学の場合
アニメーターになるには、必ずしも資格や学歴が求められるわけでなく、画力やアニメーションに関する技術が認められれば学歴のない独学者でもアニメーターとして働くことができます。
はじめは見習いとして、プロダクションや制作会社でバイトをしながらアニメーターに必要な技術や知識を学び、フリーランスとして幅広く活躍している人も多いです。
ただし、画力さえあれば良いというわけでなく、社会人としての人との関わり方やコミュニケーション能力などを最低限、身に付けておく必要があるでしょう。
アニメーターに関する資格
アニメーターとして働くときに、必要な資格などはありません。
しかし、アニメーターに関する資格を取得していると、アニメーションのプロダクションや制作会社の採用などで有利になります。
近年では、タブレットを使用したデジタル作画が増えてきているので、CGクリエイター検定資格は有効といえます。
また色彩検定の受験は、絵を描くことが仕事のアニメーターにとって活用できるでしょう。
アニメーターに関する資格とは、どのようなものがあるのか解説していきます!
CGクリエイター検定
CGクリエイター検定は、公益財団法人のCG-ARTS協会が主催する民間の資格です。
2次元CGの基礎から、3次元CGの制作・理論・手法の知識を証明する資格で、ベーシックとエキスパートの2種類あります。
1年の間に前期・後期の2回試験が行われ、アニメーター志望の人にも役立つ知識を得ることができます。
色彩検定
色彩検定は、公益社団法人の色彩検定協会が主催する民間の資格です。
1級から3級まで分けられていて、色彩に関する基礎や理論・配色技術・環境色彩など幅広い知識を証明する資格で、色彩の実践的な活用を習得できる資格です。
1級は年に1回、2~3級は年に2回行われ、キャラクターの配色や色が与える影響など絵を描くときに役立つ知識を得ることができます。
アニメーターってどんな仕事?(仕事内容)

アニメ制作の現場では、1つの作品を完成するまでたくさんの人が関わり分業して作業を担当をする仕組みになっています。
アニメーターは、アニメーション制作において需要な役割を担っていて、「動画マン」と「原画マン」の2つの業務に分かれています。
ここでは、「動画マン」と「原画マン」はそれぞれどのような仕事なのか、仕事内容を解説していきます。
動画マン
はじめてアニメーターとして仕事をするとき、一般的には「動画マン」という役割からスタートします。
動画マンとして、経験を積んだ後に原画マンへとキャリアアップするのが一般的な流れになります。
動画マンとは、アニメーション制作においてアニメの主要となる「絵」を描いていく仕事です。
原画マンから受け取った原画・設定資料・指示書を受け取り、動画用紙に丁寧に線を描いて、元の絵となる原画を書き写す「トレース」という作業をしていきます。
トレースを終えたら、中割りと呼ばれる原画と原画の間を補う作業を行い、パラパラと動かして不自然な部分がないか確認し、必要に応じて修正を行います。
最後に、清書に移って不自然な部分がないか最終チェックを行い、統一感のあるスムーズな動きに仕上げて完成です。
動画マンの仕事は、アニメーション制作に動きを加えるときの重要な役割を担っています。
原画マン
原画マンとは、アニメーション制作においてキャラや背景などアニメの元となる原画描いていく仕事です。
原画マンは、原画の元となる絵コンテ・設定資料・レイアウト用紙を受け取り、監督や脚本家を打ち合わせを行いキャラや背景を描いていきます。
そして、タイムシートと呼ばれる原画をもとに動画をつくるための指示書に、シーンに関する詳しい内容を書き込んでいきます。
必要に応じて、レイアウトを修正したりとチェックを行い、この後に作業する動画マン担当の人がわかりやすいように丁寧に原画を仕上げて完成です。
原画マンの仕事は、アニメーション制作の原液となる重要な役割を担っています。
自分の手でアニメーションに命を吹き込んでいく作業は、他ではなかなか経験できない魅力となるでしょう。
アニメーターの就職先・バイト・勤務時間
アニメーターになるには、学歴や資格は必要ないですが、一人前になるまでは給料が少なく生活が安定しません。
しかし日本のアニメ産業は、アニメーター含め、脚本家や監督、映像制作の人が1つの作品を作り上げることで成り立っています。
自分が手掛けた作品が、注目を浴びて多くの人から称賛を受けることは、アニメーターの魅力といえます。
アニメーターとして働くとなったとき、主な就職先や勤務時間、必要なスキル、やりがい、大変なことは一体どのようなものなのか?
ここでは、アニメーターの就職先・バイト・勤務時間ついて解説していきます。
アニメーターの就職先
アニメーターの就職先として、アニメプロダクションや制作会社が一般的といえるでしょう。
他にも、各工程を専門に取り扱う専門スタジオや、元受けと呼ばれる大手のアニメーションスタジオ、グロス請けと呼ばれる中小アニメーションスタジオなどがあります。
元受けは、受けた案件を自社ですべて完結して制作することが多いですが、グロス請けは、一部の制作を任されるなど幅広い案件を手掛けるのが特徴です。
またアニメーターの多くは、プロダクションや制作会社にも属さずにフリーランスとして活動しています。
しかし、いきなりフリーランスとして活動することは難しく、バイトを通じてプロダクションなどで修行し、実力とコネ得てから独立するケースが多いです。
アニメーターのバイト
現在アニメーション業界では、アニメーターが不足しているためバイトの求人募集などが多い傾向にあります。
しかし、募集をかけても一部の大手プロダクションや制作会社に集中して、中小のプロダクションや制作会社にはなかなか人が集まらない状況のようです。
そのため絵に自信がない人でも、絵やアニメに対する熱意や成長する見込みが評価されれば、比較的バイトの採用は合格しやすいといえます。
ただし、採用基準として「ポートフォリオの提出」や、前提として「絵を描けること」が条件となる可能性もあるので、まったくの初心者の人は厳しいでしょう。
アニメーターの勤務時間
アニメーターの勤務時間は、基本的には長時間労働になることが多いです。
アニメプロダクションや制作会社で働く場合は、会社規定の勤務時間になりますが、案件作品の納期が近くなれば残業が増えることもあります。
またフリーランスとなれば、規定時間がなく働けば働くほど稼ぐことができるため、長時間労働になりがちです。
フリーランスの場合は、1本あたりの単価が安く歩合制になるため、稼ぎを増やそうとより多くの案件を受けて長時間労働を強いられる悪循環が問題視されています。
そのような労働環境や賃金制度を改めるため、近ごろアニメーターを正社員雇用する企業が増えています。
アニメーターに必要なスキル・やりがい・大変なこと
実際、アニメーターになるには絵やアニメが好きなこと以外にどのようなスキルが必要なのでしょうか。
またアニメーターという職業のやりがいや大変なことは、どのようなことなのでしょうか?
そこで、アニメーターに必要なスキル・やりがい・大変なことについて解説していきます。
アニメーターに必要なスキル
アニメーターに必要なスキルとして、まず最も重要となるデッサン力が挙げられます。
アニメーターの命ともいえるデッサン力なしでは、原画を忠実に表現し動きを加えていく役割は務まりません。
また、同じ構図が続いたり修正が多くあったりと質の高い動画や原画を描くためには、忍耐力や根気は必要でしょう。
アニメーションは、1人ですべての制作を完結することはできません。
多くの人が関わりクオリティの高い作品を作り上げるには、密にコミュニケーションを取る必要があります。
そのため、自分の意図を伝えて相手の意図をくみ取れるなどのスキルは必要といえるでしょう。
アニメーターに必要なスキルを下記にまとめました。
【アニメーターに必要なスキル】
・デッサン力
・忍耐力・根気
・コミュニケーション能力
・作業スピード
・柔軟性
アニメーターのやりがい・大変なこと
アニメーターのやりがいとして、自分が手掛けた絵がテレビで形となったとき感動します。
画面を通して作品が映し出されると、これまで苦労したこともやり切った甲斐があったと感じるでしょう。
また大変なことですが、アニメーターとしての生活が安定せず現実の厳しさを痛感します。
アニメーターの多くは1枚200円~といった単価の安い仕事を数多くこなして生計を立てています。
決して楽な仕事ではありませんが、自分の好きな仕事で余裕ある生活をするためには辛抱して努力する期間は必要といえるでしょう。
アニメーターの給料・年収
アニメーターの雇用形態は、フリーランスが多くプロダクションや制作会社に所属していても、正社員や契約社員でない限り固定給がもらえません。
フリーランスは基本的に「歩合制」となっていて、手掛けた仕事に応じて報酬が支払われる形です。
一般的な仕事の単価は、動画は1枚180円~250円程度で、原画は1枚2000円~2500円程度が相場となります。
そのため駆け出しの20代のアニメーターは、歩合制で月収5万~10万となり、平均年収110万円程度が目安となります。
また業界全体では、30代の平均年収210万円程度、40代の平均年収350万程度となり、世代全体でも平均年収330万程度と言われています。
動画マンや原画マンを経て、作画監督へとステップアップすると平均年収600~1000万程度のクラスが期待できるでしょう。
最近では、一部の大手プロダクションや制作会社に勤める正社員の収入は、増加傾向にありますが、それでも他業種の年収よりは低い傾向となっています。
アニメーターの現状・将来性・向いている人
アニメーターになろうと夢を持って目指す人はみんな、アニメや絵に対する愛情を持っています。
しかし実際に、アニメーターとして働きはじめると忙しい日々に追われ、現実とのギャップを感じる人は多いでしょう。
アニメーターの実際の給料や業界の現状や将来性はどのようなものなのか、そもそも向いている人はどのような人なのかでしょうか?
ここでは、アニメーターの現状・将来性・向いている人について解説していきます。
アニメーターの現状
近年のアニメ業界を支えているアニメーターは、厳しい生活で身を粉にしてでも働きたいと強い信念を持って人たちです。
若手の駆け出しアニメーターの多くは、他のバイトと掛け持ちしたり、親から援助を受けて生活しているのが現状です。
そのような厳しい生活環境のなかでも、夢に向かって進む次世代のアニメーターが現在のアニメ業界を支えています。
近年は、日本国内のアニメーターの人手不足により、人件費の安い海外へ発注するケースが増加傾向にあります。
しかし、日本のアニメーション技術は世界でもトップレベルで評価が高いため、国内のアニメーターの人材育成が急務といえます。
アニメーターの将来性
近年、スマホの普及によりソーシャルゲームのジャンルで、アニメーターの需要が高くなってきている傾向があります。
その影響もあり、2DアニメーターやWEBアニメーターの人材育成に積極的で、単価の見直し・労働環境の改善を目指す企業も増えてきています。
また最近では、デジタル作画が広がってきていて、デジタル作画でアニメ制作する会社も見られます。
デジタル化により、動画作業は効率化されるため、仕上げられる枚数も増えて、歩合給の増加にもつながります。
そのため将来的にアニメーターは、デジタルツールの知識、スキルが今までより求められるようになるでしょう。
アニメーターに向いている人
アニメーターに向いている人ってどのような適性があるのか気になる人も多いと思います。
アニメーターに興味があって目指そうとしている人、実際アニメーターになっている人には、いくつかの適性を持っています。
その適性とは、アニメが好きで絵を描くことが好きな人はもちろんのこと、責任感があり素直にアドバイスを受け入れられる人は向いているといえます。
アニメーションの制作には、多くの人が関わるため1つの納期が遅れると、その分全体の制作納期にズレが生じます。
また制作物に対して、監督や脚本家からのアドバイスを素直に受け入れて、柔軟に修正することができる人は、成長する可能性が秘められています。
そこで、アニメーターに向いている人を下記にまとめました。
【アニメーターに向いている人】
・アニメが好きな人
・絵を描くことが好きな人
・責任感を持って制作できる人
・素直にアドバイスを受け入れられる人
・コツコツと作業できる人
アニメーターの主な著名人
世界を代表するアニメ監督は、元々アニメーター出身であることが多いです。
作品を務める監督によって、描写や世界観が大きく異なり好みが分かれるのも醍醐味ですよね。
そこで、日本を代表するアニメーターの主な著名人を解説していきます。
宮崎 駿
みなさまご存知のジブリ作品を生み出し、日本を代表するアニメ監督になった宮崎駿さんです。
元々、漫画家を目指していましたが、アニメーション映画に感動しアニメーターとしてキャリアをスタートしています。
今や世界から評価され有名になった宮崎駿監督も実は、アニメーター出身と聞くと親近感が湧きますよね。
庵野 秀明
日本を代表するアニメ「新世紀エヴァンゲリオン」シリーズの監督、庵野秀明さんです。
他にも「風の谷のナウシカ」や「シンゴジラ」を監督し、数々の受賞歴のある庵野秀明監督も実はアニメーター出身です。
彼の描く爆発のエフェクトは「庵野爆発」と呼ばれるほど繊細で圧倒的な原画として評価されています。
新海 誠
まだ記憶にも新しい2016年に公開され爆発的な大ヒットで社会現象を起こした「君の名は。」の監督、新海誠さんです。
新海誠監督は、「切ない」「儚い」が代名詞になるほど、泣けて心に響く独特な世界観が特徴です。
日本のアニメーション技術を世界トップレベルまで押し上げ、実写と見間違えるような圧倒的な映像美を誇るアニメ界のなかでも屈指の監督です。
アニメーターになるには?仕事内容・給料・スキル|まとめ
いかがでしたでしょうか。
今回は、アニメーターになるには資格が必要なのか、どのような仕事内容なのか、気になる給料や必要なスキルなど解説させていただきました。
晴れてアニメーターとして働き始めたとき、報酬が安く長時間労働などの現実に思い描いていた夢とのギャップを受けて辞めてしまう人も少なくありません。
一人前のアニメーターになるには、地道な努力と多くの経験が必要になり、新たな世代のアニメーターが、未来のアニメ産業を支える基盤となります。
アニメーターに興味のある人、目指している人は一度チャレンジしてみてはいかがでしょうか。