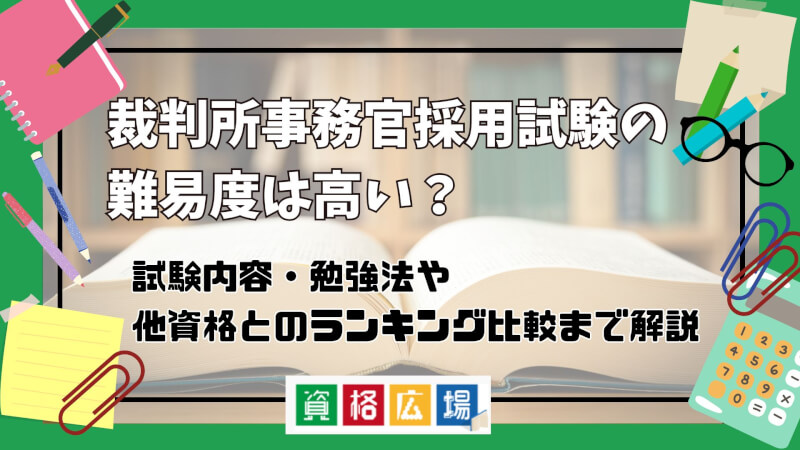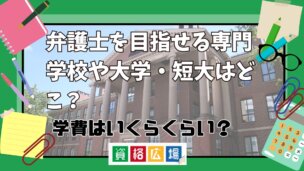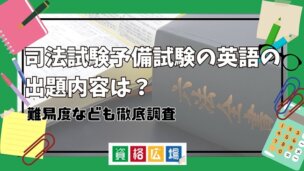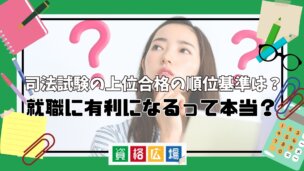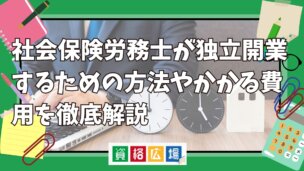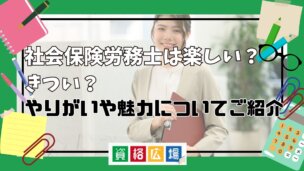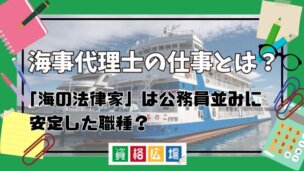裁判所事務官の採用試験について、合格率・偏差値・勉強時間の目安などを解説します。
裁判所事務官(裁判所職員)は、全国にある裁判所で働く職員のことです。
裁判所勤務といえば裁判官が思い浮かびますが、裁判官以外にも、裁判または裁判所の運営に関する様々な業務をおこなう仕事です。
司法試験・予備試験の通信講座・予備校おすすめランキング9選!料金費用の安さ・人気・評判を徹底比較【最新】
司法試験予備試験合格におすすめの通信講座
裁判所事務官の採用試験の難易度
倍率からも分かるように、裁判所事務官試験は、どの区分も非常に難易度の高い試験と言えるでしょう。
一般職試験は、総合職試験よりも難易度は若干低めといえますが、それでもかなりの倍率だといえるでしょう。
試験本来の難易度もさることながら、受験者数の多さもあり難関試験になっていることは間違いないと言えます。
裁判所事務官採用試験の倍率
令和5年度試験における各採用枠毎での倍率は次の通りです。
| 採用枠 | 倍率 |
|---|---|
| 総合職試験(裁判所事務官,院卒者区分) | 7.3 |
| 裁判所事務官(大卒程度区分) | 18.5 |
| 総合職試験(家庭裁判所調査官補,院卒者区分) | 8.4 |
| 総合職試験(家庭裁判所調査官補,大卒程度区分) | 7.4 |
| 一般職試験(裁判所事務官,大卒程度区分) | 3.6 |
| 一般職試験(高卒者試験) | 11.9 |
いずれにしても、高倍率の難関試験といえるでしょう。
裁判所事務官の採用試験合格に必要な勉強時間は1,000時間
裁判所事務官の採用試験合格に必要な勉強時間は、およそ1,000時間と考えましょう。
1,000時間は試験勉強の最低ノルマです。
余裕を持ちたい人は、1,000時間を上回る勉強時間を設定してください。
1日3時間の学習を1年間続けることで、目標の1,000時間はクリアできます。
裁判所事務官の採用試験概要
試験はもちろん日頃の業務にも、絶対に法律の知識が必要です。
さらに、一般社会での常識・マナーもしっかりと身に付けておく必要があるでしょう。
人々から信頼されるように、試験にも出題される幅広い知識が必要とされるのです。
裁判所事務官の資格は「裁判所」が運営管理を行っております。
裁判所とは:
司法権の行使を担う国家機関です。
裁判所事務官の採用試験は年1回
裁判所事務官の採用試験は1年に1回実施されます。
第一次試験が5月、第二次試験は6月(一般試験は5月)、第三次試験は7月に実施されます。
裁判所事務官採用試験の合格発表時期
各試験終了後、約10日から3週間程度で合格発表が行われます。
裁判所事務官の採用試験が難しいと言われる理由
裁判所事務官の採用試験が難しいと言われる理由をまとめました。
- 一般知能が重視される
- 専門記述が出題される
- 人物試験の配点が高い
各ポイントごとに理由をチェックしましょう。
理由①一般知能が重視される
裁判所事務官の採用試験では、一般知能が重視されます。
論理的思考力や情報処理力が求められるでしょう。
大学入学共通テストレベルの文章理解の問題です。
数的処理は数学的要素が強い試験内容と言えます。
基礎能力試験をクリアできなければ、裁判所事務官に採用されません。
理由②専門記述が出題される
専門記述では、憲法への理解が求められます。
憲法の重要基本論点から、テーマが出題されている試験です。
定義・趣旨を抑え、論述のコツをつかみましょう。
専門記述は、時間配分にも気を付けて学習を進めてください。
理由③人物試験の配点が高い
人物試験の配点が高いことは、裁判所事務官採用試験のポイントです。
人物試験の配点比率は10分の4を占めることに注意しましょう。
試験の対応で失敗をすると、挽回はほぼ不可能です。
配点にも気を配り、採用試験対策の優先度を決めてください。
裁判所事務官採用試験の難易度を他試験とランキングで比較
裁判所事務官採用試験の合格率をほかの士業と比べました。
| 区分 | 倍率 |
|---|---|
| 裁判所事務官 | 10%前後 |
| 検察官 | 25%前後 |
| 弁護士 | 41.50% |
| 警察官 | 16.50% |
| 税理士 | 18.40% |
| 弁理士 | 6.10% |
裁判所事務官の合格率は毎年10%前後です。
公務員のなかでも高難易度の採用試験ということが分かりますね。
裁判所事務官採用試験の科目
一次試験から三次試験まで実施されます。採用枠毎に以下の通りです。
| 試験区分 | 対象 | 試験項目 | 試験科目 |
|---|---|---|---|
| <総合職試験>(裁判所事務官) | 院卒、大卒 | 一次試験 | 基礎能力試験(多肢選択式)、専門試験(多肢選択式) |
| 二次試験 | 専門試験(記述式)「憲法」、論文試験(小論文)、政策論文試験(記述式)、人物試験 | ||
| 三次試験 | 人物試験 | ||
| <総合職試験>(家庭裁判所調査官補) | 院卒、大卒 | 一次試験 | 基礎能力試験(多肢選択式)、専門試験(記述式) |
| 二次試験 | 専門試験(記述式)、政策論文試験(記述式)、人物試験 | ||
| <一般職試験>(裁判所事務官、大卒程度区分) | 大卒程度 | 一次試験 | 基礎能力試験(多肢選択式)、専門試験(多肢選択式) |
| 二次試験 | 専門試験(記述式)「憲法」、論文試験(小論文)、人物試験 | ||
| <一般職試験>(裁判所事務官、高卒程度区分) | 高卒程度 | 一次試験 | 基礎能力試験(多肢選択式)、作文試験 |
| 二次試験 | 人物試験 |
第1次試験
裁判所事務官一般職試験の第1次試験は以下の通りです。
- 基礎能力試験(知能分野と知識分野)
- 専門試験(選択式)
知能分野は出題数が多く、全体的な配点比率も高いです。
基礎能力試験の知識分野は、2024年から時事問題中心の出題が増えました。
専門試験では、必須2科目と選択1科目の3科目が出題されます。
必須科目は憲法と民法の2種類で、選択科目は刑法か経済原論です。
第2次試験
第2次試験は、以下の3種類の科目に分かれています。
- 論文試験(小論文)
- 専門試験(記述式)
- 人物試験
論文試験(小論文)では、テーマに沿って教養論文を作成します。
専門試験(記述式)は憲法について一行問題が出題される傾向です。
人物試験、いわゆる面接の配点比率は高く全体の10分の4を占めます。
事前提出の面接カードに不備がないように記入し、内容を暗記してください。
裁判所事務官採用試験の勉強法
裁判所事務官採用試験の勉強法は以下のポイントがあります。
- テキストや過去問題集を活用する
- 論文は頻出テーマの答案を作成
- 模擬練習をなんどもくり返す
テキストや過去問題集を活用する
質の高い導入テキストや過去問題集がそろっているので、これらを揃えてひたすら問題演習に取りくむことが効果的な勉強法です。
裁判所職員を受験する人の半分くらいは独学、残りは公務員予備校にかよっています。
裁判所職員の教養試験と専門試験(多肢選択式)は、独学でも合格レベルまで得点力を高めることができます。
論文は頻出テーマの答案を作成
論文試験や政策論文試験の対策は、頻出テーマの答案を作成しましょう。
完成後に専門的なスキルがあるひとに添削してもらう方が効率的です。
論文には型があるので、正確に掴むまで挑戦しましょう。
模擬練習をなんどもくり返す
面接試験や集団討論試験は本番の形式で模擬練習をなんどもくり返すことが、合格への近道です。
面接は人物重視で判断がされます。
採用に近づくためには、言葉遣いや身だしなみにも気を使ってください。
裁判所事務官採用試験の独学合格が難しい理由
裁判所事務官採用試験の独学合格は難しいのでしょうか。
- 勉強スケジュールの管理が難しい
- その場で質問できない
- 面接のアドバイスがもらえない
以上のことから、無理な独学は避ける人が多いです。
結論から言うと、独学だけで学習を進めることは初学者にはおすすめできません。
独学が難しい理由①勉強スケジュールの管理が難しい
独学は勉強スケジュールの管理が難しいです。
初めにスケジュールを立てるときも、どんな計画が理想的かわかりにくいでしょう。
勉強の進捗についても、比較対象がいません。
自分一人だけの学習環境では、学習が遅れていても気づくのに時間がかかります。
独学が難しい理由②その場で質問できない
独学では講座の講師や予備校スタッフにすぐ質問できません。
その場で質問できないことで、学習が思うように進まないでしょう。
解説もテキスト頼みになり、理解が深まらないこともあります。
すぐ質問できない環境は、勉強するときにストレスになってしまいますね。。
独学が難しい理由③面接のアドバイスがもらえない
独学は、面接のアドバイスがもらえないデメリットがあります。
裁判所事務官採用の人物試験は、人間性や資質がチェックされます。
受験時は、態度や身だしなみも対策しなくてはいけません。
独学で挑むと、面接の対策が十分にできない可能性が高いです。
裁判所事務官の仕事内容
裁判所事務官は、裁判所等においてさまざまな事務処理を行い、裁判の円滑な進行と裁判所に務める人をサポートする仕事です。
勤務先は各地の裁判所や事務局です。「裁判部門」もしくは「司法行政部門」のいずれかに属して裁判事務を行っています。
具体的には、裁判部門では裁判所書記官のもとで各種書類の作成や送付、弁護士との打ち合わせなどを行い、司法行政部門では総務や人事、会計など、一般企業の事務職のような仕事を行います。
裁判所事務官の平均年収・給料
裁判所事務官の初任給は次の通りです。
- 総合職試験(院卒者試験) 24万円
- 総合職試験(大卒程度試験) 約21万円
- 一般職試験(大卒程度試験) 約20万円
- 一般職試験(高卒者試験) 約16万円
初任給は勤務地によって多少変わります。
上の金額は東京都23区内で勤務する場合のものです。
初年度の年収は、だいたい270万~390万くらいとなるでしょう。
公務員であるため、年齢とともに年収は徐々に上がっていきます。
裁判所事務官の現状と将来性
裁判所事務官は国家公務員ということもあり採用の倍率は高いですが、公務員ならではの安定職だと言うことができるでしょう。
現在の社会において裁判は欠かせないものであり、今後も裁判所事務官の仕事に対する需要はなくなりません。
その重要性も変わらないと考えられます。
業務は今後柔軟に変化する可能性がある
裁判所事務官の業務は、今後の環境により変わってくる可能性もあります。
特に近年は裁判員制度の導入、ロースクールの設立による弁護士増加の可能性、司法のあり方を問うマスコミ報道など、裁判をめぐる環境が変化を続けています。
また、職場によっては効率化を推進しているというところもあります。
そのため、安定職とはいえ非常に多くの仕事をこなす必要があるケースが多いと言えるでしょう。
裁判所事務官に向いている人
裁判所事務官の業務は多岐に渡りますが、事務的な仕事が中心となります。
そのため文書作成が苦にならないことが求められます。
特に、裁判所事務官は裁判に関わる仕事です。
場合によっては人の一生を左右する裁判の進行において大きな役割を果たさなければならないので、責任は重大でありミスは許されません。
そのため、几帳面かつ注意深い性格が求められます。
また、それだけではなく裁判所を利用する方の対応や弁護士との打ち合わせなど、人とのコミュニケーションが必要な業務が多く、他部署との連携も必須です。
そのため一人でコツコツと仕事をするタイプよりも、他者と協調して仕事ができるタイプの方が向いているでしょう。
裁判所事務官は安定性と稀少性を求める人におすすめ
裁判所事務官は多くのものが求められる難関職種ですが、それでも裁判官よりは低い難易度の試験となっております。
裁判官は難しいが、司法に携わりたいと考える人にとっては、おすすめの職種と言えるでしょう。
また、国の司法を支えるという面も、この仕事の大きなやりがいとなります。