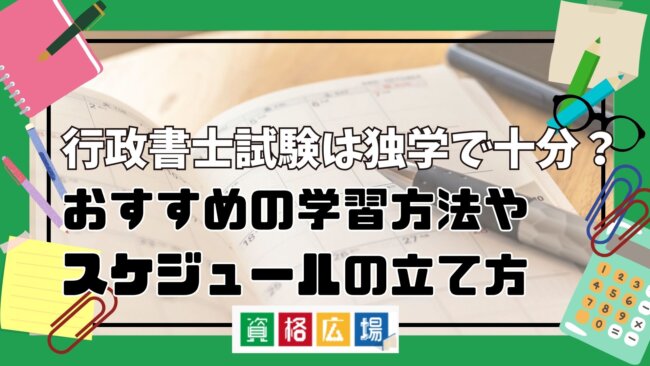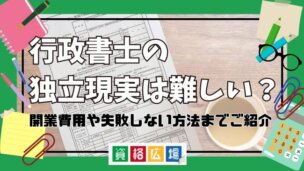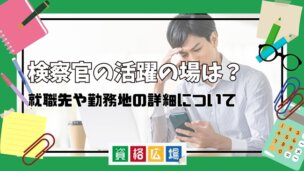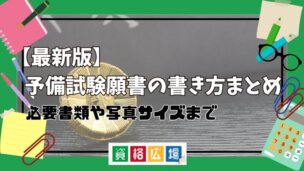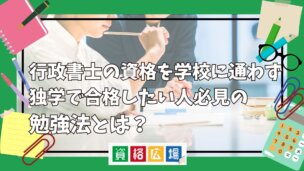「行政書士」試験合格を目指し、独学を始める方も少なくないでしょう。しかしながら、そもそも何から勉強を始めれば良いのか勉強方法が正しいのか悩み出すとキリがありません。
そこで本記事では、「行政書士試験を独学で合格するためのおすすめの学習方法やスケジュールの立て方、試験科目における対策の順番」についてご紹介します。
独学で合格を目指す場合には、徹底したスケジュール管理と出題傾向の把握や試験対策、時間の効率的な使い方が重要と言えます。
具体的な独学の学習方法について確認したい方は、ぜひ最後までお読み下さい。
行政書士試験におすすめの予備校・通信講座TOP3
独学で合格するには行政書士試験を理解する
独学で勉強を進める際には、初めに行政書士試験がどのような特徴を持った試験なのか理解する必要があります。
こちらでは、独学で合格するために最低限押さえておきたい行政書士試験の3つのポイントについてご紹介します。
- 試験範囲
- 配点
- 出題傾向
行政書士試験の特徴を理解し、効率良く対策を行いましょう。
参考書と問題集で試験範囲を理解する
まず初めに、行政書士試験対策に特化した参考書と問題集を用意し、試験範囲を確認しましょう。
試験範囲は大きく分けて、「法令科目」と「一般教養」の2つから出題されます。以下の表にて、試験科目をまとめたので参考にしてください。
| 法令科目 | 基礎法学 民法 憲法 商法 行政法 |
|---|---|
| 一般教養科目 | 政治・経済・社会 情報通信・個人情報保護 文章理解 |
また、注意点として、本格的な専門書を購入しないようにして下さい。専門書は該当分野の内容を全て網羅するため、試験範囲外の内容まで勉強することになりかねません。
「試験対策」と記載された参考書かどうか確認してから購入するようにしましょう。
行政書士試験の配点を確認する
行政書士試験の各科目における配点は同じではないので、重点的に対策を取るべき科目を事前に確認するようにしましょう。
以下の表にて、直近令和5年度の「行政書士試験合否判定基準」を参考に、各科目の配点をまとめました。
| 試験科目 | 配点 |
|---|---|
| 基礎法学 | 8点 |
| 民法 | 76点 |
| 憲法 | 28点 |
| 商法 | 20点 |
| 行政法 | 112点 |
| 政治・経済・社会 | 32点 |
| 情報通信・個人情報保護 | 12点 |
| 文章理解 | 12点 |
行政書士の試験というだけあり、行政法と民法など圧倒的に法令科目からの配点が高い傾向にあります。確実に合格するためには、法令科目の対策が重要と言えます。
過去問で出題傾向を掴む
過去問を使って出題傾向を把握することで、各科目の中で重点的に学習すべき範囲の理解に繋がります。
例えば、行政法では、行政手続法・行政不服審査法・行政事件訴訟法・地方自治法・国家賠償から毎年出題されています。
全ての範囲から出題されることはないので、効率的に学習するためにも必ず出題傾向を把握しましょう。
また、過去問を解くことで、苦手な科目が明確になるメリットもあります。
過去問は出題傾向の確認と対策を行うために重要と言えます。
行政書士試験を独学で合格するためのおすすめの勉強方法
独学で合格を目指す場合、参考書の1ページ目から順番に解き進めていては非常に効率が悪いです。
こちらでは、行政書士試験の特徴を踏まえ、「行政書士試験におすすめの勉強方法や勉強におすすめの順番」についてご紹介します。
優先度の高い科目から取り組むことで、手堅く合格を目指しましょう。
行政書士試験は何から勉強すると良い?
いきなり本格的な法律を学んだり条文を暗記するのは、法律初学者の中にはハードルが高く感じる方も多いでしょう。
抵抗感がある方は、生活に身近な法律である「民法」から取り組むと良いでしょう。民法は、馴染み深い条文もあり暗記科目でもないので、取り組みやすい科目と言えます。
また、同じく日常に身近な「一般教養」は、話題の時事問題から最新のIT技術まで幅広く対策しなければなりません。
そのため、1番初めに取り掛かり出すとキリがないため、重要度の高い法令科目の対策が疎かになる可能性もあります。
一般教養は、最後の方に後回しにするか隙間時間で勉強するのがおすすめです。
「民法」と「行政法」の配点は全体の6割
行政書士試験の配点にはバラつきがあることを先ほどご紹介しましたが、特に「民法」と「行政法」の2科目だけで全体の6割を占めます。そのため、これら2科目をしっかりと対策することで大幅に合格へ近づくことが可能と言えます。
以下の表にて、民法と行政法はどのような特徴があるのかまとめました。
| 試験科目 | 特徴 |
|---|---|
| 民法 | 1,000以上の条文と判例の知識を要する長文問題が出題される傾向にある 全部で11問出題され、法令科目の中で2番目に出題数が多い科目 |
| 行政法 | 法律用語と条文知識を問う問題が主に出題される 全部で22問出題され、行政書士試験の中で最も出題数が多い科目 |
上記を踏まえて、民法で高得点を狙うためには、法律用語を押さえた上で条文を理解しておくことが重要です。
一方で、行政法では、とにかく法律用語と条文の暗記を重点的に行いましょう。また、過去問演習を行うことで、確実に点数を稼ぐことができます。
上記を参考に、配点の高い民法と行政法の対策を念入りに行いましょう。
行政書士試験の勉強におすすめの順番
これまでに解説してきた配点や取り組みやすさを考慮し、行政書士試験の勉強におすすめの順番をご紹介します。
- 民法
- 行政法
- 憲法
- 基礎法学
- 一般教養
- 文章理解
- 情報
- 政治経済社会
- 商法・会社法
まず初めに、配点も高く比較的理解しやすい「民法」から取り組み、続いて配点が高い「行政法」を勉強します。この2つを時間的にも気持ち的にも余裕がある初めの段階で対策すると良いでしょう。
次に、法律の基礎ともなる「憲法」と「基礎法学」に取り組みましょう。
そして次に、「一般教養」の対策を行います。一般教養は、優先順位は低いものの、4割以下で不合格になる「足切り」が存在するので、隙間時間を活用し他の科目と並行して勉強を進めると効率的です。
最後に、法令科目の中では優先度が低めの「商法・会社法」に取り組みます。商法・会社法は、出題数が少ない割に暗記項目が多く広範囲なのでスケジュールに余裕があれば取り組むと良いでしょう。
以上、配点や取り組みやすさに基づいたおすすめの順番でした。上記をご参考に始めてみてくださいね。
行政書士試験の勉強時間とスケジュールの立て方
計画的に試験勉強を行わなければ、本試験直前期になり山積みの参考書に追われ苦労することになります。
後々後悔しないように、「行政書士試験の勉強に必要な時間と試験日から逆算したスケジュールの立て方」について理解しましょう。また、「隙間時間の重要性やスケジュールを立てた後のポイント」についてもご紹介します。
計画性を持ったスケジュールを組み立てることで、確実に合格を目指しましょう。
必要な勉強時間は500時間~1,000時間
行政書士試験に合格するために、必要な勉強期間はどれくらいでしょうか。
目安として、「合計500〜1,000時間確保」すると良いでしょう。具体的には、通信講座の場合は500〜800時間で済みますが、法律初学者が独学する場合には一般的に800〜1,000時間必要です。
推奨時間を達成するために、以下の2つが独学の学習パターンとして現実的と言えます。
- 毎日2〜3時間勉強する
- 平日は1時間程度で休日に5時間以上まとめてする
あくまでも目安ですが、通信講座や予備校に通学する場合と比較し、独学で行う場合には学習時間がかかることを覚悟しましょう。
試験日から逆算して計画を立てる
勉強に費やせる時間は限られているため、「試験日から逆算して計画的に勉強する」ことが重要です。
行政書士試験の本試験は、毎年「11月の第二日曜日」に実施されます。以下の表にて、独学を行う場合に試験日から逆算した学習時間を見ておきましょう。
| 本試験までの期間 | 1日当たりの学習時間 | 1週間当たりの学習時間 |
|---|---|---|
| 1年 | 約2.5時間 | 約17.5時間 |
| 10ヶ月 | 約3時間 | 約21時間 |
| 半年 | 約5時間 | 約35時間 |
| 3ヶ月 | 約10時間 | 約70時間 |
上記の表より、学習開始が早いほど、スケジュールに余裕があることがわかります。そのため、なるべく早くから試験勉強を始めるようにしましょう。
また、試験日から逆算すると、各科目に対してどれほど費やせる期間があるのかについても確認しておきましょう。ここでは、本試験当日の10ヶ月前から着手した例で解説します。
| 学習開始時期 | 試験科目 |
|---|---|
| 1〜3ヶ月目 | 民法・行政法 |
| 4〜5ヶ月目 | 憲法 |
| 6ヶ月目 | 基礎法学 |
| 7ヶ月目 | 一般教養 |
| 8ヶ月目 | 商法・会社法 |
| 9ヶ月〜10ヶ月 | 総復習 |
学習期間の前半は民法と行政法、憲法で消費し、後半は優先度の低い科目の勉強期間に充てます。また、最後の1,2ヶ月間は総復習を行えるように余裕を持ってスケジュールすると効果的です。
以上のように、試験日から逆算して学習開始時期や試験科目の学習期間などのスケジュールを決めましょう。
移動時間や隙間時間を利用する
行政書士試験日の当日まで思う以上に時間が無いと感じた方も多いのではないでしょうか。
そこで、まとまった学習時間以外にも、「移動時間や就寝前など隙間時間を有効活用」することでスケジュールに余裕を持たせることが出来ます。
例えば、毎日の通勤時間を行政法等の暗記科目に充てたり、就寝前の10分間で解けなかった過去問を1問復習するなど、隙間時間の活用はいくらでも考えられます。
スマホを触る時間やテレビを見る時間などを極力減らし、試験勉強の時間に充てましょう。
スケジュールは途中で調整する
残業が増え思い通りに学習が進まないことや、理解が進まず予定よりも大幅に時間をかけてしまうなど、当初決めたスケジュール通りに学習を継続することは困難と言えます。
そのため、「資格スクール 大栄」では、キャリアナビゲーターによる進捗管理サービスがあり、既定の学習スケジュールから遅れた場合に柔軟に調整してもらえます。
独学で勉強を進める場合には、自分でスケジュールを定期的に見直す必要があります。
独学以外の学習方法はなにがある?
独学での合格を目指す場合は、勉強時間や学習環境の確保、モチベーションの維持、適切なスケジュール管理など、学習における様々な障壁があります。
こちらでは、独学を含めた以下の3つの学習方法についてのメリットとデメリットをご紹介します。
- 独学
- 通信講座
- 通学制の予備校
改めて独学が最適な学習方法か考え直し、効率良く合格出来る方法を選びましょう。
独学のメリット・デメリット
独学は3つの学習方法の中で1番コストを抑えることができる魅力があり、独学で資格勉強を始める方も少なくありません。こちらでは、独学で学習するメリットとデメリットを理解し、自分に合った学習方法かどうか見極めましょう。
まず、独学のメリットを見てみましょう。
- コストを抑えて学習できる
- 時間や場所に縛られず好きなタイミングで勉強できる
続いて、独学のデメリットについてもまとめました。
- 質問できる環境がなく疑問点がすぐに解決できない
- 自分でスケジュール管理や教材選びをしなければならない
- モチベーションの維持を工夫しなければ挫折してしまう
独学での学習方法は、メリットよりもデメリットの方がどちらかと言えば多いと言えます。特に、質問環境やモチベーション維持など学習環境に関するデメリットが目立ちます。
独学で試験勉強を行う場合は、かなりの根気が必要であることを覚悟してください。
通信講座のメリット・デメリット
通信講座は、近隣に予備校がなく質に高い教材で試験対策を行いたい方におすすめの学習方法です。
通信講座には、2種類のタイプがあり、予備校の講義を通信講座形式で受講するタイプと通信講座を専門としているタイプが挙げられます。
どちらも通信講座だけで合格できるようにカリキュラムが組まれています。まずは、通信講座のメリットについてご紹介します。
- テキスト以外にもWebやCDなど、講義の受け方の選択肢が広がる
- チャットやメールなどで質問ができる講座もある
- 通学制の予備校と比較し、割安な費用で受講できる
次に、通信講座のデメリットについてもご紹介します。
- 講師や他の受験生と交流する機会がなく孤独感に陥りやすい
- 自分でスケジュール管理をしなければならない
- 原則として自習室の利用ができないため自宅で学習環境を整える必要がある
独学と比較し、質問環境やテキスト以外の講義スタイルを選べるなど、充実した学習環境が特徴的です。一方で、独学同様に、モチベーションの維持を工夫する必要があります。
本業が忙しく通学する余裕がない方や、地方で近くに予備校がない方におすすめの学習方法と言えます。
通学制の予備校のメリット・デメリット
最後にご紹介する通学制の予備校では、高額な費用をかける分、充実した学習環境が提供されています。
まず、通学制の予備校のメリットについて確認しましょう。
- プロの講師から質の高い内容を直接指導してもらえる
- 同じ志を持つ仲間とのつながりができるため高いモチベーションを維持できる
- 自習室が使えるため集中して勉強できる
一方で、以下のようなデメリットも挙げられます。
- 通学時間や費用がかかる
- 受講料金が高額なため経済的に圧迫される
通学制の予備校では、熟練の講師から直接合格のためのノウハウや最新情報を教えてもらえるメリットが大きいと言えます。独学や通信講座で挫折を味わい、通学制の予備校へ変更する方も少なくありません。
本記事を読み独学が難しそうだと感じた方は、通学制の予備校を利用すると良いでしょう。
効率よく合格を目指すならアガルート!

費用などの面でメリットのある独学ですが、最短ルートで合格を目指すのであればアガルートの通信講座を活用するのがおすすめです。
非常に多くのメリットが目白押しとなっておりますので、ぜひ最後までご覧ください!
大きな実績を残す通信講座
アガルートの通信講座の最大の特徴は効率性であり、講師が作成した見やすいフルカラーテキストと分かりやすい映像講義を通じて合格に必要な情報をスムーズにインプットできます。
受講者の方に合わせたコースが複数設定されているのも魅力で、法学を学んだことのない初学者の方でも安心した状態での学習が可能です。
アガルートは業界でも数が少ない実績を公表している通信講座となっており、初めて試験を受けた方であっても56.11%もの方が合格を掴み取っています。
令和5年度の全国合格率は13.98%であり、4.01倍を超える実績を持っているのがアガルートなのです。
受講しやすい制度が充実
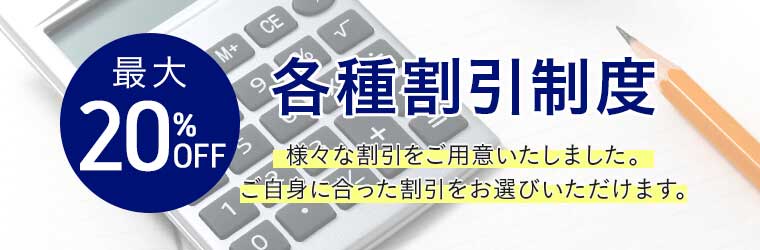
アガルートでは受講生の方が快適に学習できる様々な制度が充実しています。
学習面では講師に直接相談できる無料質問制度などが特徴的で、受講の中で生まれた疑問をすぐに解決することが可能です。
また金銭面でも嬉しい制度が充実しており、諸条件を満たすことで10%~20%割引で受講できる割引制度や最大で講座料金が全額返ってくる合格特典などが揃っています。
講座自体の完成度も非常に高く、こうした制度が拡充されていることもあって受講生の満足度はかなり高くなっているようです。
→アガルートの行政書士の評判・口コミを調査!合格率は42.14%!
まずは無料の受講相談を
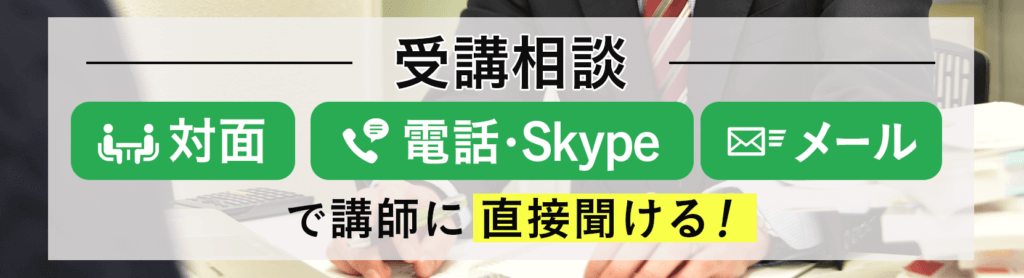
アガルートでは、講座の受講を迷っている方へ向けた無料受講相談を行っています。
行政書士試験に精通したアガルートスタッフと話すことで、講座や試験のことも含めたあらゆる疑問が解決できるはずです。
この受講相談は完全無料で開催されているため、講座の受講を少しでも考えているのであればお気軽にお申し込みください!
またアガルートの行政書士講座が気になった方は、ぜひこちらから公式サイトをご覧ください!
行政書士試験の学習方法まとめ
今回は、行政書士試験を独学で合格するために必要な勉強時間の目安やスケジュールの立て方、勉強方法について解説してきました。
法律初学者が独学する場合にはかなりの時間と根気を必要とし、モチベーションの維持やスケジュール管理に苦戦する可能性が高いと言えます。
一方本記事でもご紹介した「通信講座」や「通学制の予備校」では、スケジュール管理や参考書選定の手間がなく効率良く試験勉強を行うことが出来ます。
それぞれの学習方法のプラス面とマイナス面の両方を考慮し、効率良く合格を目指せる方法を選びましょう!