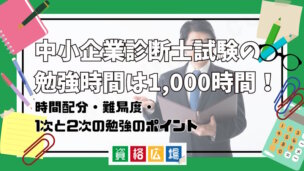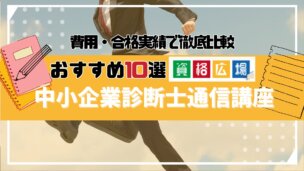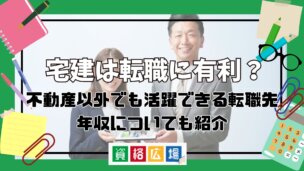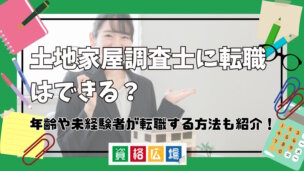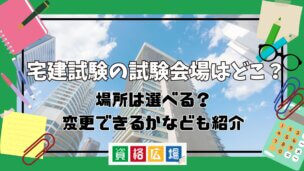宅建士。皆さんも一度は聞いたことのある資格だろうと思いますが、土地や建物などの不動産が関わるあらゆる場面において大変重要な役割を担っている職業です。
国家資格にもなっており実際に宅建士になるには宅建試験に合格しなければなりません。そのためには高度なスキルと知識の取得が絶対で、合格率が低いことでも有名ですよね。
一部では宅建試験の難易度は難化しているという噂もあります。
しかし実際は工夫すれば独学でも目指せる資格ですし、毎年合格者も非常に多く出ています。
それでは、本ページでは宅建試験の難易度についてや、難化しているという噂は本当なのか?等々のテーマで一緒に見ていきましょう。
宅建の試験概要や難易度は?

気になる宅建の試験概要ですが、出題範囲は主に民法、法令上の制限、宅建業法、その他関連知識の4つの分野から幅広い知識が問われます。
各出題範囲の配点及び合格点に関しては非公開ですが、受験者の中で上位15〜17%が合格のため毎回合格点は変動します。
他の国家試験に比べれば難易度はそれほど高くないと言えますが、日常生活においてあまり聞き慣れない法律や専門知識の習得が合格のカギとなるため、余裕をもって対策を練る必要があります。
全ての範囲を完璧に網羅しようとしても絶対に不可能です。そのため満点を目指すのではなく、まずは自分の得意分野から確実に得点を稼ぎ最低でも7〜8割り程度取れるほどの実力を付けることが合格のために必要となります。
要点を押さえて確実に大事なところから勉強することが重要です。難易度の高い要点対策や確実に得点を稼げる問題はどれなのかなどを効率よく勉強するなら通信講座などを利用するのもおすすめです。
どの程度勉強すればいい?
宅建士に関する一切の予備知識が無く、資格試験に慣れていない人を基準として、ゼロから挑戦して合格するまでにおよそ300時間程度の勉強時間は必要と言われています。
勉強しやすい教材の有無や、受験者本人の予備知識・実力次第でさらに少ない勉強時間でも合格できるとの見方もできます。
実際に、独学で50時間~100時間程度の勉強で宅建の試験を合格してしまったというような人も中にはいますし、通信講座などでは10月の試験に向けて、7月ごろから勉強し始めるようなスピード合格パックも存在します。
7月から10月までの3ヶ月となると、毎日2時間勉強すれば合計で少なくとも90日、180時間の勉強時間を取ることができます。
宅建試験の難易度は難化しているの?

宅建士は、もともとは宅地建物取引主任者(=宅建主任者)という呼ばれ方をしていましたが、平成27年に宅地建物取引士という名前に変わり、略称も宅建士となりました。
そのタイミングで、若干宅建試験の問題も難化したのでは?という噂が目立っています。
宅建試験の合格率だけ見れば、前述の通り例年15%~17%程度で、データ上は受験した人の8割以上落ちるなんてと言われると非常に難易度が高いように思えます。
宅建試験は受験者数が非常に多い
宅建試験は、学歴も不要で受験資格は一切ありません。
ですが宅建士は就職に役立つ、給料がアップするなどのメリットが全面的に一般的に知れ渡ってしまった資格であるため、受験者が20万人を超えるという事態になっています。
合格率15%は確かにそれだけで見れば難易度の高い資格に見えます。
しかし実際には20万人中の15%ですので、毎年3万人以上の宅建士資格保持者が新しく誕生している計算になります。
記念受験や熱意のない受験者も多い
もちろん、その受験者の中には、会社から資格を取れと言われて仕方なく受けに来る人や、あまりしっかりと勉強に取り組んでいなかった人なども多く混じっています。
厳しい受験資格を乗り越えてやっと受けることのできる資格試験のほうが、受験者の熱意の高さゆえに合格率が高く出るものです。
また、宅建試験に関しては実は相対評価で合格者を決定しています。
毎年30000人前後程度の合格者が出るように合格ボーダーが調整されており、その点数が例年だと50問中35~37問程度正解すれば合格できるというラインなのです。
つまりは受験者の成績が全体的に良ければ合格ボーダーは厳しくなり難化、熱意のない受験者が多い年は意外と楽に合格できる可能性があるという仕組みです。
受験者数が増えるにつれて合格者数だけがどんどん増えていくので、合格率自体も下げてくるのではないかとの噂が立っているワケです。
宅建士の合格ラインは?

宅建士の合格ラインの推移を見ればこの資格の難易度がみえてきます。
ここでは、宅建士の資格の合格ラインについて詳しくみて行きます。
宅建士の合格点の推移
過去4年間の宅建士の合格点の変容についてみていくので、参考にして見て下さい。
| 年 | 点数 |
|---|---|
| 令和3年度 | 34点 |
| 令和2年度 | 36点 |
| 令和元年 | 35点 |
| 平成30年 | 37点 |
上記が宅建士資格の合格点の推移となっています。
年によって多少のバラつきはありますが基本的に35点前後で推移しています。
宅建士の資格は50点満点なので、それの35点は約7割となっているので、宅建士の資格を点数だけで見ればそれほど難易度の高い試験ではないことが分かります。
合格率の推移
次に宅建士資格の合格率の推移を過去4回分の結果を見ていきます。
以下が過去4回分の結果を表した表となっています。
| 年 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
|---|---|---|---|
| 令和3年度(12月) | 39,814人 | 3,892人 | 15.6% |
| 令和3年度(10月) | 256,704人 | 37,579人 | 17.9% |
| 令和2年度(12月) | 55,121人 | 4,610人 | 13.1% |
| 令和2年度(10月) | 204,163人 | 29,728人 | 17.6% |
合格率があまり高くなく難関試験という印象を受ける方もいらっしゃるかもしれませんが、宅建士の資格は受験資格がないので誰でも受けることが出来ます。
よって、このような合格率になっている節目があるので、合格率の低さから悲観視するのは浅はかかもしれません。
これからの宅建士資格はどう変わる?

今まで宅建士のこれまでを説明してきましたが、これからの宅建士はどのようになっているのでしょうか。
民法大改正の影響を中心に見ていきます。
民法改正の概要
最初に民法大改正の概要について見ていきたいます。
民法大改正とは2017年に成立した民法の一部を改正する法律となっており、この民法大改正が2020年の4月から施行されます。
約120年間実質的な改正が行われていなかった民法が見直される運びとなりました。
変更目的としては、現在行われている裁判や取引の実務の基本的な法律を明確にするなどの目的が組み込まれています。
民法改正による影響は?
民法大改正によって出題範囲の変化が見られるので、学習の範囲や分野が変わってきます。
よって、独学で学習している方は的確な情報を得られない可能性があるので、他の通信講座や専門学校に通っている受験者と差がついてしまうことが予想されます。
民法大改正の試験の内容の変化は必ず抑えないといけないポイントなので、独学で行う人は注意しましょう。
過去問があてにならない
宅建士の勉強はこれまでずっと過去問が重要と言われ続けてきましたが、2020年の試験及びそれ以降数年にわたる試験では、問題や出題傾向などが分かってくるまでしばらくの間は、過去問に頼った勉強方法がなかなか成り立たないため、一時的に勉強を進めることそのものが難化することは避けられないというわけです。
宅建士を今目指そうかどうか迷っている人は、教材や過去問が充実している2019年中に、急いで勉強して合格をもぎ取ってしまった方が手っ取り早いのは間違いないでしょう。
宅建士対策ならアガルート

難易度が高い宅建士の資格が受かるか不安、独学で学習をするのが嫌という方は通信講座を利用するのがおすすめです。
アガルート通信講座は宅建士を始めとした、司法試験などの難関国家資格を専門に扱う通信講座となっています。
ここでは、アガルートの良さや特徴について紹介していきます。
圧倒的な合格率
アガルート通信講座は高い合格率を誇っているのが特徴としてあります。
宅建士のアガルート受講者の令和2年度の合格率は43.3%と全国平均の2.58倍と驚異の合格率を残しています。
これは、アガルート受講者の約2人に1人が宅建士の資格を合格していることになるので、アガルートの宅建士の資格対策のレベルの高さが分かりますね。
このように、アガルートは高い合格率を誇っているので成績が伸び悩んでいる方や合格率を上げたい方はアガルートの通信講座がおすすめです。
知識が0からでも合格を狙える
宅建士の資格を取ろうとしている方で知識0からでも合格が出来るのか不安に感じている方もいらっしゃるかもしれませんが、アガルートでは法、宅建士の知識が0でも合格を狙うことが出来ます。
それを可能とするのはアガルートの合理的なカリキュラムや、充実なフォローがあるためです。
確実に実力を伸ばして行くために、問題演習や過去問演習が効率的に、合理的に組まれています。
なので、宅建士初学者でも安心して学習を進めていくことが出来るので、アガルート通信講座はおすすめとなっています。
プロが監修している考え尽くされたテキスト
アガルートで使われている宅建士の資格のテキストはプロが監修しているため確実な情報を得ることが出来るのが特徴です。
また、アガルートでは過去問も一目で重要度が分かるようになっているので、優先順位を付けやすいので効率的に学習することが出来ます。
このように、アガルートの通信講座は魅力が多くあるので宅建士の受験を考えている方はアガルートを利用してみるのがおすすめとなっています。
宅建士の試験難易度と難化についてまとめ
宅建試験の難易度と、難化していることについての噂や情報をまとめました。いかがでしたでしょうか?
色々な視点から見て、今後宅建試験は少なからず難化していく可能性も高いと言えます。宅建資格がほしい人は、早めに合格してしまいたいところですね。
合格までの道のりは決して楽ではありませんが、宅建士資格は努力して取得するだけの価値はあります。
熱意をもって勉強すれば誰でも手にできる資格という事で、それだけの熱意がある人は、上位15%以内の点数を試験で取るべく専門学校や通信講座を利用している人も多いですよ。
アガルート通信講座では合格に一切の妥協のないカリキュラムが組まれているので、独学での学習が不安になった方や、興味がある方はアガルート通信講座を受講するのがおすすめです。