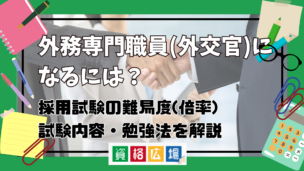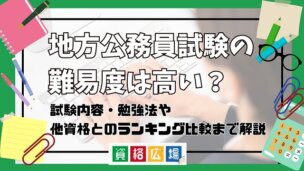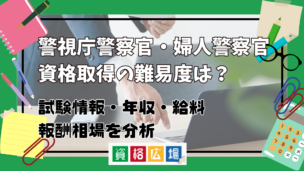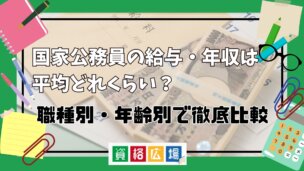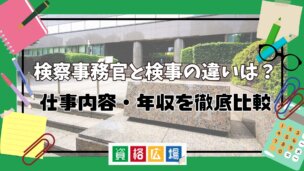国家公務員になるには国家公務員採用試験に合格し、採用予定機関で官庁訪問を行うことで内定獲得という流れになります。
ただし国家公務員には総合職か一般職かによって試験内容は異なります。
また国家公務員は高卒や大卒であっても受験科のであり、学歴による制限はありません。
ただし学歴によって試験区分が異なるため注意が必要です。
そこで今回は国家公務員になる流れや注意点などについてご紹介します。
これから国家公務員を目指す方はぜひ参考にしてみてください。
国家公務員と地方公務員の違いとは?どっちがいい?年収・試験難易度・仕事内容の違いをわかりやすく解説
公務員講座ならアガルート!
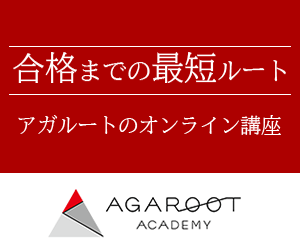
公務員試験合格を目指すならアガルートアカデミーがおすすめです!
アガルートでは、「地方上級」「国会一般職」「専門職」「裁判官」など、さまざまな公務員試験に対応したカリキュラムが用意されています。
通勤や家事の合間など隙間時間も活用することができるので、効率的に学習を進めることができる講座です。
国家公務員になるには
ここでは、国家公務員になるまでの一般的な流れについて紹介します。
希望する公務員の種類を決める
国家公務員といってもさまざまな種類があるため、まずは自分外貌する公務員の種類を決めましょう。
具体的には「財務省」「厚生労働省」「文部科学省」といった公官庁があり、さらに同じ公官庁であっても「総合職」「一般職」「技術職」など、さまざまな試験区分があります。
試験区分によって試験の内容や難易度が異なるため、事前に調べておくことがおすすめです。
また基本的に公務員試験は希望する省庁に関係なく共通の試験が実施されますが、「裁判所事務官」「国税専門官」「国立国会図書館」といった特定の業種は独自に試験を行っているため注意が必要です。
公務員試験を受ける
国家公務員の採用試験では1次試験として択一試験や論文試験が行われ、2次試験では面接が実施されます。(総合職の場合は記述式試験も追加されます)
国家総合職(大卒)の場合
国家総合職は毎年3月中旬に第1次試験が行われ、6月上旬に最終合格の発表といった流れになります。
さらに、6月中旬から官庁訪問が行われ、内々定を得ることができます。
具体的な試験内容としては第1次試験は筆記試験で基礎能力試験と専門試験(択一式)が行われ、第2次試験では専門試験(記述式)と面接試験が実施されます。
国家総合職は英語試験の得点によって加点されるため、TOEICなどの語学対策をしておくのがおすすめです。
国家一般職(大卒)の場合
国家一般職は毎年6月上旬に第1次試験が行われ、8月中旬に最終合格の発表があります。
1次試験の合格発表から最終合格までの期間に官庁訪問が行われるため、志望官庁の研究など早めの準備が必要です。
試験内容としては第1次試験が筆記試験で基礎能力試験と専門試験(択一式)が行われ、第2次試験では面接試験が実施され、判定が行われる流れです。
国家公務員試験は1次試験に合格した者のみが2次試験を受けることができる仕組みであり、試験日程が重ならなければ複数の公務員試験を併願することができるので併願する場合はスケジュールの調整が重要です。
官庁訪問
国家公務員試験では総合職と一般職のいずれにしても、国家公務員試験への合格の後に官庁訪問を行い内定を得なければいけません。
具体的には5年間官庁訪問を行う資格が得られますが、総合職と一般職で大きく異なるため注意が必要です。
たとえば総合職の場合、官庁訪問は人事院試験の最終合格発表後に行われ、最終的に内定を得るためには基本的に1つの官庁を4日間訪問することになります。
官庁訪問で問われる内容は、主にその省庁を選んだ理由とキャリアを選んだ理由です。
面接の形式も個別面接から集団討論まで多岐にわたります。
一方、一般職の場合は日程調整の都合により一次試験の合格発表後、最終発表の前に官庁訪問が行われます。
官庁訪問のスケジュールも総合職のように体系化されておらず、人気のある省庁では確実に訪問できるのは1つの庁に限られるケースもあります。
専門職について
国税専門官、財務専門官、労働基準監督官などの国家専門職試験は国家総合職や一般職と同じく人事院が主催していますが、試験日程は異なるため併願ができます。
例年、国家公務員の専門職については国家一般職試験の一週間前に実施されます。
試験内容は基本的に国家一般職と似ており、一次の筆記試験と二次の人事院面接が行われます。
国家専門職試験の一次試験は全て同じ日程で実施され、基礎能力試験の内容は共通です。
出題科目は国家総合職や一般職と同様で、基礎能力試験と専門試験は多肢選択式で行われます。
国税専門官・財務専門官・労働基準監督官それぞれの専門科目についてまとめると以下の通りとなります。
ただし年度によって替わる可能性があるため、人事院のサイトをチェックするようにしましょう。
| 国税専門官 | 【必須科目】民法・商法、会計学 【選択科目】憲法・行政法、経済学、政治学など9科目 |
|---|---|
| 財務専門官 | 【必須科目】憲法・行政法、経済学・財政学・経済事情 【選択科目】民法・商法、統計学、政治学・社会学など8科目 |
| 労働基準監督官A | 【必須科目】労働法、労働事情 【選択科目】憲法、経済学、社会学など7科目 |
国家公務員一般職試験(旧II種・III種)の難易度は高い?他資格とのランキング比較や合格率・偏差値・勉強時間の目安について解説
学歴別!国家公務員になるには
国家公務員になるには、学歴によっても試験区分などが異なります。
そこでここでは、学歴別に国家公務員を目指す方法についてご紹介します。
大卒の場合
国家公務員になるためには、大卒程度の試験に合格する必要があります。
国家公務員には、国家公務員総合職試験、国家公務員一般職試験(大卒程度)、および各種専門職試験が含まれます。
専門職試験には、皇宮護衛官採用試験、外務省専門職採用試験、国税専門官採用試験などがあります。
試験は各公庁で行われ、一部の試験は高卒程度のものもありますが、年齢制限によって受験できない場合もあるため、大卒程度の試験に合格することが重要です。
大学4回生の4月から6月に1次試験が行われるのが一般的であり、試験対策の期間を逆算してスケジュール管理を行うようにしましょう。
さらに1か月から2か月程度で2次試験が行われます。
ただし、試験日程は試験区分や年によって異なる場合があるため、人事院のホームページで毎年確認するようにしましょう。
高卒の場合
国家公務員一般職試験は大卒程度と高卒程度の区分があり、受験資格は年齢によって異なります。
高卒の場合は、「高卒程度」の試験を受験することになります。
専門職試験も同様に、高卒程度の試験が数多く開催されています。
代表的なものには「刑務官採用試験」「税務職員採用試験」「気象大学校学生採用試験」などが挙げられます。
受験のタイミングは、高校3年生の9月で、10月上旬に1次試験の合格発表があり、10月中旬に2次試験が開催されます。
ただし、1次試験の日程は変更になる可能性もあるため、事前に確認することが重要です。
社会人の場合
社会人から国家公務員になるには、「社会人経験枠」の区分で以下の公務員試験に合格しなければいけません。
- 国家公務員経験者採用試験
- 一般職社会人試験(係長級)
- 各種専門試験(法務教官A/B(社会人)など)
通常、1次試験は例年9月下旬から10月上旬に行われ、その後10月下旬に1次試験の合格発表が行われます。
さらに、11月上旬に2次試験が行われます。
ただし、試験日程は変動する可能性があるため、事前に確認することが重要です。
また、社会人であっても大卒程度の受験資格に該当していれば、以下の試験を受験することもできます。
- 国家公務員総合職試験
- 国家公務員一般職試験(大卒程度)
- 各種専門職試験
上記の試験を受験することで社会人からでも国家公務員に転身することができます。
国家公務員合格者の出身大学
人事院が発表する2024年度秋・2025年度春に行われた総合職試験の合格者における出身大学は以下の通りとなります。
| 大学名 | 合計 | 2024年度(秋) | 2025年度(春) |
|---|---|---|---|
| 東京大学 | 327 | 156 | 171 |
| 京都大学 | 171 | 59 | 112 |
| 早稲田大学 | 123 | 47 | 76 |
| 慶應義塾大学 | 89 | 17 | 52 |
| 東北大学 | 89 | 37 | 72 |
| 北海道大学 | 88 | 12 | 76 |
| 中央大学 | 70 | 14 | 58 |
| 大阪大学 | 66 | 12 | 52 |
| 立命館大学 | 64 | 5 | 62 |
| 東京かがく大学 | 57 | 12 | 54 |
| 筑波大学 | 50 | 3 | 3 |
参照:人事院
上記のように国家公務員の総合職は国公立や難関私立出身者が多い傾向にあります。
大学名で判断されることはないものの、合格者はかなりレベルが高いことがわかります。
また、国家公務員総合職試験の場合、試験区分が「政治・国際」「法律」「経済」「人間科学」とあるため、法学や政治学、経済学を学べる大学・学部に進学して公務員を目指す方もいます。
もし国家公務員の総合職を目指すのであれば、大学選びも重要なポイントとなるでしょう。
国家公務員試験合格には1,500時間の学習時間が必要
国家公務員になるには国家総合職試験や官庁訪問をクリアしなければいけません。
春の試験に向けて準備を進める場合、合格に必要な学習時間は一般的に約1,500時間とされています。
1,500時間を1年間で学習する場合、週に28時間、1日あたり4時間の勉強が求められます。
またもし2年間をかけるのであれば、週14時間の学習が必要だといわれています。
たとえば平日は隙間時間を利用して1.5時間勉強し、土日のいずれかに4時間を確保し、もう1日は予備日として設けるというのが現実的なスケジュールでしょう。
もし新卒で入庁を目指す場合、大学2年生の春から2年間をかけて計画的に学習を進めるのが最も効果的です。
国家公務員を目指す際の注意点
ここでは、国家公務員を目指す際の注意点についてご紹介します。
公務員試験には年齢制限がある
国家公務員試験は全ての区分に年齢制限があります。
大卒程度の試験では多くが30歳までの受験資格とされています。
経験者採用試験でも40歳未満を対象とする試験があり、年齢制限は緩やかではないため、受験資格について理解する必要があります。
面接対策が必要となるケースがある
国家公務員の採用試験では、最終合格が採用とは限りません。
総合職試験や一般職試験では、採用試験とは別に官庁訪問で内定を得る必要があります。
専門職試験でも公務員試験以外に採用面接が行われることが多く、最終合格しても内定が出ない場合もあるため注意が必要です。
したがって、官庁訪問の面接対策が非常に重要となっています。
併願するのがおすすめ
公務員試験において重要なポイントのひとつは併願を行うことです。
公務員試験は試験範囲が共通している場合が多いため、併願は保険や予行練習として有効です。
大卒程度の場合だと、国家公務員総合職、国家公務員一般職、地方上級、東京特別区、国家公務員専門職などが主な併願先となります。
興味があるかどうかに関わらず、併願することで後々の選択肢が広がるメリットもあるのでぜひ検討してみてください。
国家公務員とは
国家公務員は司法府・立法府・行政府で活躍する公務員です。
行政府では国家の中枢で政策の企画立案に携わる国家総合職、各府省庁や地方機関で政策立案を支える国家一般職、この他に国家専門職などがあります。
また立法府では、議会を円滑に運営するための衆議院、参議院職員、司法府では裁判所事務官などが国家公務員として活躍しています。
司法職には裁判所事務官と家庭裁判所調査官が挙げられ、裁判所事務官は裁判所で事務をする傍ら、裁判官と協力して法廷の運営などをします。
国家公務員には地方検察庁や法務局、労働局などの出先機関の仕事に対して、霞ヶ関の1府12省庁の仕事(本庁とも呼ばれる)があります。
具体的には内閣府、復興庁、防衛省、総務省、法務省、外務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省がこれにあたります。
出先機関の仕事が実に多様な仕事であるのに対して、この本省庁は異なる官庁でも比較的似ているのが特徴です。
おもな仕事内容としては議会対応や予算組み放逸案の作成などであり、残業時間や忙しさなどは省庁によって異なります。
それぞれの職種の仕事についてまとめると以下の通りとなります。
| 国家総合職 | 一般的に「キャリア官僚」と呼ばれる職種。政策の企画・立案・調査・放置湯の制定や改廃などを担当する。 |
|---|---|
| 国家一般職 | 各省庁や地方支分部局に配属し、行政業務を担当。 |
| 国税専門官 | 法律・経済・会計等の専門知識を活かして国税調査官、国税徴収官、国税査察官といった職種に分かれて仕事をおこなう。主に国税局や税務署で働く。 |
| 財務専門官 | 財務局、財務省、金融庁等の本省庁と地域の双方で活躍し、国有財産の管理運営を行う。 |
| 労働基準監督官 | 労働局や労働基準監督署で勤務し、労働基準関係法令に基づいて始動もしくは働く人の安全や健康を確保する。 |
| 外務省専門職員 | 高い語学力を生かし、外交の現場で活躍する国家公務員専門職のひとつ。特定の国に従事し、条約・経済・経済協力・軍縮・広報文化などで専門性を発揮。 |
| 裁判所職員 | 裁判所職員は職種が大きく裁判所事務官、家庭裁判所調査官に分かれ、裁判所事務官は、各裁判所の裁判部や事務局に配置、家庭裁判所調査官は糧に関する問題解決にかかわる調査や調整を行う。 |
| 法務省専門職員(人間科学) | 法務省における人間科学の知識が必要な官職に従事する職員で、矯正心理専門職区分、法務教官区分、保護観察官区分の3区分で分けられ、調査やカウンセリング、指導、教育をおこなう。 |
| 防衛相専門職員 | 防衛省専門職員は防衛省に所属し、本省内部部局や陸海空の自衛隊、情報本部で日本の安全保障を支える仕事。 |
| 国立国会図書館 | 国会と同じ立法府に属する国立国会図書館に所属する職員。主に国会活動の保佐や資料・情報の収集、情報資源の利用提供などをおこなう。 |
| 衆議院・参議院事務局 | 衆参両議院内の事務を担当。資料作成や関係者との連絡調整、さらに議員立法の立案起草のための調査や議員秘書に関する業務や広報などもおこなう。 |
国家公務員の年収
国家公務員の年収は職種や経験年数によって異なるものの、本府省勤務の場合だと約550万~570万、係長級・課長補佐級だと約730万~930万円となっています。
これを基に月給を算出すると、国家公務員の平均月給は約41万円と推定され、民間企業の平均月給の約1.5倍に相当し、民間企業の中では非常に高い水準の給与であると言えます。
さらに、国家公務員は各種手当が充実しており、扶養手当、地域手当、通勤手当、特殊勤務手当、管理職手当、時間外手当などが基本給に加算されます。
国家公務員の中でも最高位に位置する事務次官や官僚(事務職)の場合、年収はさらに大幅に増加します。
人事院が発表した令和6年度の国家公務員モデル給与例によれば、事務次官の月給は141万円に達するというデータもあります。
国家公務員のキャリア
昇進の速度は官庁によって若干の違いがあるものの、一般職に比べて総合職の方が圧倒的に早い傾向があります。
最初は係員からスタートする点は共通していますが、係長への昇進は総合職は4~5年目からできますが、一般職では7~8年目が必要だといわれています。
また、課長補佐への昇進には総合職で7~9年、一般職では17~20年程度の時間がかかります。
国家公務員においては本省課長級以上を幹部と呼びますが、一般職で幹部に昇進することは稀です。
一方、総合職では17~20年目以降に課長級以上に昇進することが可能であり、その後も能力に応じて昇進のチャンスが大きく広がります。
事務次官を含む幹部職員の大半は総合職から選ばれるため、将来的なキャリアアップを目指す方には総合職を推奨いたします。
公務員試験講座ならアガルートアカデミーがおすすめ!

公務員試験合格を目指すならアガルートアカデミーがおすすめです!
フルカラーで見やすいテキスト教材と分かりやすい動画講義で、初めて資格勉強をする方でも充分合格が目指せるカリキュラムになっています。
合格者には受講費全額返金orお祝い金3万円の特典もあるのでモチベーションの維持も期待できます!
最短ルートで合格が目指せる!
アガルート公式HPはこちら
国家公務員試験の合格率
| 試験名 | 申込者数 | 1次試験合格者数 | 最終合格者数 | 合格率 |
|---|---|---|---|---|
| 総合職試験(院卒者試験) | 1,350人 | 1,057人 | 668人 | 49.5% |
| 総合職試験(大卒程度) | 12,249人 | 10,141人 | 1,285人 | 10.5% |
| 一般職試験(大卒程度) | 24,240人 | 17,463人 | 7,557人 | 31.2% |
| 国税専門官採用試験(大卒程度) | 12,161人 | 5,910人 | 3,358人 | 27.6% |
| 一般職試験(高卒程度) | 9,681人 | 4,269人 | 3,132人 | 32.3% |
参照:2024年度国家公務員採用一般職試験(大卒程度試験)及び専門職試験(大卒程度試験)の申込状況について
2024年度の国家公務員試験において合格率が1番低い総合職試験(大卒程度)では10.5%、1番高い総合職試験(院卒者試験)でも49.5%とかなり合格率に幅があることがわかります。
一般的に一般職よりも総合職の方が難易度が高い傾向にあり、出身大学も東大など難関大学出身者が多いといわれています。
国家公務員採用試験の最も難しい部分は、一次試験で行われる筆記試験です。
合格基準点は試験の種類によって異なりますが、一般的には教養試験と専門試験の両方で約7割の正答率を目指すことが求められています。
また国家公務員採用試験の出題範囲は非常に広範囲にわたることも難易度が高い理由として挙げられます。
国家公務員試験を突破するには効率的な学習が重要であり、頻出問題に焦点を当て、得点源を増やすのがポイントです。
国家公務員を目指すならアガルート

今回は公務員の種類や仕事内容、向いている人の特徴などについて紹介してきました。
公務員といってもさまざまな種類があり、それぞれなり方や仕事内容が異なります。
いずれにしても公務員になるには、各試験に合格しなければなりません。
公務員試験は範囲が広く、さらに二次試験と呼ばれる面接があるため十分な対策が求められます。
難関資格の合格実績のあるアガルートでは、公務員試験対策の講座を開講しているので、独学での対策が不安な方にはおすすめです。
実力はの講師陣夜指導や手厚いサポート、充実したオリジナルテキストはアガルートにしか出せない持味で、大きなアドバンテージになってくれるはずです。
アガルートでは合格特典やお得なキャンペーンも実施されているのでぜひチェックしてみて下さい。