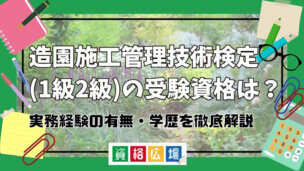害獣駆除には、高い特殊性と高額な報酬といった魅力があります。
しかし、駆除には資格取得が必要となり、未所持のまま狩猟を行うと自治体からの報酬金は貰えません。
その必要な資格というのが「狩猟免許」なのですが、これらには「網漁免許」、「わな猟免許」、「第一種銃猟免許」、「第二種銃猟免許」の4種類があります。
4種類の中から今回は「第一種銃猟免許」と「第二種銃猟免許」の2つに特化してお教えします。
そして資格取得後に必要な診断書や、試験合格率、取得にかかる費用なども書いてあるので、ぜひご覧ください。
「第一種銃猟免許」と「第二種銃猟免許」の違い

「第一種銃猟免許」と「第二種銃猟免許」の違いは、使用できる銃の種類にあります。
が、第二種銃猟免許を取得すれば、「空気銃」のみが使用でき、第一種銃猟免許を取得すれば「装薬銃」と「空気銃」の両方が使えるようになります。
装薬銃とは
実は、猟銃と呼ばれているのは第一種銃猟免許で使用が可能になる装薬銃のみとなっています。
火薬が爆発した際に発生するガスの圧力で弾を発射させるのですが、猟銃には『散弾銃』と『ライフル銃』が用いられることが主です。
「散弾銃」は原則として弾数が多く、弾のサイズも小さめです。
主に狩猟やクレー射撃に使われており、狩猟では、飛んでいる鳥やスピードのあるものを狙撃するのに適しています。
「ライフル銃」は銃の内側に螺旋状の溝が(ライフリングといいます)が刻まれており、発射時に弾が回転しながらまっすぐに飛ぶような仕組みになっています。
鹿や熊などの大型生物を仕留めるのに使われ、その威力も凄まじいものとなっているので、使い方次第では大変危険になります。
空気銃とは
「空気銃」とは、火薬を使わずに、空気やガスの圧力を利用して発射する銃です。
「ライフル銃」と同様、こちらにもライフリングがあり、「エアライフル」とも呼ばれています。
基本的には、木の枝にとまっていたり、畑で餌を食べているような鳥を狙撃するために使われています。
取得方法について
狩猟免許の取得には、各都道府県に狩猟免許の申請を行い、試験に合格しなくてはいけません。
しかし、猟具や鳥獣、法令などの知識や、猟具の扱い方を知らないと合格は難しいので、各都道府県猟友会支部によって、この試験の1か月ほど前に予備講習が開催されています。
この予備講習の申し込み先は各都道府県猟友会のウェブサイトで確認してください。
狩猟免許試験への申込
狩猟免許試験の開催日時は地域によって違います。
各都道府県によって公開されているのでそちらで確認していただき、申請書等は各都道府県の自然環境行政担当部局に提出してください。
狩猟免許の更新は?
有効期間はおよそ3年間で、更新は区分ごとに更新料がかかります。
合格率はどれくらい?

狩猟免許の合格率はおよそ80%ほど。決して難易度が低いわけではありません。
試験内容について
■知識試験■…正答率70%以上で合格
1、法令や狩猟免許制度等に関する問題
2、猟具の種類や取扱に関する問題
3、狩猟鳥獣や狩猟鳥獣と間違われやすい鳥獣の生態などに関する問題
4、個体数管理の概念等、鳥獣の保護管理に関する問題
■適性試験■
1、視力の検査
2、聴力の検査
3、運動能力の検査
■技能試験■…70点以上で合格
1、鳥獣の判別問題
2、猟具の取り扱い問題
3、目測の問題
免許取得したそのあとは?
狩猟免許の取得だけでは、猟銃を手にすることはできません。
都道府県公安委員会に「鉄砲所持許可証」の取得が必要となります。
警察署を訪ね、複数の手続きが必要となりますので、講習や許可申請等に関しては、住所地の警察署にお問い合わせください。
猟銃等講習会(初心者講習)
まずは初心者講習である猟銃講習会を受講し、講習終了後に試験を受けます。
試験時間は60分で、問題は〇×形式となっております。
狙撃練習
試験に合格しますと、講習修了証明書が交付され、その後狙撃練習の申し込み手続きに進めます。
なお、「空気銃」の場合は、狙撃練習を受けずに「空気銃所持許可証」を申請することができます。
講習では銃の分解や組み立て方などが学べ、実技試験では実際に銃を撃ちます
狩猟免許取得に必要な『診断書』って?
「狩猟免許」で検索すると「診断書」と出てくるのにお気づきになったとは思いますが、ではその「診断書」とはいったい何なのでしょうか?
どうやら、猟銃等、銃器所持許可のためには病院からの診断書が必要のようです。
診断書を作成できる医師の資格の限定
平成21年12月に銃刀法の改正が行われ、猟銃等の所持許可に関わる診断書を作成できる医師の資格が限定されております。
「精神保健及び精神障碍者福祉に関する法律」第18条第1項に規定する精神保健指定医と、都道府県公安委員会が認める医師が診断書の作成が行えます。
診断書の費用は?
病院によって異なる場合がありますが、診察・検査・診断書などで5,000円以上はかかるみたいですね。
診断書作成は各病院によって異なりますので、その病院の指示に従って作成してください。
狩猟を開始するための費用はいくらかかる?
狩猟を開始するにはそれなりに費用が掛かります。
実際にどのくらいの費用が掛かるのかまとめてみました。
免許取得にかかる詳しい内訳
●狩猟免許取得費用● 各5,200円
●猟銃等講習会の受講料● 約10,000円(各都道府県によって異なります)
●試験申請のための医師の診断書● 約3,000円(病院によって異なります)
鉄砲所持許可にかかる費用
●初心者講習会手数料● 6,800円
●鉄砲所持許可申請手数料● 15,000円
●申請のための医師の診断書● 約3,000円
●住民票や各種提出書類● 約1,000円
※猟銃(散弾銃)の場合はさらに下記の費用も掛かります
●教習資格認定申請手数料● 8,900円
●火薬の譲受許可申請手数料● 2,400円
●射撃教習受講料● 約30,000円(射撃場によって異なります)
●射撃教習のための弾代● 約3,000円
税金、猟友会費等
●狩猟者登録手数料● 1,800円(各都道府県によって異なる場合があります)
●狩猟税● 第一種…16,500円 第二種…5,500円
(手数料や狩猟税の納付は、登録する各都道県ごとに必要です)
●猟友会会費● 年間約10,000円
●狩猟者登録のためのハンター保険費用● 約5,000円(条件により金額が異なります)
道具類の内訳
●散弾銃● 新品…約100,000円~
中古…約50,000円~
●空気銃● 新品…約200,000円~
●弾代● 鳥・小型獣用の散弾銃1発…約80円~ 空気銃1ケース(約200発程度)約3,000円~
●わな● くくりわな…約5,000円~ 小型獣用箱わな…約10,000円~ 大型獣用箱わな…約50,000円~
他にもウェアや道具も必要となります。安全用の長靴や手袋、止め刺し用のナイフ、双眼鏡など、手ごろなものであればざっと10,000円程度でしょうか。
第一種銃猟免許を取得するとしたら、免許取得代や道具類を含め20万以上かかりますし、第二種銃猟免許であれば25万円以上になります。
なかなかに高額ではありますが、近年では新規の狩猟免許取得者に補助金を交付する地域も増えております。
補助金の金額や条件は地域によって異なりますので、各都道府県のウェブサイトなどでご確認ください。
猟銃免許取得方法のまとめ
今回は銃猟免許に関してまとめました。
いかがでしたでしょうか、思ったより費用が掛かる?興味深い?
経験と気力がないとなかなかお金を稼ぐのは難しいと思われます。
合格率は決して高くなく、資格取得を目指すことができます。
大変危険な仕事ですが、やりがいはありそうですね。マナーを守って是非充実したハンター生活につなげてください。