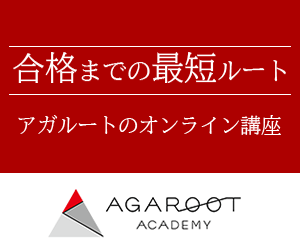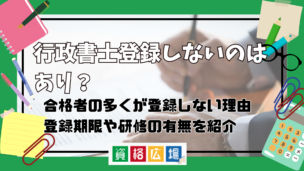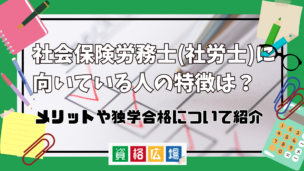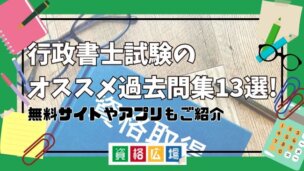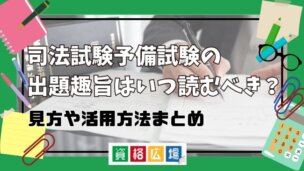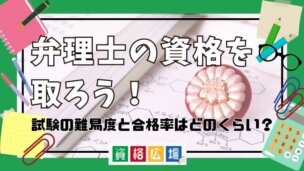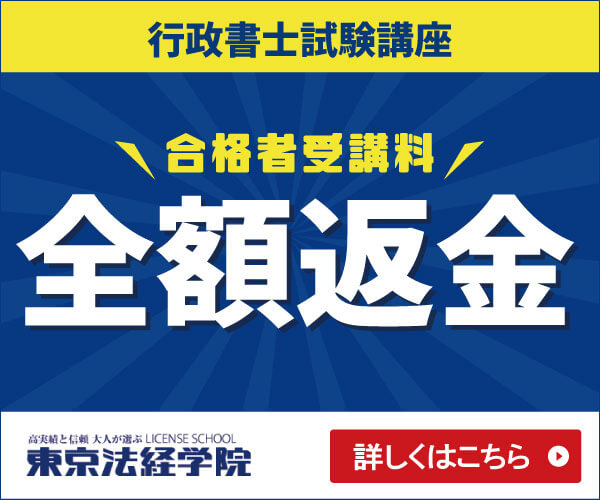合格率10%前後と超難関資格の1つに数えられる行政書士試験ですが、合格するためにはいったいどれくらいの勉強時間が必要なのでしょうか。
また、どのような勉強法を使えば合格しやすいのか気になる方も多いと思います。
この記事では、行政書士試験の受験を検討しているがどれくらい勉強しなくてはならないか気になる方のために、行政書士試験合格に必要な勉強時間や勉強を始める時期、オススメの勉強法について紹介します!
行政書士試験にチャレンジしたいと考えている人は必見です!
行政書士試験におすすめの予備校・通信講座TOP3
行政書士試験合格のために必要な勉強時間

行政書士試験に合格するためには多くの勉強時間が必要と言われますが、実際どのくらい必要なのでしょうか。
試験合格者の平均勉強時間を知っておくことでどのくらい勉強をすればいいのかの目安が分かります。
また、「学習が間に合わない」ということを防ぐためにも、自分の予定と照らし合わせながら無理のない勉強スケジュールを組むことは合格法として非常に重要です。
行政書士試験合格者の平均勉強時間
様々なWEBサイトで行政書士試験の勉強時間に検索すると、合格するために必要な勉強時間はサイトごとに大きな開きがあります。
これは、行政書士試験の合格には幅広い法律の知識が必要な上、その人の実力によっても勉強時間が変わってくるからです。
法学部や行政書士以外の法律関連の資格を取得したことがある人は、全く法律について勉強した経験がない人に比べて勉強時間が少なく済みます。
法律について学んだことがある人、ない人それぞれの勉強時間を分けてご紹介すると行政書士の勉強時間は下記のとおりです。
- 法律について勉強したことがある人:500〜600時間程度の勉強時間が必要
- 初めて法律について勉強する人:800~1,000時間程度の勉強時間が必要
独学で勉強するかどうかにも左右されるので上記の時間はあくまでも目安と考えてください。
ただし、かなり長い勉強時間が要求されることからも行政書士試験の難易度を窺い知ることができます。
独学だとさらに時間がかかる場合も
行政書士試験を独学を目指す場合、出題範囲や傾向がわからず効率的な勉強ができないため上記より更に多くの勉強時間が必要です。
また、わからないところがあってもわからないままになってしまったり、間違った内容を覚えてしまう可能性もあります。
しかし、独学の合格者は実際にいらっしゃいますので、不可能というわけではありません。
しっかりとスケジュールを組み、模擬試験や勉強に役立つサイトなどを活用して挑みましょう。
他の難関資格との勉強時間の比較
他の難関資格に求められる勉強時間と行政書士試験の勉強時間を比較することでより具体的な難易度の感覚がつかめると思います。
ここでは他の難関資格に合格するのに必要な勉強時間をご紹介します。
他の難関資格に合格するために必要な勉強時間は以下の通りです。
- FP2級:150~300時間程度の勉強時間が必要
- 宅建士:200~400時間程度の勉強時間が必要
- 行政書士:500時間~1,000時間勉強時間が必要
- 社労士:1,000時間程度の勉強時間が必要
- 中小企業診断士:1,000時間程度の勉強時間が必要
- 司法書士:3,000時間程度の勉強時間が必要
他の難関資格の勉強時間と比較すると行政書士が極めて長い勉強時間を必要とする資格ではないように感じられますが、かなり幅広い範囲から出題されるため決して簡単に取れる資格ではありません。
上記の時間は1年で合格できた時の勉強時間
行政書士試験は他の資格と比較的平均な勉強時間が必要ですが、もちろんそれは1年で合格できた時の勉強時間です。
もしも1年で合格できたなかった場合は翌年の試験を受験する必要があり、あらためて対策を取る必要があるのでさらに勉強時間を要します。
確実に1年で合格したいなら、通信講座や予備校を利用するなどして効率的な勉強法と徹底した試験対策をすることをオススメします。
行政書士試験の勉強を始める時期は?
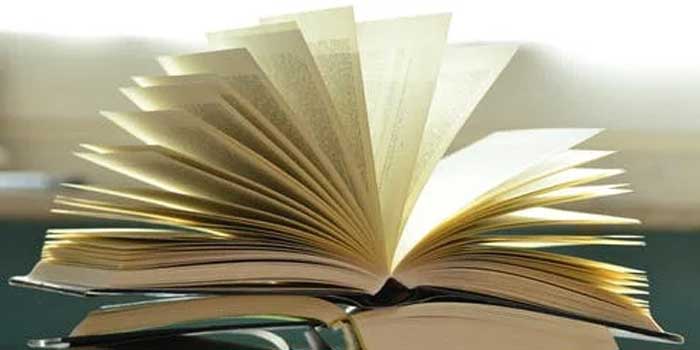
行政書士資格を取得したいと思っても、どのタイミングで勉強を始めるのが最適なのでしょうか?
行政書士試験は年に一度しか開催されないため、資格を取りたい!と思ったタイミングによっては今年受験するか翌年の試験に向けてしっかり勉強するか悩むこともあるのではないでしょうか。
例年通り11月の第二日曜日に開催されることを前提に、適切なタイミングかを紹介します。
あくまで目安なので、自分の性格や勉強法を考慮して参考にしてみてください。
11~1月
行政書士試験に合格した多くの方が11~1月ごろから勉強を始めているため、適した時期と言えます。
試験当日まで約1年ほどの勉強期間があるので余裕をもって勉強を進めることができるでしょう。
自分に合った勉強法で、合格に向けて勉強を始められます。
2月~5月
2~5月ごろに勉強を始める場合、少し時間に余裕は無くなりますが合格を目指せる範囲です。
しかし、試験日に近ければ近いほど休みなく勉強をする必要があり、進捗や理解度を加味しながらスケジュールをその都度組みなおすなど勉強以外の工夫も必要になってきます。
そのため、勉強時間が少ないことが不安な方は翌年の受験を目指すのが良いかもしれません。
本命を翌年として、本番の会場や雰囲気を確認するためにその年の行政書士試験を受けてみるのも良いでしょう。
6~10月
6~10月ごろに勉強を始める場合は、翌年の行政書士試験を目指したほうが良いでしょう。
行政書士試験目前のため、合格するために必要な勉強時間を確保するのは難しいです。
また、初学者だと内容を理解するだけでも時間がかかるため、合格は厳しいと言えます。
翌年の試験合格を目指すのであれば、長めに勉強時間を確保できるので余裕をもって勉強ができます。
しかし、勉強期間が長いとどうしても中だるみしがちです。
長期間の勉強スケジュールを組むのが不安な場合は、最初は行政書士の勉強に軽く触れる程度にとどめておき、11月ごろから本格的に始めるのがおすすめです。
行政書士試験合格のための効率的な勉強法

独学での行政書士試験突破は不可能ではありませんが、やはりオススメな勉強法は予備校や通信講座といった資格試験対策のプロのもとで学習をする勉強法です。
予備校、通信講座は試験の出題傾向や重要問題、効率的な学習法など試験に合格するためのあらゆるノウハウを持っているため合格へ確実に近づいていくことができます。
また、学習スケジュールを一緒に立ててくれるところが多いので、勉強時間が足らず学習が間に合わないといったことも防げるでしょう。
ここでは、予備校と通信講座、それぞれの特徴を解説します。
予備校に通う
先述の通り、独学以外の勉強法といえば「予備校に通う」方法が挙げられます。
実際に通学し、講師の先生の授業を直接聞いたり、指導を受けながら学習することができるので、自分で勉強計画を保つのが苦手という方や、モチベーション維持に不安があるという方におすすめです。
通学する時間の制約や、受講料金が高い傾向にあるというデメリットがありますが、カウンセリングや、講師の指導により質の高い授業を受けられるというのは魅力的です。
また、予備校に通う人同士でつながりが生まれるというメリットもあり、資格試験も受験と同様仲間がいると悩みを共有したり質問し合ったりするなどして高め合うことができます。
行政書士は将来的に人との繋がりが重要視される職業でもあるので、学習面以外でも様々なメリットがあるといえるでしょう。
通信講座を受講する
もう一つの勉強法が『通信講座の受講』する勉強法です。
予備校に比べて、費用や時間の両面で制約が少ないため社会人の方や日常生活が忙しいという方におすすめの勉強法となっています。
独学と違い、学習のカリキュラムや教材などが事前に用意されているため、教材を選ぶ手間や、学習の方向性がズレにくいといったことがメリットです。
また、講座によっては講師にネットを通して質問することができたり、web上で講師の指導を受けることができたりと、予備校に劣らない質の高い講義を受けることもできます。
通信講座の場合隙間時間を利用して学習する利用者が多いことから、スマホに対応した学習ツールの提供や、いつでもどこでも動画講義を視聴できる体制が整っていたりといった利便性が魅力的です。
一方で、予備校に比べてサポートは講師に投げかけた質問の返答に時間がかかるなど手薄な場合が多く、また他の受験生とのつながりを得ることもできないのでモチベーションの低下や、学習スケジュールをいかにこなせるかといった枷があるというデメリットはあります。
特にオススメなのは通信講座
独学で行政書士試験合格を目指す方は、「お金をあまりかけたくない」か「まとまった勉強時間の確保が難しい」場合がほとんどでしょう。
そのような方に向いている勉強法は通信講座で行政書士試験の対策を取ることです。
通信講座は予備校と比較しても受講料が安く、講義はオンデマンド配信でスマホやPCで視聴できるため時間と場所を選びません。
独学の場合の勉強スタイルとも近く、無駄なストレスがかからずに学習できるのでおすすめの勉強法となっています。
行政書士試験講座はアガルートアカデミー!

通信講座を利用して行政書士試験合格を目指すなら、オススメはアガルートアカデミーです。
アガルートは2015年に開講した新進気鋭の資格試験向け通信講座です。アガルートの「行政書士試験講座」の強みは56.17%(全国平均の4.63倍)という高い合格率と合格が1年で目指せるところにあります。
アガルートの勉強法の特徴は以下の3つを柱とした徹底的な合理化です。
- 最小限に絞った講座体系
- 最良のテキスト
- 使いやすい受講環境
アガルート「行政書士試験講座」の特徴①:最小限に絞った講座体系
アガルートの「行政書士試験講座」は、試験合格に必要なすべてのカリキュラムを一つにして提供しています。
試験合格に必要な内容“のみ”を厳選しているため講座毎で内容が重複することもなく、関連性を持っているため効率的に学習ができます。
また、過去の択一式・記述式試験の傾向を講師と教材制作の専門スタッフが共同で分析しているためインプットとアウトプットがバランス良く盛り込まれています。
受講生のレベルに合わせた3つのコースが用意されているため初学者も経験者も過不足なく学ぶことができ、最も自分に合った勉強をすることが可能です。
アガルート「行政書士試験講座」の特徴②:最良のテキスト
アガルートの期間講座はフルカラーテキストを用意しているため初学者でも視覚的にわかりやすく、かつ楽しく学習することができます。
また、アガルートの令和4年度試験の出題カバー率はなんと97.8%です。
法令等科目の記述式問題も的中しているためアガルートの教材を使用して学習するだけで合格を狙うことができます。
アガルート「行政書士試験講座」の特徴③:使いやすい受講環境
オンライン特化したアガルートはスマホやPCでも学習しやすいよう、再生速度の倍率変更やしおりをつけられる、テキストと動画を同時表示できるなど便利な環境が整っています。
講師への質問は無料質問制度で直接聞けるため不安もありません。
学習上のよくある悩みや択一と記述の予想問題を解く「直前ヤマ当てフェス」など、日々の学習を助けるサポートも満載です。
アガルートなら、合格のノウハウが詰まった充実の授業をいつでもどこでも受講できます。
行政書士試験講座の講座内容
アガルートでは非常に細かくレベル分けがなされており、受講者のレベルや受験までの期間に応じて様々なカリキュラムの中から選択して受講することができます。
初心者向けのコースでも1年間の勉強時間で合格を目指せるスケジュールが組まれているので最短合格を目指す方には非常におすすめです。
入門カリキュラム

入門総合講義/入門総合カリキュラム(フル・ライト)は本格的に行政書士試験の学習をスタートする方向けの短期合格カリキュラムです。
初めて法律の学習をする方やもう一度基礎から知識を得たい方、ブランクのある方におすすめのカリキュラムとなっていて、行政書士の知識をゼロから丁寧に学ぶことができます。
入門総合講義の講師は豊村慶太講師と相賀真理子講師のどちらかが担当し、ガイダンスやサンプル講義を試聴した上で自分に合う講師を選ぶことができます。
充実のサポートと頼れる講師で行政書士試験1年合格を目指しましょう。
| コース名 | 入門総合講義 | 入門総合ライトカリキュラム | 入門総合フルカリキュラム |
|---|---|---|---|
| 講座内容 | 入門講義 |
入門講義 短答過去問解説講座 記述過去問解説講座 『択一式対策完成への問題』解説講座(民法) 模擬試験 |
入門講義 短答過去問解説講座 記述過去問解説講座 『択一式対策完成への問題』解説講座(民法) 模擬試験 逐条ローラーインプット講座 文章理解対策講座 |
| 講座料金 | 184,800円 | 228,800円 | 261,800円 |
中上級カリキュラム
中上級総合講義/中上級総合カリキュラムは行政書士試験の学習経験がある方が、一気に合格レベルまで学力を上げるためのカリキュラムです。
過去問を6割以上解ける方や問題演習に力を注ぎたい方、仕上げを頑張りたい方はこちらのカリキュラムで最後の追い上げを行うといいでしょう。
中上級カリキュラムは豊村慶太講師が受け持ちます。
| コース名 | 中上級総合講義 | 中上級総合ライトカリキュラム | 中上級総合フルカリキュラム |
|---|---|---|---|
| 講座内容 | 中上級総合講義 |
中上級総合講義 総まくり択一1000肢攻略講座 総まくり記述80問攻略講座 模擬試験 |
中上級総合講義 総まくり択一1000肢攻略講座 総まくり記述80問攻略講座 模擬試験 逐条ローラーインプット講座 文章理解対策講座 |
| 講座料金 | 272,800円 | 316,800円 | 360,800円 |
上級カリキュラム
上級総合カリキュラム(フル・ライト)は合格まであと一歩の方が余裕を持って合格するためのカリキュラムです。
行政書士試験の知識が定着していて本試験で160点前後獲得できる方、中上級レベルの他社講座を7割以上マスターしている方にはこちらのカリキュラムをオススメします。
他の受験生にはない確固たる知識レベルで自信をつけたい方も上級カリキュラムで学習するといいでしょう。
| コース名 | 上級総合ライトカリキュラム | 上級総合フルカリキュラム |
|---|---|---|
| 講座内容 |
図表まとめ講座 「START UP 判例」解説講座 行政書士試験過去問ベストセレクション講座 他資格試験過去問ベストセレクション講座 総まくり記述80問攻略講座 模擬試験 |
図表まとめ講座 「START UP 判例」解説講座 行政書士試験過去問ベストセレクション講座 他資格試験過去問ベストセレクション講座 総まくり記述80問攻略講座 模擬試験 逐条ローラーインプット講座 文章理解対策講座 |
| 講座料金 | 217,800円 | 261,800円 |
こちらの記事では各コースの詳細やアガルート行政書士講座の評判・口コミなどを紹介していますのでより詳しく確認したい方はご覧ください。
お得なセールや割引・合格特典あり!
アガルートでは期間限定の割引セールや常設の割引があり、タイミングによっては最大30%OFFで受講することも可能です!
また、受講生が合格した際は受講料全額返金や、合格祝い金といった豪華な特典を受け取ることができるのでモチベーションの維持にも最適でしょう。
セールやクーポンは以下の記事で最新の情報を紹介していますので、ぜひご確認ください!
行政書士試験合格に必要な勉強時間|まとめ
- 行政書士試験は難しく、多くの勉強時間がいる
- 初心者で500~100時間の勉強時間が必要とされている
- 試験本番に学習が間に合わないことを防ぐためにもスケジュール管理が大切
- 3つの勉強法があるが、おすすめの勉強法は「通信講座」
- アガルートなら1年間で合格を目指せる
行政書士試験は多くの勉強時間を必要とする試験で、勉強したことがある人でも300~500時間の勉強時間が必要であり、初心者だと500~1,000時間程度の勉強時間がないと合格は難しいです。
試験日に間に合わなかったということがないように、勉強時間は少し長めに考えておくと良いでしょう。
勉強法は「独学」「予備校」「通信講座」の3つがあり、独学での合格もできますが難易度の高い勉強法となるので、料金が比較的安くすむ「通信講座」がおすすめの勉強法になります。
ただし行政書士試験は初心者でもしっかりと正しい勉強をすれば1年間の勉強時間で一発合格を目指せる試験なので、最短合格を目指したいという方はアガルート公式HPから資料請求してみてはいかがでしょうか!
行政書士試験については、以下のページでも詳しく紹介しています!
- 行政書士を偏差値で表すと難易度はどれくらい?他資格との違いも徹底調査
- 行政書士試験の配点や合格点は?試験内容や出題範囲についてご紹介!
- 行政書士試験は簡単?試験の詳細や実際の仕事内容を徹底解説!
- 行政書士は稼げないって本当?高収入を得るための方法を解説!
今なら完全無料!年収UPのチャンス!
-
大学・専門学校で手に職を付ける
 (高校生向け)スタディサプリ 進路
(高校生向け)スタディサプリ 進路
 (社会人向け)スタディサプリ 社会人大学・大学院
(社会人向け)スタディサプリ 社会人大学・大学院
-
既卒者向け!20代の就職サポート
マイナビジョブ20's アドバンス
-
初めての転職をサポート
マイナビジョブ20's
-
年収800万~の求人多数!登録するだけ
リクルートダイレクトスカウト
-
転職エージェントによる徹底サポート
doda