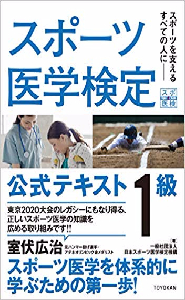現在、様々なスポーツの競技において、老若男女を問わず多数のアスリートが大活躍しています。
しかし、スポーツをするうえで切っても切り離せないのが”ケガ”です。
スポーツをする以上、ケガをしないということはほぼ不可能ですが、ケガを減らすことはできます。
そこで作られたのが『スポーツ医学検定』です。この検定の難易度や合格率はどのくらいでしょうか?また、過去問や活かせる就職先についても徹底調査します!
スポーツ医学検定とは何か?
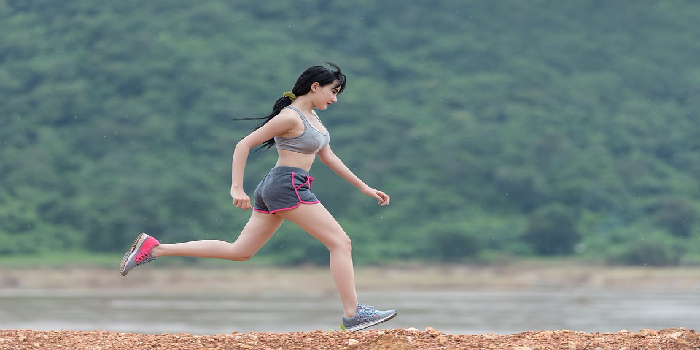
皆さんは、スポーツをすることが好きでしょうか?
2020年、東京オリンピックとパラリンピックの開催が目前となる中、スポーツへの関心は日々高まりを見せています。
また、インターネットの普及に伴い、かつては知名度や注目度も低かったスポーツがクローズアップされ、選手の活躍や面白さが知れ渡って競技人口の加速につながっているケースも多々見受けられます。
そのような中でも、スポーツをする以上は”ケガ”がつきものですね。
夢中になりすぎるあまり、もっと上手になりたいあまり、無茶をしてケガをした経験がある人も多いと思われます。
そこで今回は、『スポーツ医学検定』という試験の内容や合格率についてご紹介します!
スポーツ医学検定はどうしてできた?
スポーツ医学検定とは、身体のことに加えてスポーツを行なうことによって負ったケガに関する知識を問われる試験となっています。
これは一般の人が対象になっていて、スポーツ医学検定に合格したからといって実際に治療や診療など、医療行為を行なうことはできませんのでご注意ください。
スポーツでケガをすることを減らし、より楽しくスポーツができる安全な環境を作るべく、スポーツ医学に関する知識をスポーツの現場にいる人たちに広まってほしいという目的があって作られた検定試験となっています。
この検定を受験することによって、ケガを予防すること、ケガを乗り越えて競技に復帰すること、競技をする力を向上させることなどに活かすことができます。
検定を主催している『一般社団法人 日本スポーツ医学検定機構」は、スポーツで指導者の立場にある人や選手自身のみならず、保護者やメディカルの関係者にも受験してほしいと促しています。
スポーツ医学検定の詳細

スポーツ医学検定は、春と冬の年2回にわたって実施されています。
試験の形式はマークシートになっていて、問題に記述式はなく、実技試験もありません。
持っている資格や職業についても問わず、誰でも受験することができます。その他の詳細は次のとおりです。
実施される級とレベル
スポーツ医学検定は、1級から3級に加え、Web検定で常時受験することができる初級(ビギナー)の4つに分かれています。
それぞれと特色として、3級(ベーシック)は身体のことやスポーツでのケガなど最も基本的なことを問う試験となっています。
スポーツ医学について、初めて学ぶ方や部活でマネージャーを務めている方、選手本人、成長期の選手を育てる保護者の方などがこの級を受験することを勧められています。
2級(アドバンス)は、3級よりもより詳しく幅広い知識が問われる試験です。スポーツ・体育系の学生や、指導者、部活の顧問を務めている方々におすすめです。
1級(マスター)は、専門的な知識が問われる試験となっています。スポーツ医療に関わっている方や、将来は関わりたいと考えている方々が受験を勧められています。
また、初級(ビギナー)についてはWeb検定となっていて、いつでも受験することができます。
こちらは身体やケガについて初歩的な知識を問う試験となっていて、合格すると自分で印刷できるPDFファイルの合格証がもらえます。
スポーツ医学検定の難易度
スポーツ医学検定の難易度についてですが、受験者によると初級に関してはあまり難しく捉えていない人が多かったようです。
「テキストなどはしっかりと一読しておいた方がいい」との声がある一方で、元からスポーツに関する知識をある程度持っている場合は、Web検定の合格はわりと簡単なのではないかとの意見もあがっていました。
2級3級ともなると込み入った知識も必要となってくるので、「テキストをすべて覚える気持ちでいこう」とのアドバイスもありました。
難易度が高いか低いかは人それぞれのようですが、かつてはテキスト以外からの思わぬ出題もあったそうなので、油断せずに勉強は怠らない方が良いと言えますね。
スポーツ医学検定の合格率
スポーツ医学検定は、web検定の初級が80点以上で合格、他の級も70〜80%を合格基準としています。
ある年のメールマガジンで発表された合格率は、3級が90%、2級が60%だったそうです。
3級に関してはかなり高い合格率となっていますね。
2級になると少しは内容も複雑になるからか、30%も合格率が下がる結果となっています。
ちなみに1級は、2019年の春にはじめて開催される予定のため、合格率はまだ不明の状態です。
身近なスポーツのことだからこそ、「もう分かっているから」とこれまで得た知識に固執してしまうかもしれません。
しかし、新たな知識もたくさん得るつもりで、覚え直しを含めて受験対策を取った方が良さそうです。
合格率がすべてではありませんので、あまり気にせずに勉強に取り組みたいですね。
スポーツ医学検定の過去問
日本スポーツ医学検定機構のホームページに、2級と3級の練習問題がPDFファイルとしてあります。
試験後はマークシートの返却もしていないため、過去問についてはテキストや練習問題をフルに活用した方が良いでしょう。
公式テキストはこちらです。
スポーツ医学のことをはじめて学ぶ人にも分かりやすく、イラストも交えて解説しているこちらの一冊。
専門書ではないので、誰でも読みやすい形となっています。
「資格を取るためには最適の本」「勉強になる」「この本を理解すれば、大概のアクシデントにも対応できるのでは」といったコメントが寄せられています。
過去問ではありませんが、しっかりと熟読することで十分に自分の合格率を上げられる書となっています。
こちらの公式テキストは、スポーツ医学の基本的な知識があることを前提として、専門的な内容を含めた解説が記載されています。
内容に深みがあり、より広くスポーツ医学を学ぶために有効の書です。
前述のとおり、スポーツ医学検定の1級は、2019年にはじめて開催されるために合格率もまだ分からない状況です。
テキストも1月に発刊されたばかりなので、まずはこれを理解することに重点を置きましょう。
スポーツ医学検定は就職に使える?
スポーツ医学検定はまだ歴史が浅く、この検定を持っているから就職に有利などといった声は少ないようです。
しかし、部活の顧問や指導者の立場にある人や、スポーツ医療の分野に携わる方は取得を勧められているため、スポーツ関係の仕事に就いている人には有利な資格だと言えますね。
いつしか、この資格を活かして多くの就職口が開く日が来るといいですね。
スポーツ医学検定についてのまとめ
スポーツの現場において、指導者や選手を監督する立場にない一般の人であっても、スポーツ医学検定で学んだことを活かせることは多いはずです。
スポーツ以外でも、身体のことやケガのことは誰もに関係があることです。
今後、この検定試験の受験者が増えると、合格率や就職に関しても数字が大きく変わってくることでしょう。
ケガを未然に防ぎ、皆が楽しく汗を流せるスポーツライフを送りたいものです。