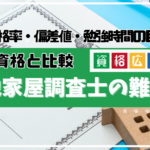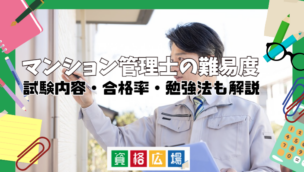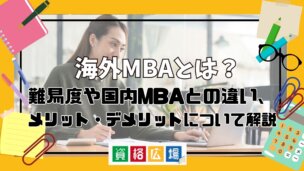土地の測量業務や不動産情報の申請の専門家である土地家屋調査士になるためには、土地家屋調査士試験に合格する必要があります。
そこで今回こちらの記事では土地家屋調査士試験の試験日程や試験会場、試験内容についてご紹介します!
加えて土地家屋調査士試験を受験する際の受験資格も調査いたしましたので、何もわからない方でもこの記事を読めば多くのことが知れるはずです。
合格基準点や働きながら資格を取得するためのポイントもあわせてご紹介しておりますので、土地家屋調査士試験を受験しようと考えている方は是非参考にしてみてください!
土地家屋調査士試験におすすめの通信講座
土地家屋調査士試験の日程

こちらでは土地家屋調査士試験の試験日程や合格発表日などについてご紹介します!
土地家屋調査士の試験は1年に1度実施される国家試験のため、試験日を逃してしまうと来年まで受験できなくなるのでしっかりと確認しておきましょう。
| 管轄省庁 | 法務省 |
|---|---|
| 扱う法律 | 土地家屋調査士法、基本六法 |
| 受験資格 | 制限なし |
| 試験日程 | 筆記試験 2023年10月15日(日)(予定) 口述試験 2024年1月25日(木)(予定) |
| 独占業務 | 不動産の「表示に関する登記」 |
| 全国の調査士の数 | 約16,000人 |
下記では土地家屋調査士試験の各日程について解説をしていきます。
申し込み期間や合格発表日はいつ?
申し込み期間や合格発表日は以下の通りです。
| 試験日程 | 筆記試験 例年10月第3日曜日 口述試験 翌年1月中旬 |
|---|---|
| 申し込み期日 | 2023年7月24日(月)~ 2023年8月4日(金)(予定) |
| 筆記試験合格発表日 | 2024年1月10日(水)(予定) |
| 最終合格発表日 | 2024年2月(予定) |
上記の通り筆記試験と口述試験はそれぞれ別々の日程で行われます。筆記試験は「午前の部」と「午後の部」から構成されており、同じ日に試験が行われます。
例年では、筆記試験は10月第3日曜日に行われ、口述試験は翌年の1月中旬に行われています。合格発表は筆記試験が1月の初旬から半ばに行われ、最終合格発表は2月の中旬に行われます。
以下では申し込み期日やそれぞれの合格発表について深堀って説明をしていきたいと思います。
申し込み期日
申込期日は例年7月第4週の月曜日又は第5週の月曜日~8月第1週の金曜日までとなっています。
申し込み方法には2種類の方法があり、窓口での受付と郵送での受付となっていますが窓口の受付には受付時間が設定されています。
受付時間は土日祝祭日を除く、午前8時30分~正午までと午後1時~午後5時15分までとなっています。正午から午後1時までの時間は受付をしていないので注意をしましょう。
郵便での申し込みの場合は申込期日最終日までの消印があるものに限り受付が認められます。申し込み期限が過ぎていて来年の受験まで待たなければならないということがないようにしましょう。
筆記試験の合格発表について
筆記試験の合格発表は例年1月の第1週の水曜日か第2週の水曜日に午後4時から行われています。合格発表の方法は以下の通りです。
①法務局又は地方法務局での掲示
②法務省ホームページ
③受験者への通知
法務局または地方法務局、法務省のホームページにて合格を確認することができ、受験者にも合格通知として、口述試験を行う試験会場から口述試験の受験票が届きます。
合格を確認したにもかかわらず受験票が送られてこない場合は、口述試験を実地する法務局の総務課まで問い合わせて下さい。
口述試験合格発表日について
口述試験合格発表日は例年2月の中旬に行われています。
口述試験合格の発表方法は以下の通りです。
①法務局又は地方法務局での掲示
②法務省ホームページ
③官報への公告
上記の①、②の方法は筆記試験合格発表方法の①、②と同じです。
官報への公告では例年3月下旬に官報に最終合格者の受験番号及び氏名が掲示されます。早く合否の結果が知りたい方は法務省のホームページで確認をしましょう。
土地家屋調査士の試験会場はどこ?
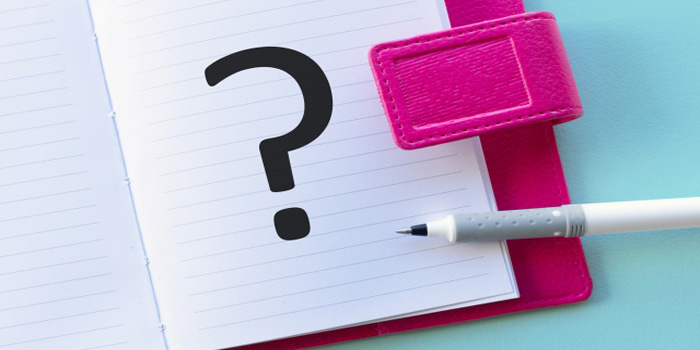
土地家屋調査士の試験会場は全国9都道府県で実施されます。試験会場の多くは、大学や専門学校などの教室型の施設で実施されることが多いです。
全国9都道府県は以下の通りです。
東京、大阪、名古屋、札幌、福岡、那覇、広島、仙台、高松
全国9都道府県以外の場所に住んでいる方々は県外での受験となるので、どの会場が一番近いかを確認しておきましょう。
那覇会場では口述試験が実施されない
那覇会場では口述試験が実施されません。
那覇会場で筆記試験を受験し合格した場合は福岡会場で口述試験が実施されるため、那覇で受験された方は注意しましょう。
筆記試験の合格が確認できたら、福岡会場の近くのホテルなどを早めに予約をして試験に望む準備をしておくと良いです。
試験会場は7月初旬に分かる
7月初旬に各受験地管轄の法務局より試験案内がされます。試験案内には試験会場の場所が記載されているのでしっかりと確認をしておきましょう。
試験会場の多くは大学や専門学校で行われたり、合同庁舎や会議場が試験会場となることが多いです。
また、会場は各場所に1つというわけではありません。試験会場の定員に達した場合は別の試験会場が指定されるので、自分がどこの試験会場で受験するのかをしっかりと把握するようにし、試験が受けられなくなるといったことがないようにしましょう。
試験会場に着いてやるべきこと
試験会場についたら自分が試験を受験する部屋と席を確認をし、試験で使う関数電卓や三角定規、全円分度器、黒インクのボールペンのインクの量などを確認しましょう。
また、関数電卓やボールペンなどは予備を用意しておくと問題を解いている際に壊れたりしたとしても安心して試験に望むことができます。
試験開始40分前ぐらいから特に男子トイレが混むことが多いので、お手洗いなどは早めに済ませるようにしましょう。
土地家屋調査士試験に受験資格はある?

土地家屋調査士以外の士業の試験では受験資格に大卒であることなどが挙げられていることもありますが、土地家屋調査士の受験資格はどうなっているのでしょうか。
これから試験に挑戦する予定で受験資格が気になっている方はぜひご覧ください!
土地家屋調査士試験に受験資格はない
結論から述べると年齢、性別、学歴等の条件がないため受験資格の制限はありません。
そのため誰もが試験の受験資格を持っており、難関とも言われる試験に突破できれば土地家屋調査士として活躍することができます。
しかし、受験資格の制限はありませんが土地家屋調査士として働くにはいくつかの条件があります。
この条件を満たしていないと例え受験資格があって試験に合格しても土地家屋調査士として働けないので今一度ここで確認をしておきましょう。
未成年者は資格を取っても働けない
未成年者は土地家屋調査士として働くために必要な土地家屋調査士名簿の登録が出来ません。
それは土地家屋調査士法の第五条の欠格事由で定められているからです。
未成年の時に資格を取得した方は成人になってから土地家屋調査士名簿の登録が可能になり、働くことが出来るようになります。
土地家屋調査士法の第五条の欠格事由に定められている条件は未成年者以外にもあり、その条件に該当する方は資格が認められません。
受験資格があって試験に合格しても条件に該当していて土地家屋調査士として働けないといったことがないように下記の条件をしっかりと確認しておきましょう。
土地家屋調査士法
第一章 総則
(欠格事由)
第五条 次に掲げる者は、調査士となる資格を有しない。一 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつてから三年を経過しない者
二 未成年者
三 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
四 公務員であつて懲戒免職の処分を受け、その処分の日から三年を経過しない者
五 第四十二条の規定により業務の禁止の処分を受け、その処分の日から三年を経過しない者
六 測量法(昭和二十四年法律第百八十八号)第五十二条第二号の規定により、登録の抹消の処分を受け、その処分の日から三年を経過しない者
七 建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)第十条の規定により免許の取消しの処分を受け、その処分の日から三年を経過しない者
八 司法書士法(昭和二十五年法律第百九十七号)第四十七条の規定により業務の禁止の処分を受け、その処分の日から三年を経過しない者
未成年の方であればまず測量士補
未成年の方にも受験資格がある土地家屋調査士試験ですが、高校生といった方にとっては非常に難しい試験であるとも言えます。
合格しても働くのは難しいため、まずは同じ業界の資格で受験資格の制限がない測量士補の資格を受験してみてはいかがでしょうか。
この資格に合格すると土地家屋調査士の試験で大きなメリットがあり、午前の部の試験を免除できるのです。
毎年この制度を多くの方が利用しておりますので、未成年の方でも受験資格があるからといって焦らないのをおすすめします!
→土地家屋調査士試験の試験科目は?午後の部の難易度も徹底解説!
土地家屋調査士講座ならアガルートアカデミーがおすすめ!
土地家屋調査士を目指すならアガルートアカデミーがおすすめです!
フルカラーで見やすいテキスト教材と分かりやすい動画講義で、初めて資格勉強をする方でも充分合格が目指せるカリキュラムになっています。
合格者には受講費全額返金orお祝い金5万円の得点もあるのでモチベーションの維持も期待できます!
最短ルートで合格が目指せる!
アガルート公式HPはこちら
土地家屋調査士の試験時間は何時間?

筆記試験「午前の部」「午後の部」、口述試験の試験時間は以下の通りです。
| 試験科目 | 所要時間 | 開始時刻 |
|---|---|---|
| 筆記試験「午前の部」 | 2時間 | 9時30分~11時30分 |
| 筆記試験「午後の部」 | 2時間30分 | 13時00分~15時30分 |
| 口述試験 | 15分~20分 | 口述受験票に記載 |
土地家屋調査士法施行規則の改正により、令和3年度から午前の部は午前9時00分、午後の部は午後0時30分までに着席をしなければならないので試験会場には遅くても1時間前に余裕を持って会場入りするようにしてください。
また、午前の部は午前9時15分、午後の部は午後0時45分までに試験室に出頭していない場合は受験することが出来なくなるため注意が必要です。
試験開始30分前くらいから退出できなくなるのでトイレにはしっかり行っておきましょう。
土地家屋調査士の試験は問題数に対して試験時間が短いので、過去問を解き始める段階で時間配分も意識して学習を進めていくと良いです。
土地家屋調査士試験の試験科目

土地家屋調査士の試験は「民法」や「不動産登記法」といった暗記が必要な科目や土地の測量計算に関する問題で構成されています。
細かな法律を覚える知識量と、測量計算の正確さが求められる試験となっています。
以下では土地家屋調査士試験の試験科目についてそれぞれ説明をしていきます。
午前の部は測量がメイン
午前の部試験科目は以下の通りです。
| 試験科目 | 解答形式 | 問題数 | 配点 |
|---|---|---|---|
| 平面測量 | 多肢択一式 | 10問 | 60点 |
| 作図 | 図面作成 | 1問 | 40点 |
| 合計 | 11問 | 100点 |
午前の部は土地家屋の調査及び測量に関する知識と技能が問われます。
平面測量の問題がメインに出題され、関数電卓を使った計算が多く出題されます。作図の出題では問題に合わせて内容が変化するので慣れが必要です。
「午前の部」は試験免除が受けられる?
筆記試験「午前の部」は試験内容が難しいうえに学習しようにもそれに関するテキストや問題集というものがほとんどありません。そのため受験者の9割の方が午前の部の試験の免除を受けています。
午前の部は該当者に限り免除を受けられる制度があります。免除対象となるのは下記の方です。
①特定の資格を所有している者
②前年度に行われた土地家屋調査士試験で筆記試験を合格した者
③午前の部の試験合格した者同等以上の知識及び技能を有する者として法務大臣が認定した者
上記の①特定の資格とは「測量士」「測量士補」「一級建築士」「二級建築士」の4つの資格です。また試験の免除をうけるには事前に申請をする必要があるため要項を確認し忘れずに申請を行いましょう。
測量士補の資格の取得がオススメ
測量士補の合格率は約30%と上述の①の特定の資格の中で一番難易度が低く取得しやすいため、測量士補の資格を取得し午前の部の試験免除を受けられている方がほとんどです。
中には同年の測量士補試験と土地家屋調査士試験のダブル受験で一発合格される方もいます。
午後の部は不動産登記法がメイン
| 試験科目 | 解答形式 | 問題数 | 配点 |
|---|---|---|---|
| 民法 | 多肢択一式 | 3問 | 7.5点 |
| 不動産登記法(筆界特定1~2問を含む) | 多肢択一式 | 16問 | 40点 |
| 土地家屋調査士法 | 多肢択一式 | 1問 | 2.5点 |
| 土地に関する問題 | 記述式 | 1問 | 25点 |
| 建物に関する問題 | 記述式 | 1問 | 25点 |
| 合計 | 22問 | 100点 |
午後の部は「民法」「不動産登記法」「土地家屋調査士法」の3つの法律科目から50点分の問題が出題されおり、特に不動産登記法は16問で40点と配点が一番高くなっています。
また、「土地に関する問題」と「建物に関する問題」は1問25点の配点となっており、それぞれ登記申請書を書く問題と土地面積の作図の問題が出題されます。
午後の部の試験では出題配点の高い科目を重点的に対策することがおすすめです。
面接形式の口述試験
口述試験は緊張して上手く答えられずに無言になっても試験官が答えまで誘導してくれたりと不合格にしてやるといった姿勢ではないため、全体的に和やか雰囲気で試験が行われます。
口述試験は業務に必要な知識について問われ、1人15分程度の面接方式で実施されます。
質問に対しては簡潔に要点を抑えて答えることや択一式の出題を解けるレベルの知識さえあれば普通に質問に答えられるので定期的に復習をしましょう。
土地家屋調査士試験の合格率と合格基準

土地家屋調査士試験の合格率や合格基準はどのようなものになっているのでしょうか。
試験の結果に深掘りをして分析も行っておりますので、ぜひ最後までご覧ください!
土地家屋調査士試験の合格率
まず合格率について説明をします。土地家屋調査士試験の合格率は概ね8~9%となっています。
土地家屋調査士試験には「択一式基準点」と「記述式基準点」の2つの基準点が設定されており、それぞれの基準点に満たなかった場合は足切り点となり不合格となります。
過去3年間の基準点と合格点は以下の通りです。
| 年度 | 試験 | 択一式基準点 | 記述式基準点 | 合格点 |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 午前の部 | 30.0点 | 34.0点 | 70.0点 |
| 午後の部 | 32.5点 | 33.0点 | 76.5点 | |
| 2020 | 午前の部 | 30.0点 | 32.5点 | 70.5点 |
| 午後の部 | 32.5点 | 30.0点 | 71.0点 | |
| 2021 | 午前の部 | 30.0点 | 30.5点 | 64.0点 |
| 午後の部 | 32.0点 | 30.5点 | 73.5点 |
合格するためには、全体の7~8割程度の得点が必要となっています。
試験に合格する方の属性について
先ほどは簡単に試験の合格率のみをお見せしましたが、実際に試験に合格する方はどのような属性を持った方が多いのでしょうか。
まずは年齢という点にフォーカスして、試験の合格者にまつわる情報を整理してみましょう。
| 令和3年度合格者分布 | ||
|---|---|---|
| 20代 | 16.1% | |
| 30代 | 36.4% | |
| 40代 | 32.9% | |
| 50代 | 12.9% | |
| 60代 | 1.7% | |
最も多い受験者層は30~40代となっており転職によるキャリアアップを狙う方が多いことがわかります。
また合格した方の卒業学部をみても文系・理系が均等に別れており、誰でも挑戦しやすいのが土地家屋調査士試験の特徴であることがわかりました。
相対評価制度の試験
土地家屋調査士試験はあらかじめ合格者数を何名以上と決められた合格点を調整する相対評価となっています。
択一式・記述式でそれぞれ合格できる人数が決められており、択一式が2,000人程度で記述式が700人程度です。
記述式で合格した700人のうち足切り点で300人程度が不合格となるため、合格者は概ね400人程度となっています。
土地家屋調査士の試験が難しいとされる理由

これまで様々な情報をお伝えしてきた土地家屋調査士試験ですが、インターネットなどで検索をすると「難しい」といった声がかなり目立ちました。
そこで、試験の合格を阻んでいるいくつかの理由をご紹介します。
午後試験の専門性が高い
免除制度を使って午前試験をスキップしたとすると、いきなり試験のクライマックスである午後試験から受験することになります。
試験時間が少ない中で問われるのは非常にレベルの高い問題であり、試験の緻密な計算と作図は間違いなく大きな壁です。
けど、相変わらず書式問題の求積と作図に苦手意識がある。
どちらも自己流になってしまっている気がする。
予備校に質問票を出すつもりだったけど、なかなか文章にして伝えるのも難しい。。。
こんな時調査士事務所で働いていたら先生に質問も出来ただろうか。
— TKF (@Tkf0513) July 9, 2019
本番の試験を想定した模擬練習などで時間の間隔をしっかりと掴んでおかないと、本意ではない減点を量産してしまう可能性があります。
法的な知識といったインプットはもちろんですが、アウトプットへの意識の比重も意識した方が良さそうです。
試験時間がタイトすぎる
こちらは午前試験と午後試験に共通する点ですが、土地家屋調査士試験では短い時間のなかで数多くの問題を解く必要があります。
午前試験では2時間の中で択一式10問と記述式1問、午後試験では2時間半の中で択一式20問と記述式2問の問題が問われます。
特に午後試験が鬼門であり、特に記述式試験については自分の思考のクセなども加味してスムーズなアウトプットの練習をしておくことが重要です。
また勉強時間の確保が難しい点も試験の難易度を上げている要因ですが、働きながら合格を目指すことは可能なのでしょうか。
働きながら土地家屋調査士の資格は取得できる?

土地家屋調査士試験の合格率は8〜9%と低い難関の試験ですが、受験者の多くは働きながら学習をしています。
結論から述べると働きながらでも土地家屋調査士試験に合格することは可能です。
しかし働きながら資格を取得することは容易ではありません。働きながら資格の取得を目指す場合は以下の点を踏まえることが大切です。
1.合格目標を設定する
2.1年で合格するのは難しい
3.通信講座を利用する
下記には働きながら資格取得を成功させるポイントについてそれぞれ説明をしていきます。
具体的な合格目標の設定
土地家屋調査士試験の合格を目指すうえで、具体的な合格目標を設定することは非常に重要で、計画性のある学習計画が立てやすくなります。
また、学習に対する意識や行動にも変化が見られ、学習を進めていくうちに自分に何が不足しているのかを考えることができ、努力する気持ちを高めることが可能です。
いきなり、具体的な合格目標を設定をすることが難しいと感じる方は、何年以内に土地家屋調査士の資格を取得するといった大まかな目標を設定し徐々に細かい部分の目標を設定していくと良いでしょう。
1年での合格は難しい
土地家屋調査士試験に合格するための学習時間は一般的には1,000時間程度の勉強時間が必要だといわれています。
1年で合格するためには、毎日3時間程度の学習時間を確保する必要がありますが、働きながら1日3時間の学習を毎日行うことは容易ではありません。そのため1年半~2年の学習期間を設けるようにしましょう。
また、長すぎる学習期間を設定することも良くありません。それは学習期間が長すぎると初めの方に学習したことを忘れてしまい学習しなおす必要があるからです。
最短合格を目指すなら通信講座
最短で合格を目指すなら通信講座の利用がオススメです。隙間時間を利用して学習を進めれることやスマホやタブレットと用いた学習方法のため、好きな場所で学習を行えるからです。また、講座によりますが疑問点を質問できる環境があります。
このように、通信講座を利用すればテキストを選ぶ手間が省くことができたり、添削者がいることや学習項目が明確なので、時間があまり取れない社会人の方にオススメできます。
土地家屋調査士の通信講座について詳しく知りたい方は以下の記事も確認してみてください!
土地家屋調査士試験の試験日程まとめ
・筆記試験の日程は例年10月第3日曜日
・口述試験の日程は例年1月中旬
・午前の部は免除制度がある
・合格率は概ね8~9%
・合格基準点は択一式基準点と記述式基準点の2種類
・最短合格を目指すなら通信講座がおすすめ
土地家屋調査士試験の試験日程や試験会場、試験科目と内容、合格基準点、受験資格について説明をしてきました。
試験科目は「筆記試験」が例年10月第3日曜日に実施され、「口述試験」が例年1月中旬に実施されます。
土地家屋調査士試験の合格率は概ね8~9%となっており合格するためには試験の7~8割以上は正解できるようにしましょう。
働きながら資格を取得する際に大切なことは具体的な目標や計画性のある学習計画をたてることが重要です。また、最短での合格を目指すなら通信講座を利用しましょう。