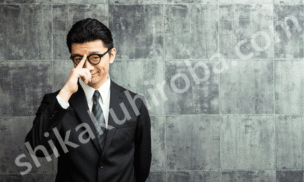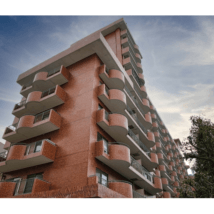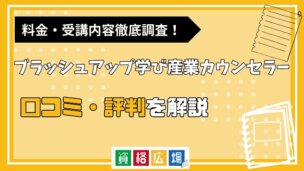宅地建物取引士(通称、宅建士)は不動産業で働く人が持っている資格というイメージが強いのではないでしょうか。実際のところ、『不動産取引に関わる資格』であることは理解していても、具体的に何をしているのか知らないという人も多いでしょう。
そこで今回は、宅建士の年収や、資格が有利になる場面、試験の難易度についてご紹介します。
春から勉強を始めて合格を目指せる資格を探している方にもおすすめの資格ですので、ぜひご一読ください。
宅地建物取引士とは

宅建士は略称であり、正式名称は宅地建物取引士という国家資格です。
宅建士になるためには、毎年20万人前後が受験する最大規模の宅建試験に合格する必要があります。
数ある資格の中でも宅建士の人気が高い理由として、宅建士にしかできない独占業務があること、また設置義務があることが挙げられます。
宅建士は業務独占資格である
業務独占資格とは、特定の資格を持っている人でないと携われない業務を独占的に行える資格のことを指します。
たとえば、業務独占資格として医師や弁護士などが挙げられます。業務独占資格の種類や業務内容などは法律で定められているため、資格のない人がその業務を行うと法律違反となってしまいます。
このような独占業務が宅建士にもあり、宅地建物取引業法によって3つの独占業務が規定されています。
重要事項説明
不動産売買や不動産賃貸借といった不動産取引は、高額な金銭のやり取りや複雑な権利関係が絡むことがあります。トラブルを防ぐためには、物件概要や取引条件などを当事者双方が理解した上で契約に進むことが必要になるでしょう。
そこで、宅建士は不動産売買や不動産賃貸借の契約前に、物件や取引条件に関する重要事項について、買主や賃借人に対して説明する義務を負っています。
重要事項説明では、契約の対象となる不動産の概要や権利関係、取引条件などが説明されます。
重要事項説明書(35条書面)への記名・押印
重要事項説明書の作成・交付を行い、書面に記載された内容に沿って宅建士が買主・賃借人に説明していきます。
この重要事項説明書への記載内容に責任を持ち、記名と捺印ができるのが、宅建士に限られるというわけです。
契約書(37条書面)への記名・押印
宅建士による重要事項説明が終わると、契約へと進みます。不動産の契約では、契約内容を記した不動産売買契約書や賃貸借契約書といった書面の作成・交付が行われます。
契約書に記名・捺印ができるのは宅建士のみであるため、宅建士は不動産取引の際に必要な存在であるといえるでしょう。
宅建士の設置義務
宅地建物取引業者には、事務所ごとに一定の割合で専任の宅建士を設置しなければならない義務が設けられています。
具体的にいうと、事務所や店舗に在籍する社員の5人に1人以上の割合で、専任の宅建士を配置しなければならないという規定です。そのため、宅建士の資格所持者は、宅地建物取引業者において優先的に採用されやすい傾向にあります。
宅建士はこのような独占業務や設置義務があることから、特に不動産業界での就職・転職に困りにくいといえるでしょう。
宅建士の年収は?

独占業務や設置義務など需要の高い宅建士の平均年収は、おおよそ350万円~650万円と言われています。
日本人の平均年収は436万円なので、平均よりやや高い給与水準であると言えます。
もちろん、宅建士の年収は勤務先の業種や規模、採用された際の職種などの条件によっても大きく異なるでしょう。また、働く地域や自身の実力によっても年収が大きく変わります。
次の項目からは、年齢、性別、地域によってどのくらい年収差があるのか見ていきましょう。
年齢別│平均年収
| 年齢 | 平均年収 |
|---|---|
| 20代 | 300万円~380万円 |
| 30代 | 400万円~480万円 |
| 40代 | 500万円~600万円 |
| 50代 | 600万円~650万円 |
| 60代 | 450万円~600万円 |
参考:https://career-picks.com/average-salary/takkenshi-nenshu/
なお、この表にかかれた年収はあくまで平均です。
社員の実績に応じてインセンティブを支給している会社もあるため、20代で年収700万~1,200万円以上を稼ぐ人もいます。
男女別│平均年収
続いて、男女別に平均年収を見ていきます。
宅建士は、ライフイベントによって働き方を左右されることが多い女性からも高い人気を得ている国家資格です
| 性別 | 平均年収 |
|---|---|
| 男性 | 381万円~713万円 |
| 女性 | 278万円~538万円 |
この表では、ボーナス4ヵ月分の支給ありとして計算されています。
男性宅建士の平均収入は381万円~713万円で、女性宅建士の平均収入は278万円~538万円。
男女別での平均年収に差がある要因の1つとして、雇用形態の違いが考えられるでしょう。
とはいえ、宅建士の国家資格を所持していれば就職・転職に有利であることは大きなメリットといえるでしょう。
地域別│平均年収
続いて、都道府県別にも見ていきましょう。
| 地域 | 平均年収 |
|---|---|
| 東京 | 756万円 |
| 大阪 | 648万円 |
| 愛知 | 594万円 |
| (中略) | (中略) |
| 青森 | 432万円 |
| 宮崎 | 432万円 |
| 沖縄 | 432万円 |
参考:https://heikinnenshu.jp/fudousan/takuken.html
首都圏・関西圏・中部圏の都心部は平均年収が高い傾向にありますが、地方の中には日本の平均年収を下回っているところもあります。
トップは東京都の平均年収756万円に対し、最下位は青森・宮崎・沖縄県での432万円。実に200万円以上の開きがあります。
首都圏と地方では不動産の価格に差があるため、会社・個人としての売上にも影響が出やすいと推測できるでしょう。
宅建士の資格が有利に働く場面

ここまで主な宅建士の特徴や年収についてまとめてきました。実際に宅建士の資格はどのような業界で効力を発揮するのでしょうか?
宅建士の資格を生かしやすい業界をまとめました。
不動産業界
宅地建物取引業者は事務所ごとに5人に1人の割合で専任の宅建士を設置する義務があるため、宅建士の資格は不動産業界において重宝されやすいといえます。
宅建士の資格がなくても不動産業界で働くことは可能です。しかし、事務所や店舗に在籍する社員の5人に1人以上の割合で専任の宅建士が必要になるため、資格保有者の方が需要の高いことは間違いないでしょう。
建設会社
宅建業者が自ら売主となって住宅・マンションの販売する場合、買主との契約前に宅建士による重要事項説明を行わなければなりません。
つまり、独占業務を持つ宅建士の資格が必要になるため、宅建士を持っていると大きなアドバンテージになるといえるでしょう。
また、宅建士の資格を持つことで不動産取引における重要な知識が身に付くため、物件販売に活かしやすいメリットもあります。
金融機関
銀行や信用金庫などの金融業界においても、宅建士の知識は有用です。
例えば、住宅ローンの貸し出し業務を考えてみましょう。銀行側はお客様が購入する土地や建物がどれくらいの価値があるものなのか、いくらまで貸し出すことができるのか審査をしなればなりません。
担保を必要とする融資業務では、融資を判断するために不動産に対する適切な知識や鑑定力が必要となります。
宅建士は、このような業務にも役立つ資格であるといえるでしょう。
その他資格手当が貰えることも!
資格を取得すると「資格手当」が支給される企業もあります。
企業によって金額は異なりますが、宅建士における資格手当の相場は1~3万円。年間12万円~36万円の収入アップが見込めるでしょう。
宅建士の資格を取ったほうがいい人とは

宅建士の資格は多くの企業や業界でも必要とされていることから、所持していることで有利に働く場面が多いといえます。
続いて、宅建士資格の取得を目指すべき人はどんな人なのかご紹介します。
宅建士の資格を必要としている企業や業界も多いため、所持していることで有利に働く場面もあるでしょう。
ここでは、宅建士資格の取得を目指すべき人はどんな人であるかご紹介します。
転職をしたい人
不動産業界に転職したいと考えている人にとって、宅建士の資格は転職活動において自身の市場価値を高める武器になるといえるでしょう。
まだ資格を取得していない場合でも、採用担当者に勉強中であることを伝えると心証が良くなる可能性があります。
また、宅地建物取引業者は2021年3月時点で全国に12万7,215もの数があります。
業者数が多いということは、不動産業界で働く営業マンの数も多いということ。しかし、意外にも宅建士資格を持って働いている不動産営業マンはそれほど多くはないのです。
先ほどにもご紹介したように、宅地建物取引業者では事務所・店舗ごとに一定の割合で専任の宅建士を設置する義務があるため、宅建士の資格を所持しているだけで採用率がアップしやすくなるといえます。
なお、宅建士の資格がなくても不動産業界で働くことは可能となっており、不動産業界に転職してから宅建士を目指そうと考える人もいるでしょう。
しかし、不動産業界に転職したものの勉強時間が思うように取れず、なかなか合格できずにいる人も存在します。
不動産業界への転職を考えている人は、勉強時間の確保ができるのであれば転職前の取得を検討してみましょう。
就職を有利にしたい大学生
宅建士の資格は、不動産業界・金融・保険業界に就職したいと考えている大学生にもおすすめです。
宅建試験は受験資格がないので大学生でも受験できます。また、国家資格を取得しているとその他の人よりも面接官の印象に残りやすくなるでしょう。
宅建士の取得を考えている場合は、就活時期になってガクチカや履歴書に書く資格がない!と焦ることがないように、計画的に勉強を進めておくことをおすすめします。
国家資格である宅建士の合格率はおおよそ15%前後。誰にでも取れる資格ではありませんが、1日1,2時間ずつ勉強すれば十分合格を目指せる数値です。
大学3年次の春~夏に勉強を始めれば、半年の時間があるので十分資格取得を目指すことが可能です。そうすれば、大学4年時の就職活動にも間に合うでしょう。
宅建士の資格を取得することで、他の就活生よりも即戦力となる知識があることを証明できるでしょう。さらに、資格合格に向けた計画性、実行力、意欲の高さなども評価されやすいといえます。
キャリアアップしたい人
不動産会社によっては、キャリアアップの条件に宅建士の資格取得を掲げているところもあります。
昇進し役職に就くと役職手当が支給され、それに伴い年収も上がっていきます。また、宅建士の資格があると重要事項説明から契約締結までお客様を一貫してサポートをすることが出来るため、お客様からの信頼も厚くなります。
お客様からの信頼を得て確実に契約に結び付けることができれば、昇進につながりやすいといえます。そのため、不動産会社でのキャリアアップを考えている人は、できるだけ早く資格を取得するべきといえるでしょう。
宅建試験の概要

ここからは宅建士試験取得を目指す方に宅建試験の概要や、合格率についてご紹介していきます。
| 受験費用 | 7000円 |
| 受験費用 | 1回/年(10月の第3日曜日に実施) |
| 試験時間 | 2時間 |
| 試験内容 | 全問マークシート方式(4肢択一式)、出題数50問 ・民法(14問) ・宅建業法(20問) ・法令上の制限(8問) ・その他関連知識(8問) |
| 合格基準 | 31~38点(50問中)※年度により異なる |
宅建試験は、合格ボーダーが明確に決まっているわけではなく、合格者の割合によって合否が決まる相対評価の試験です。
したがって、問題が難しかったときは合格ラインが下がり、簡単な場合は合格ラインが上がることになります。
宅建士を目指す人は最低でも35点以上を合格基準、余裕をもつならば38点以上を目標にするとよいでしょう。
スケジュールの目安
6月 実施告知
7月 申し込み開始
8月 試験会場通知の送付
10月 宅建試験
12月 合格発表
毎年このような流れで宅建資格は開催されていますので、早め早めの資格取得の為の勉強が必要となります。
気になる合格率・難易度は?
宅建士の合格率は毎年15~17%程度となっています。
司法試験や行政書士などと比べると比較的合格しやすい数値ではありますが、難関資格であることに変わりはありません。
| 実施年度 | 受験者数(人) | 合格者数(人) | 合格率 |
|---|---|---|---|
| 令和2年度 | 204,247 | 34,337 | 16.8% |
| 令和元年度 | 220,797 | 37,481 | 17.0% |
| 平成30年度 | 213,993 | 33,360 | 15.6% |
| 平成29年度 | 209,354 | 32,644 | 15.6% |
| 198,463 | 198,463 | 30,589 | 15.4% |
宅建試験の合格率が低い理由として、受験資格に制限がないため、勉強不足のままでも受験できてしまうことが挙げられます。
また、サラリーマン、主婦、学生など幅広い層が受験して母数が大きくなり、このような合格率になっていることも考えられます。
宅建試験の勉強時間はおおよそ300時間必要とされています。
しかし、試験範囲は広く、特に民法や宅建業法といった法律科目は慣れるまで時間がかかります。
そのため、計画的に勉強していかないと300時間を確保できても試験に間に合わなくなってしまう可能性もあるでしょう。
宅建試験を合格するためには、モチベーションの維持と、計画的な学習が重要といえます。
宅建試験は独学で合格できる?

結論から言うと、独学でも合格することはできます。
ただし、1人で勉強を続けることへのモチベーションの維持やそもそもの法律関係への理解度によって、独学での難易度は大きく異なるでしょう。
300時間を目安に独学で勉強する場合
宅建試験のために独学で勉強した場合、勉強目安である300時間を元にするとこのようなスケジュールになります。
試験までの学習時間300時間の場合
・1時間の場合:10ヶ月(12月中旬頃から)
・2時間の場合:5ヶ月(5月中旬頃から)
・3時間の場合:4ヶ月(6月中旬頃から)
・4時間の場合:3ヶ月(7月中旬頃から)
・5時間の場合:2ヶ月(8月中旬頃から)
なお、上記のスケジュールは、あくまで継続的に「まとまった時間が取れる場合」です。
ある程度時間が取れる方であれば、独学であっても合格を目指すことができるでしょう。
宅建試験の合格を目指している社会人の方が独学で勉強する場合は、まとまった勉強時間の確保が難しかったり、モチベーションを保ちにくかったりすることが多いでしょう。忙しい日々の中で効率的に勉強したい人は、仕事後や電車の中など隙間時間で勉強しやすい通信講座を利用することもおすすめです。
働きながら取得なら通信講座がおすすめ
通信講座の中には、短期間で集中して合格できるようにカリキュラムが設定されているものがあります。また、隙間時間で学習できるように講義動画が10分程度で収められているものもあり、より効率的に学ぶことができるようになっています。
通信講座の相場は18,500円~150,000円程と、運営会社や講座の種類によって値段に幅があります。
独学の場合でもテキスト・問題集代として1~2万円程必要となるため、自身の学習環境やスケジュールから自身に適した学習方法を選択してみてはいかがでしょうか。
宅建試験合格におすすめの通信講座・予備校についてはコチラ!
⇒【宅建】コスパ良く合格するのにオススメな通信講座ランキング3選+α!!
宅建士の年収や試験概要まとめ

今回は、宅建士の年収や、資格が有利になる場面、宅建試験の難易度についてまとめてご紹介しました。
この記事内容のまとめです。
・宅建士は業務独占資格であり、平均年収は350万円~650万円と高め
・取得すると特に不動産業界への転職・就職・キャリアアップに有利
・不動産業界・建設会社・金融機関で従事する人は取るべき資格である
・宅建士になるには、合格率15~17%の宅建試験に合格する必要がある
・社会人の方は隙間時間で効率的に学べる通信講座がおすすめ
宅建士の資格を取得しようと思っている人、春から資格の勉強を始めてみたいと思っている人は、ぜひ参考にしてみてください。
監修者情報
小花 絵里(おばな えり)

不動産会社・住宅メーカーで働いていた経験から、不動産について初心者にもわかりやすく解説する不動産ライター。ブログでは、賃貸併用住宅や戸建て投資に関する記事を更新しています。
所有資格等
宅地建物取引士・賃貸不動産経営管理士・FP2級・日商簿記2級など
公式サイト:https://www.erix.work/