技術士とは、科学技術に関する高い専門的能力を認定する国家資格です。
一括りに技術士と言っても、21もの部門に分かれており、試験も部門ごとに行われます。
技術士は「五大国家資格」の一つでもあり、「弁護士」「弁理士」「医師」「公認会計士」とともに名を連ねるほど難関資格ではありますが、
実際どんなことをしているのか疑問に持たれる方もいると思います。
今回は、技術士の年収や業務についてまとめましたので、ご紹介します。
技術士とは

そもそも技術士とは、
各分野の技術者(科学技術に関する高度な知識と応用能力を有する技術者)を国(文部科学省)が「技術士」として認定するものです。
技術士の歴史は、第二次世界大戦時まで遡ります。
敗戦を喫した日本は、復興と世界平和への貢献を達成するために、「社会的責任をもって活動できる権威ある技術者」の存在が必要となりました。
そうした背景によりアメリカに倣って「技術士制度」が創設され、1951年に日本技術士会が誕生、1957年に「技術士法」が制定され、現在も優れた技術士の育成がなされています。
技術士を取った後は
技術士の資格を取った後は、技術コンサルタントとして活躍する人もいます。
「技術士」は国が認めた技術コンサルサントでもあるからです。
技術コンサルタントとして働く場合は、科学技術に関する顧客の課題を相談・調査を通して発見し、助言や提案を行うことで解決に導きます。
しかし技術士が行う技術コンサルティング業務は、医師や弁護士のように業務独占資格ではないので、資格を持っていなくても行うことができます。
資格を持つことで、技術士は、「技術士法」による規制を受けることから無資格のコンサルタントよりも、信用が得やすいという点があります。
21部門一覧

現在、技術士の専門分野は21部門あります。
試験では、上記の中から1部門を選択し受験します。
複数部門の技術士資格を取得することができるので、多い人では8~9個の部門で資格を持っています。
21部門ある技術士の専門分野の中でも難易度や人気度が上位に位置付けられるのが、総合技術管理部門です。
総合技術管理部門とは
総合技術管理部門は、各専門分野の技術者が自分の持つ能力を最大限に発揮させ、能力を1つに集結させる必要があるという命題のもと、
その目的を達するために、総合的に監督し、判断できる人材を育成するという趣旨で創設されました。
総合技術監理部門の試験では、他の分野とは異なり、マネジメント能力(安全管理や情報管理などの管理技術についての知識やスキル)が要求されます。
5つの管理技術をバランスよく体得することで、広い視野でプロジェクト管理や組織管理を行うことが出来るようになります。
これまで、技術士とはどのような資格で、資格取得後は何をするのかについて見てきました。
続いては技術士の年収についてみていきましょう。
技術士の年収は?
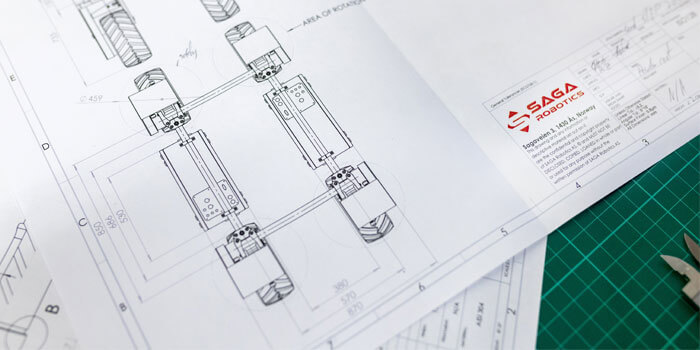
技術士の平均年収は669万円です。
国税庁の調査によると、日本全体のサラリーマンの平均年収は400万円程度となっていますので、技術士の年収は高いと言えます。
また、税理士・公認会計士の平均年収が684万円であり、「医師」「弁護士」「税理士・公認会計士」の次に年収が高い国家資格となっています。
※厚生労働省が発表している統計データによると、毎月決まって支給される現金給与額が439.4千円で、年間賞与その他特別給与額が1396.5千円ですので、単純計算で439.4千円×12か月+1396.5千円=669万円として算出しております。
男女別|技術士の平均年収
では、男女別の平均年収についても見ていきましょう。
| 性別 | 平均年齢 | 平均年収 |
|---|---|---|
| 男性 | 46.6歳 | 652万3400円 |
| 女性 | 39.8歳 | 542万8,600円 |
(「令和元年賃金基本統計」より算出)
※平均年収は、きまって支給する現金給与額×12ヶ月+年間賞与その他特別給与額にて計算しております
年齢別|技術士の平均年収
| 年代 | 年収(男性) | 年収(女性) |
|---|---|---|
| 20~24歳 | 407万円 | - |
| 25~29歳 | 515万円 | 492万円 |
| 30~34歳 | 624万円 | 683万円 |
| 34~39歳 | 646万円 | 628万円 |
| 40~44歳 | 749万円 | 501万円 |
| 45~49歳 | 760万円 | 662万円 |
| 50~54歳 | 770万円 | 634万円 |
| 55~59歳 | 757万円 | 510万円 |
| 60~64歳 | 612万円 | 287万円 |
| 65~69歳 | 529万円 | - |
| 70歳~ | 335万円 | - |
(「令和元年賃金基本統計」より作成)
稼げる技術士とは

給料水準の高い技術士ですが、稼げる技術士とはどのような人なのでしょうか?
企業に所属する技術士の年収についても見ていきましょう。
| 企業規模 | 従業員数 | 平均年収 |
|---|---|---|
| 零細企業 小企業 |
~99人 | 531万5,100円 |
| 中企業 | ~999人 | 578万5,200円 |
| 大企業 | 1000人以上 | 628万5,200円 |
大企業に勤め課長クラスに昇進すると、1000万円を超える年収が見込め、中小企業でも部長クラスになると1500万円ほどの年収を稼いでいる人もいます。
年収が1000万円以上の人は、全国では200万人程度となっており、給与所得者の4%程度となっているので、収入レベルとしては相当高いと言えます。
技術士のメリット

技術士資格を取ることのメリットは、お給料が高いことだけではありません。
メリット①海外でも通用する国際資格である
日本で実施、認定されている資格試験は、日本国内での業務や規定に合わせてあります。
そのため、日本で資格を取得しても海外では通用しない場合がほとんどです。
一方で、海外でも通用するように、海外での業務や規定に合わせてある資格は「国際資格」と呼ばれます。
技術士の資格は、申請によって国際資格の取得が可能になっています。
エンジニアとして、海外で働きたいと考えている場合、国際エンジニアリング資格を保有していることは大きなアドバンテージとなります。
技術士の資格で取得することができる国際エンジニアリング資格は4つあります。
- APECエンジニア
- IPEA国際エンジニア(旧EMF国際エンジニア)
- Euro Engineer
- AER(ASEAN Engineer Register)
メリット②給料が上がる
技術士の資格を取得すると、資格手当を受けられることもあり、直接的に年収が上がることがあります。
また、技術士資格を持っていると、他企業からオファーも受けられるため、業界内の転職が有利になったりします。
より収入の高い企業へとの転職がかなったり、キャリアアップになることは確実です。
メリット③法人ともwinwinな関係
技術士になると、自分自身にメリットがあるだけではなく、法人側にもメリットがあります。
なぜなら、建設業界においては、技術士がいると公共工事をより高い金額で受注できる可能性が高くなるためです。
また、技術士になったものがいる会社では、建設コンサルタント登録が可能になります。
以上のことから、技術士になることは、法人にも多大なメリットを生み出すのです。
技術士のデメリット

デメリット①業務独占資格がない
技術士は、「五代国家資格」の一つではありますが、「医師」や「弁護士」のように業務独占資格がなく、名称独占資格となっています。
つまり、「この資格がないとできない業務」というものがないので、技術士自体の認知度が低く、取得する人が少ないというデメリットがあります。
日本の技術士の総数は約4万人で、米国のプロフェッショナル・エンジニア(約41万人)や英国のチャータード・エンジニア(約20万人)と比較すると、かなり少ないことが分かります。
デメリット②責任が重い
技術士は「技術士法」という法律が適用されるため、技術者として仕事をしている時よりも責任を背負わなければならない場面が増えてきます。
技術士法によると、技術士には3義務2責務というものがあり、これに違反すると懲罰や罰金、資格の取り消しという罰則が科されます。
技術者として働いていれば背負わなかった責務があるということで、技術士資格を取るデメリットと言えます。
デメリット③受験資格が厳しい
技術士においては、二次試験の受験資格が厳しく設定されています。
2)職務上の監督者の指導の下で、4年(総合技術監理部門は7年)を超える実務経験。
3) 指導者や監督者の有無・要件を問わず、7年(総合技術監理部門は10年)を超える期間の実務経験。
このように、二次試験の受験資格には4年以上の実務経験が必要になっています。
実務経験を重ねた技術者が受験生なので、当然難易度も上がってきます。
技術士になるためには

一般的に、技術士に必要な勉強時間は1,000時間程度と言われています。
もっと少ない勉強時間(200時間程度)で合格される方もいらっしゃいますが、このくらいの時間がかかると思っておいた方が安心です。
技術士には、一次試験と二次試験を両方突破する必要があります。
一次試験では【適正科目、専門科目、基礎科目】を受験し、全科目50%以上の得点率があれば合格です。
一次試験においては、例年の合格率は50%前後となっており、2人~2.5人に1人は受かる程度の合格率となっています。
ちなみに、令和元年の一次試験の合格率は、47.6%でした。
難関とは言われている技術士資格ですが、一次試験は勉強すれば1年で合格することが出来ます。
二次試験では、【筆記試験(論述)と、口述試験】が課されます。
一次試験の合格率が50%であるのに対し、二次試験の合格率は例年10〜15%となっています。
技術士試験では、二次試験が最大の関門と言えますね。
二次試験が高難度化しているのは、論述形式である筆記試験の採点基準が開示されていないからです。
一次試験では、マークシートでの択一式であるので独学でも合格はできますが、
二次試験は筆記試験と口述試験であり、見てもらう相手がいない中で勉強を進め、合格に必要な実力をつけるのは難しいと言えます。
したがって、一次試験も二次試験もストレート合格したいと考えている方はオンライン講座を受講するほうが良いでしょう。
オンライン講座では、筆記試験対策として、文章の書き方、答案の回答方法といった点数を取るためのノウハウを身に付けることができ、
口頭試験講座の対策として模擬口頭試験を受験し、フィードバックも受けることが出来るので、独学では手が届かない視点でしっかりと対策することができます。
技術士の仕事や年収まとめ

今回は、技術士の年収や業務、資格をとるメリット・デメリットについてみてきました。
これまでの内容をまとめるとこのようになります。
・技術士とは、文部科学省が認定するエンジニアの最高峰資格
・全21部門の中で、何部門でも取得することが出来る
・技術士の年収は669万円で、男女ともに高水準
・技術士は独占業務がない、知名度は低いというデメリットはあるが、業界では重宝されるためメリットは大きい
・一次試験は独学でも、二次試験は通信講座を受講した方が良い
技術士を目指している人は、ぜひご参考にしてみてください。
今なら完全無料!年収UPのチャンス!
-
大学・専門学校で手に職を付ける
 (高校生向け)スタディサプリ 進路
(高校生向け)スタディサプリ 進路
 (社会人向け)スタディサプリ 社会人大学・大学院
(社会人向け)スタディサプリ 社会人大学・大学院
-
既卒者向け!20代の就職サポート
マイナビジョブ20's アドバンス
-
初めての転職をサポート
マイナビジョブ20's
-
年収800万~の求人多数!登録するだけ
リクルートダイレクトスカウト
-
転職エージェントによる徹底サポート
doda












